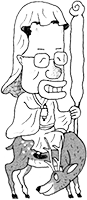
■今回の報告者は、東京農工大学名誉教授・兵庫県森林動物研究センター所長で、知床自然アカデミー(旧知床自然大学院大学設立財団)代表理事の梶光一さん。2006年にも一度報告をしていただき、今回は約19年ぶりの報告となる。
◆北海道大学大学院農学研究科博士課程修了でヒグマ研究グループ、通称「クマ研」の一員だった梶さん。クマ研が発足した1970年、北海道ではヒグマによる人身被害や家畜被害が相次いでおり、ヒグマの根絶を目指した「春グマ駆除」政策が行われていた。北海道の開拓が進む中でも最大の阻害要因となり、世界で最も凶暴と恐れられてきたヒグマ。そんな中、詳しい生態もわからずに殺すのはおかしい、と反発を覚えた学生たちが調査を始めたのがクマ研設立のきっかけである。クマ研の活動がスタートして3年がたったころに梶さんは入部。ヒグマの生態研究・調査にのめり込んだ。
◆クマ研1年のとき、スカンジナビアのヒグマ管理の歴史に強く興味をもった梶さん。スカンジナビアでは17~19世紀に、森林伐採と高い報奨金をかけた駆除によって絶滅寸前となるまで激減し、19世紀末から20世紀半ばまで保護政策がとられていたことを知る。当時の北海道では、まさにヒグマの根絶作戦を展開しているところであり、「これを進めればヒグマは絶滅するのでは」と疑問に思った。卒業論文ではヒグマの分布と捕獲統計の解析を行い、春グマ駆除は幼獣や母獣を多く捕獲するので個体群存続を危うくするとの警告を発した。その後、梶さんの予想通り個体数は減少し、ヒグマによる被害も低減したということで、1990年に春グマ駆除制度は廃止された。
◆大学院に進学するも予算や体制がなくヒグマの研究を断念し、シカの研究に転向する。北海道では明治以降、エゾシカは「乱獲→個体数激減→保護政策」という事態が繰り返されており、梶さんは、エゾシカを資源として利用しつつ個体数を安定的に管理する必要があると考えるようになる。そして、エゾシカの個体群管理を目的に、個体数の増減の仕組みとその要因を探る個体群動態研究に取り組むことにした。
◆調査のフィールドは、生息環境の異なる洞爺湖中島と知床岬に設定した。1980年に開始した中島でのエゾシカ生息数調査では、約100頭から始まり1983年秋には299頭とピークに達し、1983~84年冬に群れの崩壊(大量死)が生じた。野生のシカは「増えすぎると崩壊する」という説と「自己調節能がある」という説がぶつかり合う中での、初めての爆発的な増加と崩壊であった。大量死の原因は餌不足による餓死で、生息数の増加にともない、植生が劇的に変化したことが関係していた。ここには「シカ騒動」と呼ばれる「間引くべきか放置すべきか」の議論も巻き起こっていた。地元の営林署や環境庁などからは、森林被害を防ぐために、調査を中止して一刻も早く間引きを実施すべきであるとの意見が出されたが、梶さん含め研究者らはもちろん研究の継続を主張した。道主催の会議では意見対立のまま終了したが、最終的に道は間引きを決定した。自然死67頭、人為的に95頭が島外へ搬出。「非常に残念な結果」と語る梶さんだが、科学に基づく野生動物管理政策の必要性を実感したことと、今日のシカの増え過ぎ問題を40年前に先取りしたことから、科学と政策を考える契機であったと振り返る。さらに北海道は、自然保護課「野生動物分布等実態調査」事業に破格の予算措置をとるなど、鳥獣行政には専門的な知見が必要だという認識が広がったそうだ。
◆中島の調査では、シカの大量捕獲方法の確立に苦労した。1981年に全数捕獲を目指した捕獲作戦を実行したが、12日間、延べ345人で3頭捕獲にとどまった。大量捕獲の目途がたたず断念を決断するも、無報酬・重労働ながらも献身的に協力してくれるクマ研メンバーに申し訳が立たないと、思いとどまる。「できるかできないかじゃなく、やらなきゃいけないときはやらなきゃいけない。やる価値があるかどうかが重要」と梶さんは言う。作戦を全数捕獲から一部の越冬集団の捕獲に変更する。1982年、追い込み罠による捕獲作戦では15日間、延べ321人で54頭の捕獲に至った。その後も、移動式シカ用囲いワナの一種であるアルパインキャプチャーシステム、大型囲いワナなどさまざまな捕獲方法で、1980~2002年に563頭の捕獲に成功し、標識装着、体重計測、妊娠診断を行った。さらに餌植物の調査では、落葉広葉樹林における植物現存量の99.9%はシカの不嗜好植物であり、餌を食い尽くしたシカは、落ち葉が周年を通じた重要な餌となっていることが明らかになった。夏に高栄養の落ち葉を採食して、脂肪を蓄積して越冬する。落ち葉は無限にあるので、シカが増えても餌は減らないという仕組みだ。つまり、エゾシカの生態的特徴として、嗜好種の餌がなくなっても高密度が維持されるということだ。捕食者や狩猟者による高い捕獲圧がなければ、シカは高密度に達して、自然生態系に強い影響を与えるということがわかった。
◆知床岬でもシカの爆発的増加と崩壊の一連の現象が観察された。知床のシカは、1970年代に明治期の大雪による絶滅を免れた阿寒地域の残存個体群が再分布して定着したと言われており、その個体群は年率21%(3年で倍増)で増加を続けてピークに達すると大量死亡が発生した。600頭近くまで増加して大量に死ぬ、その後再び個体数が回復することを繰り返し、知床岬の植生に強い影響を与え続けていることが判明する。これ以上放置した場合には植物が絶滅するリスクがあると考えられたため、発生しうる最大の被害を未然に防ぐ「予防原則」に基づいて密度操作実験を開始することとなった。それにより、当初目標としていた知床岬の越冬個体数(メス成獣)の半減を達成。シカ生息数の減少に伴い、2016年度までに知床岬を含む遺産地区の一部の植生で回復傾向、知床岬の草量の増加など、部分的な効果が確認された。
◆洞爺湖中島と知床半島での調査を検証すると、次のような知見が得られた。第一に、自然の推移に委ねてはシカによる森林植生への影響を緩和できず、個体数増加の初期段階からの個体数管理が必要であるということ。第二に、長期的な採食を受けた森林植生は、シカの数を減らしても回復しないため、長期間の低密度化の実現が必要であること。梶さんらは、これまで日本になかったエゾシカのさまざまなモニタリング手法を開発するとともに捕獲個体の繁殖力調査や年齢査定を行った。その結果、個体群変動のメカニズムに「自然調節機能がほとんど効いていない」という事実が明確化した。人為的に導入したか自然定着か、閉鎖的か反閉鎖的かといった生息環境に関わらず、人間による捕獲がなければシカは増加し続けるということだ。つまり、「個体数管理は必須」なのである。梶さんらは、管理目標を仮説、捕獲を実験と見立て繰り返し、不確実な情報をもとにした順応的管理と呼ばれる方法で「為すことによって学ぼう」と試みたことで、個体数指数に応じて雌雄の捕獲数を調節するフィードバック管理によって道東のシカを二度減らすことができた。しかしながら、全道的にシカの分布拡大と個体数急増によって、今や人間の手に負えない管理不能な状態に陥っているという。
◆私たちはこれから野生動物とどのように付き合っていけばよいのか。2000年代以降、ニホンジカやイノシシ、クマなどの大型獣の分布域は急速に拡大している。同時に捕獲数も駆除により急増。北海道においては、ヒグマの生息数・捕獲数は右肩上がりで、人身被害や農業被害は深刻になっている。2019年には、札幌市郊外にもヒグマが50年ぶりに出没した。2019年~2023年6月末までに合計66頭の牛を襲ったオスのヒグマ「OSO18」は、記憶に新しい。北大クマ研の40年にわたる調査によると、ヒグマの痕跡の発見率は、春グマ駆除制度期間中は減少していたが、駆除制度廃止後は上昇していることが分かった。北海道は、2022年度から2026年度のヒグマ管理計画において、生息数35%減を目指すよう改定している。
◆良好なヒグマの生息環境が維持されてきた知床半島では、地域住民の生活や産業を守りながら、ヒグマの本来の生活と個体群を将来にわたって維持することを目指している。知床のヒグマは、海と陸の物質循環の橋渡しをしてくれる非常に重要な役割を担っており、適切に管理していく必要があるからだ。国立公園や国指定鳥獣保護区の指定、春グマ駆除制度の廃止等、1980年代以降に保護政策が強化されてきた知床半島だが、ヒグマの個体数を把握できないまま飽和状態で維持されてきた。そのためか、餌不足に見舞われた2012年、2015年、2023年度の3回にわたり、市街地や農地への大量出没があった。クマの大量出没は、人命に関わる危険を伴い、ヒグマの大量捕殺を招くので、大量出没を発生させない個体数水準を維持することが必要だと考えられるようになった。今年三月には、従来の問題個体(人の活動に実害をもたらす、人につきまとう、または人を攻撃するクマ)管理に加えて個体数管理を併用することが合意された。ヒグマと人間がどう折り合っていくかを軸に、個体数のモニタリングおよびフィードバックを行い、問題個体と総個体数を管理する仕組みを構築していくことが課題なのだそうだ。
◆一方、シカの個体数は有史以来最大規模かそれに近いという。シカが増えすぎることによって起こる問題は、生態系被害、農業被害、林業被害と森林被害、列車事故・自動車事故、都市出没問題、野生動物感染症などかなり多様であり、その被害は全国的な社会問題となっている。ここまで深刻になった要因に、野生動物の増加、里山の放置、林業政策の失敗、農村の過疎と高齢化等が関係しているといわれており、梶さんは「動物の力が一番強くて、人間の力が一番弱い時代に、我々は直面している」と話す。法的な仕組みは明治時代から変わらず、為す術がないのだという。
◆なぜ、管理不能になってしまったのか。ヨーロッパでは土地管理者が狩猟権を持つ猟区制度、北米では管理ユニット(管理単位)を設定して捕獲数を割り当て、狩猟によって個体数管理が実施されている。しかし、日本には管理ユニットのような捕獲数の割り当て制度はなく、管理地域が市町村や都道府県など事業によって異なるために「誰が管理するのか」があいまいである。管理責任の所在が不明確である事例として、土地管理の一環として野生動物管理が行われていないということがある。公有地でシカの生息の場となるのは、国立公園、国有林、自衛隊駐屯地など一般市民が入れない地域であるので、国家行政組織がシカ管理の主体となるのは当然のことである。ところが、日本の法制度上、土地所有権と野生動物の所有が関係づけられていないために、国有地の野生動物管理は都道府県や市町村に丸投げ状態なのだ。公有地での捕獲は限定的であり、これらの地域は野生動物の避難場所と化している。捕獲の空白地帯をつくらないために、「野生動物管理は基本的な土地管理義務」とする考え方が必要だという。
◆では、野生動物管理をどのように進めたらよいのか。梶さんは「補完性原則——自助・共助・公助による獣害対策」という、市民に近い地域レベルから始める地域主権型の方法を示し、それは次のように進められる。(1) 集落・地域による被害防除(自助・共助)(2) 市町村による駆除(公助)(3) 都道府県による個体数管理(公助)——この手順で行うためには、市町村と都道府県の緊密な連携が必要になる。必要に応じて上の組織が下の組織を補完し、専門職員として市町村に鳥獣対策員、都道府県に野生動物管理専門員を配置し、国と協働できる仕組みの構築が求められる。
◆現在、日本の鳥獣管理の専門職は圧倒的に不足している。梶さんが北海道を離れたのは、次世代の野生動物管理専門人材を育成する手伝いがしたいと覚悟を決めたからである。野生動物管理教育の研究拠点を広げ、人材育成の輪を広げる準備が進んでいるのだそうだ。梶さんは、その一環として「知床ネイチャーキャンパス」という現場で学ぶ独自の教育を実施している。高校生から社会人まで、海・川・陸といった現場で学び、野生動物管理の専門家(ワイルドライフマネジャー)の養成を目指して活動を行っている。
◆日本では、近年、シカとイノシシがそれぞれ約60万頭、合計120万頭が捕獲されており、ドイツ(211万頭)、フランス(142万頭)に次いで捕獲数が多い。ところが日本の現状は、捕獲は狩猟の役割が低く、駆除がほとんどである。将来は、狩猟による資源利用と駆除による被害管理の組み合わせによる相乗効果が求められる。梶さんは、資源利用として私たちにできることは、「獲って食べる」ことだという。日本列島北部周辺の先住民族であるアイヌ民族はヒグマを山の神(キムンカムイ)として敬い、資源として利用してきたそうだ。野生動物と人間が共存する手段の一つとして、適切に管理・利用させてもらうという姿勢は大切にしなければいけないだろう。狩猟に対して、そして野生動物に対する私たちの価値観の転換がいよいよ求められている。
◆報告会には、シカの研究に興味があるという片倉景道さん(中2)が参加していた。梶さんの論文を読み、梶さんについて知るうちに今回の地平線報告会に辿り着いたそうだ。シカに興味を持ったきっかけを語ってくれたのだが、専門用語を用いてスラスラと話す姿には驚いた。梶さんが代表を務める知床自然アカデミーの「知床ネイチャーキャンパス」には、高校生も参加しているというのだから、人材育成の輪を広げる梶さんの取り組みは、確実に若者の心をつかみ始めているのではないだろうか。[杉田友華 4月から北大修士]
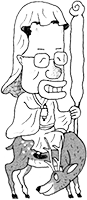
イラスト 長野亮之介
■2006年7月の報告会で「狩って食うシステム」という内容の話をした。北海道では、エゾシカの個体数の増減に応じて、雌雄の捕獲数を調整するフィードバック管理によって、北海道東部のシカの個体数を減らすことができたこと、林産物として管理する必要があること、野生動物管理の担い手の育成が急務であることを述べた。
◆その状況は今でも変わっていない。だが、この20年間でヒグマもエゾシカも分布拡大と個体数増加が生じ、ヒグマは保護から管理へと政策転換があり、エゾシカは管理不能となるまで増加した。前回「いずれにせよ、今日本人が直面している大型野生獣との関係性は、過去100年で初めて出会う事態です」と述べた。だが、今回の報告会では「有史以来、これほど人間の力が弱く、野生動物の力が強くなった時代はなかった」とさらに危機感を強調した。
◆捕獲の担い手育成、野生動物管理の専門家の育成、資源利用の仕組みの3つの柱をたてることが必要であると言い続けてきたが、その歩みは遅い。だが、国がジビエ認証制度を設立し、「野生動物管理教育モデル・コア・カリキュラム」の支援を行うようになったことなどの進歩があったことは嬉しい。
◆今回の報告会にあたって、江本さん、長野さんとの事前の打ち合わせなど、きめ細やかな対応をしていただいた。2時間半の長丁場をどう話すのか、悩ましかったのでとても助かった。また、報告会の感想を記述するというフォローアップ活動も素晴らしい。北大大学院に進学した杉田友華さんの手による報告会レポートは、細部まで正確に記述した力作である。長時間、膨大な内容をどこまで理解していただけたのか、正直不安だったが完璧な理解力である。
◆会場には最年少の片倉景道君(中2)から最高齢の90歳の川口章子さんまで参加されていてお話することができた。片倉君は、なんと拙著『日本のシカ——増えすぎた個体群の科学と管理』(東京大学出版会)という専門書を読み、もっとシカのことを勉強したくて参加したそうだ。川口さんは長く日本山岳会の自然保護委員会に所属されており、シカによって山が荒れているのを心配して、何とかしたい思いで参加したという。孫の世代に美しい山を残したいとの思いを二次会で語ってくださった。その話を伺い、山を楽しむ人たちにも野生動物問題をもっと知ってもらう必要があることを思った。
◆今回、報告の機会を与えていただきありがとうございました。また、拙著『ワイルドライフマネジメント』(東京大学出版会)の会場での販売の労をとっていただき御礼申し上げます。売上金は、「知床自然アカデミー」に寄付しました。地平線会議が世代を超えて地球で活躍する方々のプラットフォームとして継続し発展することを願っています。[梶光一]
■先日地平線報告会に参加させていただいた武蔵中学3年の片倉景道と申します。梶先生のお話を聞けて、とてもためになりました。以下に感想文を記させていただきます。
◆私は、中1の課外授業で赤城山に行ったとき、シカの頭骨、大腿骨などを見つけ、数人の仲間と土に埋まっていた骨たちを探したところから、シカへの情熱は始まりました。その中で梶先生のことを調べていたら、この報告会を見つけました。最初は、地平線会議???どんなところだろう。想像がつきませんでした。いざ行ってみると、優しい方々が多くてとても参加しやすかったです。ありがとうございました。
◆そして、梶先生の講演が始まると、前半から胸がドクンドクン。前に読んだ「日本のシカ」でわからないことが紐解かれてゆき、しかも、捕獲方法や個体数の調査方法が確立されていない中での試行錯誤が大変興味深かったです。
◆前半で語られた「狩猟圧」の意義、そこで私の心の中に1つの疑問が浮かびました。「どのようにして狩猟圧をかけていけばよいのか」。その中で始まった後半、私の疑問が丁寧に解説されてゆきました。そこで出てきた3つの単語「捕獲」「管理」「利用」。これはただの単語の羅列ではなく、つながっている大切な言葉でした。
◆今回の報告会は私に新たな視点を与えてくれました。素晴らしい講演をしてくださった梶光一先生、私を温かく受け入れてくれた方々に改めて感謝申し上げます。[武蔵中学3年 片倉景道]
|
|
|