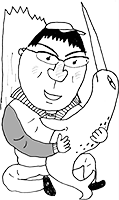
■「北海道大学大学院の矢澤宏太郎さんは、地球温暖化の影響を敏感に受けるグリーンランド北西部のカナック氷河(北緯77度)での研究活動を報告した。星野道夫の著作をきっかけに北極圏に惹かれ、気候変動が地球環境に与える影響を解明するため、氷河・氷床学の道へ進んだ。現地調査では、ドローンによる3D地形図作成やアイスレーダーを用いた氷厚測定といった最新技術を駆使。これにより、氷河が1年間で最大20mも流動するダイナミックな実態や、氷の融解量を面的に評価している。また、海に面したボードイン氷河では、氷の塊が海に崩落する『カービング』現象の観測にも成功した。これらのデータは、氷河の変動がもたらす海面上昇の予測精度向上に貢献する貴重なものである。研究は、伝統的な狩猟文化が息づくカナック村を拠点に行われる。現地の人々と交流し、その生活や文化に触れることも、研究活動の重要な一部となっている。矢澤さんは今後、博士課程へ進学し、科学的探求をさらに深めていく意欲を示した」。
◆東京駅から新大阪まで「のぞみ」で2時間半というのは、ちょうど地平線報告会の最初から締めの質疑応答までの時間そのままだ。きのうの報告会の録画を見返しながら、西へ向かう(あすは朝から大阪・関西万博会場で仕事があるのだ)。
◆冒頭の500字は矢澤さんの2時間半の報告を、Gemini 2.5 Flashに要約させたものだ。いかに味気ないことか。地平線での報告の真髄は、この500字には現れない、報告者の言葉の繰り返しや声に出さない逡巡、参加者の目の輝きや姿勢、質疑を通した戸惑いと発見にある。語られた言葉をすべて文字にしたとしても、この通信ではとても伝わらないが、せめてその努力はしてみようと思う。
◆地平線会議は来年2026年のこの季節に、北海道・西興部村で「地平線会議 in 北海道」を開催する。村の人たちだけでなく、道内各地の地平線の人たちに手伝ってもらい、かつその人たちの話を聞く場になるだろう。特に法政大学から北大大学院に進学した杉田友華さんのような若い人たちの志を受け止めたい。その杉田さんが薦めたのが、今月の報告者、矢澤宏太郎さんだ。
◆アッパという鳥がいる。植村直己さんも通ったシオラパルクで有名なアッパリアスに似ているが、手のひらサイズのアッパリアスと違い、両腕いっぱいに抱えるくらいの大きさがある。調査を終えて、カナックの村の中学生たちと歩いていた矢澤さんは、嘴が割れて食餌できなくなったアッパを見つけた。このアッパはもう長く生きられないから、殺して食べ物にしようと中学生たちは言う。日本人お前やってみろよ、胸骨圧迫して心臓を押し潰すか、首をねじって息の根を止めるかのどっちかだと言われ、矢澤さんはアッパを手にかけたが、うまくいかない。結局村の子たちがアッパの息の根を止めた。
◆「これが明日の自分たちに繋がるから、こういう生き物を殺すっていう行為は自分たちにとっては嬉しいことなんだっていうふうに教わって、相手は中学生なんですけれども彼らは強く生きてるなと。それと同時に劣等感を感じまして。そっか、自分はこの生き物1匹殺せないんだなっていう。ただの残酷な行為ではなくて、傷ついてこれ以上成長できない個体の命をいただくために殺すという行為もできないんだなっていうのにショックを覚えて」。これがきっかけで、矢澤さんはこの夏、狩猟免許を取り、命のやり取りというものが理解できないかと模索し始めたという。この24歳の眩しいまでのナイーブさもさることながら、こうした思考と行動とを直結できる北海道という環境にも、やはりどうしても魅かれてしまう。
◆矢澤宏太郎さんは札幌育ち。北大水産学部で音響資源量推定を研究。一方でワンゲル部に所属して北海道の山々を舞台に冬季の縦走やクライミングを趣味にしていた。積雪期単独北海道分水嶺縦断で知られる野村良太さんの後輩に当たる。大学3年生のときにベトナムへ1人旅した。最初に訪れたホーチミンで暑さとバイクの騒音に嫌気がさし、たどり着いたのは高原都市のサパ。そこで黒モン族の自然と密接に結びついた生活スタイルに感銘を受けたことが、大学院での選択につながった。一緒にハイキングしたり、料理したり、チャーミングな宿泊先の女主人との2ショット写真が印象的。
◆矢澤さんは海洋や音響物理から一転して、大学院では「地球圏科学専攻雪氷寒冷圏コース氷河・氷床グループ」に進むことに。そして入学式の日、「グリーンランドでドローンを飛ばさないか」と杉山慎教授に声をかけられて、極地研を中心とする「ArCSIII」北極域研究強化プロジェクトに加わった。ArCSIIIは、氷河だけでなく、海洋、文化、社会問題なども研究対象に含んだ大きなプロジェクトだ。
◆グリーンランドには2024年、25年の夏に1か月ずつ滞在した。研究の舞台は、飛行機で行ける最北の村、人口約600人のカナックだ。日本からデンマークのコペンハーゲンを経由し、グリーンランドのヌーク、イルリサットと乗り継いで向かうが、天候が不安定なため欠航が日常茶飯事。矢澤さんは「人生がうまくいってると思ってるやつはエア・グリーンランドに乗れ」という指導教員、ポドリスキー准教授の名言?を紹介した。2025年にはカナック上空まで飛んだが着陸できないこと2回。10日足止めされた後、3度目の正直でやっと村に入ることができた。着陸時には拍手が起きたという。
◆7月から8月の間の1か月は白夜の時期で、太陽は丘に隠れて村が日陰にはなるものの、沈まない。13人が共同生活するゲストハウスのオーナーはトク・オオシマさんとキム・ピーターセンさん。トクさんは、ご存知大島育雄さんの長女で、通訳から調査に使う漁船の手配まで、このプロジェクトになくてはならない存在になっている。
◆カナックではハンターがカヤックを使い、長い一本角を持つイッカクを、銛突き(ハプーン)を投げて仕留めるという伝統的な猟法が続けられている。中学を出た子供たちは村を出ていくことが多いが、ハンターに憧れて戻ってくるケースもあるそうだ。有名なアッパリアスに加え、北極イワナ、ハリバット(カラスガレイ)、アザラシと村の食生活は狩猟採集を基本としながら意外にも豊かなようだ。特にアザラシの脂は美味しく、オメガ脂肪酸が多く含まれて美容にもいいのだが、食べ過ぎると消化不良を起こす。矢澤さんもアザラシのカレーを食べすぎて、翌日から胃もたれで大変な思いをしたそう。
◆村には「ピラースイサック」というスーパーマーケットが1軒あり、食品、飲料から鉄砲まで売られている。グリーンランド語にも方言があり、矢澤さんの観察ではカナックではSの発音をHっぽく発音するのが特徴で、これを現地の人は「ピラーハイヒュック」と読む。しかしなぜか彼らはこのスーパーのことを「ビヒンヤビック」と呼ぶ。「ビヒンヤビックとは『ものを買う場所』。村の中にお金を払って物を手に入れる場所が1個しかないので、『買う場所』というと、ここを指すというのが面白い」。
◆そんなカナックをベースに、カナック氷帽、カナック氷河を杉山教授が観測地点として選んだのは、グリーンランド北西部には長期モニタリングされている氷河の研究サイトがなかったこと、そして大島育雄さんや植村直己さんら、さまざまな日本の冒険家たちの拠点となり、日本との繋がりが深いということからだという。
◆そもそも氷河とは、降り積もった雪が自らの重みで圧縮されて氷の塊となり、ゆっくりと動いている巨大な川のようなもの。チームは様々な方法でその変化を観測している。例えば、氷河に最長6メートルのポール(ステーク)を打ち込み、翌年その位置がどれだけ移動したか、ポールがどれだけ氷の表面から突き出たかを計測する「ステーク観測」。硬い氷河にドリルで6メートルの穴を穿つのは難しいし気をつかうし疲れるし、本当に大変そうだ。
◆矢澤さんの修士論文のテーマになっているのはドローンを飛ばして高精細な3D地形図を作成する「ドローン観測」。これにより、ステーク観測のような「点」の情報だけでなく、「面」として広範囲の氷河の変化を捉えることができる。この調査から、カナック氷河の末端部では、年間平均1.7メートルもの厚さの氷が失われていることが明らかになった。
◆こうした高さの比較から氷の厚さは間接的にわかるが、いま立っている表面から基盤岩までの氷自体の厚さを測るのがアイスレーダー(GPR)だ。レーダー装置を背負って2人1組で氷河の上を歩き、電磁波を氷の底にある岩盤に向けて発射する。カナック氷河では最大で厚さ150メートル。杉山教授と矢澤さんたちは氷上を40km以上歩くルートを設定して実行。しかし、実際の氷上は起伏もクレバスもあるし、水路も横切っている。GPSを持ってルート工作する杉山教授を先頭に進み、最後は融解水が濁流となった川をずぶ濡れで渡ることになった。
◆「みんなパンツまで濡れて。でもこのときはもう疲れすぎてたんで、なんかアイシングのような気分で気持ちいいな気持ちいいなとか、言ってたんですけど。約束の時間よりもオーバーしてしまって、迎えの船が干潮でも近づける場所を選ばないといけないっていうので、ずっと並走して追いかけて追いかけて、やっと船に回収してもらったんですよね。気持ち良かったはずの体はこの後の船上でどんどん冷えて、結局凍えながらカナックの村にたどり着いて、無事に氷の厚さを測定する旅が終わったっていう出来事ですね」。これはもう冒険そのものではないか。
◆こうした研究成果をカナック村の人たちと共有し、意見をもらうため、プロジェクトでは年1回ワークショップを行い、合わせて寿司やお好み焼きなど日本食も振る舞っている。矢澤さんはベトナムでの楽しかった交流を思い出したのか、カナック村の人たちの文化を知るため専門外の「研究」を個人的に試行した。日本から持参した27枚撮りのカメラ付きフィルムを数人に渡し、身の回りを自由に撮ってもらって、被写体を分析する。スーパーで働くカメラ好きのイエンスが撮ってくれた17枚はほとんどが景色と人。スーパーの裏のノスタルジーな雰囲気が伝わってくる。
◆犬ぞりでハリバットを獲りに行くハンターのマヒュッチャクは、コミュニティセンターに遊びに来る中学生や愛犬の写真を撮ってくれた。「犬がカメラのレンズなめちゃったけど大丈夫?」と心配していたらしい。学校を卒業したばかりのヤコビナが撮ったのも、やはり犬。ちょうど仔犬が生まれたばかりだったそうだ。現地のハンターに一目惚れして夏場はカナックで暮らす日本人のサキコさんにもカメラを渡した。彼女は風景だけでなく、身の回りの物を多く撮ってくれたという。
◆日本から来た学生や矢澤さん自身が撮ったものも現像した結果、ある共通点に気づいた。カナックの沖合にあるケケッタハ島がほぼ全員の写真に入っているのだ。イエンスが友人を写したショットの背景にケケッタハ、サキコさんが撮った風景にも少し見切れたケケッタハ、マヒュッチャクの写真にも、ヤコビナの写真にも。矢澤さんも数えれば50枚以上ケケッタハの風景を撮っていた。「それくらいこの景色は魅力的で、自分も好きなので、同じような思い、そこで生まれて育った人たちも持ってるんじゃないかなって思いを馳せました」。この個人的プロジェクトが次回以降どこに向かっていくのか、大変楽しみだ。
◆「自分が70歳になったときに植村直己さんがグリーンランドに初めて行ってから100周年になるんですけれども、それまでの間に自分がグリーンランドで何者かになりたいと思っていて、そのプロセスはまだサイエンスなのか、文化なのか写真なのか、冒険なのかわからないですけれども、日本との不思議な繋がりっていうものが現地に行くとすごく伝わってきて、そのためにもなるべく長く頑張りたいなと思ってます」。
◆報告会の2週間後というから、この通信が発行されるころには矢澤さんはネパールのトランバウ氷河・トラカルディン氷河の調査に参加するという。ネパールと言えば、貞兼綾子さんと共にランタン谷に長期滞在した樋口和生さんを思い出す。樋口さんも北大山岳部出身で、第57次で隊長としての南極で越冬した直後の2017年5月、地平線会議で報告。その後昨年まで第64次で2度目の越冬隊長を務めたことをご記憶の方も多いと思う。その前、63次の澤柿教伸さんも南極から戻ってすぐに報告してくれた。澤柿さんと言えば、矢澤さんを紹介してくれた杉田友華さんは澤柿ゼミ案……、あれ、ランタン、南極、グリーンランド、みんなつながってる?
◆Geminiには決して解釈されない彼らの魅力を感じるために、私は報告会に足を運ぶ。そしていよいよ来年のこの季節。北の大地でもっとたくさんの旅人たちの報告を聞きたいと期待が高まる。[落合大祐]
■今回、初めて地平線報告会に参加させていただきました。角幡唯介さんや山崎哲秀さんが報告されていたことからこの会の存在は知っていましたが、まさか自分が登壇することになるとは思ってもいませんでした。北大にやってきた杉田友華さんの推薦をきっかけに、江本さんとのやり取りがとんとん拍子に進み、あっという間に報告会当日を迎えていました。報告会では、これまでに二度参加したグリーンランド北西部カナック氷河での現地観測と北緯77度にあるカナック村の滞在について、お話をさせていただきました。2時間にわたって話すのは初めての経験でしたし、特に氷河の話は馴染みのない方が多かったと思いますので、うまく伝えられるか不安でした。それでも、温かく迎え入れてくれた地平線会議の皆さんには心から感謝しています。
◆私の先生がグリーンランドで研究を始めてから10年以上たち、村の人にとっては、夏になると日本人がやってくるというのが当たり前になっています。研究が、人と人との「つながり」を生み出してきたことには、感慨深いものがあります。また、カナック村は地球最北の村で極地冒険の拠点でもあるシオラパルクの隣町です。そのため、現地に滞在していると「オオシマ」という姓を持つ人や日本語の単語を話してくれる人と出会うことができ、6000キロメートル離れた日本とカナック村の不思議な「つながり」を感じさせます。私自身、初めての地平線報告会で、参加者の皆さんとは初めましてだったのですが、北大の先生や山岳ガイドの方々、グリーンランドの現地住民などを共通の知り合いに持つ参加者がいて、地平線会議のコミュニティの広さや歴史、皆さんの興味の幅に驚くのと同時に、ここでも不思議な「つながり」を感じました。
◆「地平線」とは、地面と空の境界をなす線を意味します。地球のどこでも地面と空の境界があり、活動の分野は違っても地平線という同じ景色を共有しているはずです。そこで、世界各地の地球体験を「地平線」と表現して語り合っているのだと感じました。私はこれからも地球のどこかでもがき続けます。またいつか、この場で報告ができればいいなと思います。[矢澤宏太郎]
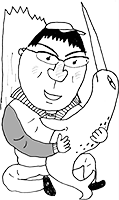
イラスト 長野亮之介
|
|
|