

1月14日。朝刊は「衆院投開票来月8日軸」(読売)と一面で伝える。つい先日までは選挙の雰囲気はまるでなかった。しかし、10日に読売が「首相、衆院解散検討」と報じてから俄然動いた。昨年10月、日本初の女性総理となった高市早苗人気は予想以上に高く、自由民主党は「いまなら勝てる」とみたのだろう。1年あまり前にやった衆院選をまたやろうとしている。
◆きのう13日午後2時、高市首相は、奈良市で訪日中の李在明(イ・ジェミョン)韓国大統領と日韓首脳会談を行った。2人はすでにソウルで初めての首脳会談をしており今回はシャトル外交の一環として2度目の会談だった。驚いたことに日本と韓国のトップは会談後、ドラム演奏を共演したという。一方で同じ日、2024年12月の「非常戒厳」宣布で内乱首謀罪に問われた前大統領、親日派としても知られた尹錫悦(ユン・ソンニョル)氏に対して特別検察は情状酌量の余地はない、として死刑を求刑した。なんという違い。
◆アメリカのトランプ大統領はベネズエラのマドゥロ大統領を麻薬密輸容疑で逮捕、一国のリーダーをアメリカまで連行し、裁判にかけている。ノーベル平和賞を受賞した活動家、マチャド氏はこうした事態を評価してトランプを絶賛しているが自身が求めてきた政権掌握の事態にはまだなりそうもない。
◆元日に車で上田に向かった。中央道は拍子抜けするほど空いていた。こんなにガラガラなら毎年ねらうべきかな。上田といえば白蛇さまだ。国道18号線から見上げると太郎山の麓に真っ白な屋根の印象的な神社がある。正しくは『松尾宇蛇神社』。木曽の御嶽山の山岳信仰の流れを汲む神社だ。家から近いのでよく行くが、急傾斜の道には往生する。高度差80数メートルの急坂を息を弾ませて登り、2026年の幸運を祈る。
◆上田には9日間もいた。この通信の作業もあるのでパソコン持参で。途中、松本に行き、女鳥羽川の岸を散策しつつ目の前の北アの山々を見上げるのはなんとも言えない贅沢だった。連れは、この街に3年間下宿して松本深志高で学んだので地理に詳しい。岸辺の喫茶「まるも」でゆっくりコーヒーをすすりながらにわか文化人の気分に。私もかって穂高から下山の都度松本にお世話になったし、上田よりなんとなく文化度が高い気がするのである。
◆相棒が運転好きで信州生まれということは幸運だった。暮れには木曽の中学仲間のTさんから熊肉、鹿肉が届き、たまたま連れが神事の見学で訪れた飯田市で仕入れた猪肉と合わせた豪華なジビエ3種の料理を作ってくれた。熊鍋、猪肉のパイ、鹿肉のシチュー。どれもなかなかの味で居合わせた客にも好評だったのである。
◆2026年、いよいよ北海道西興部村に集結する年だ。私はこの機会に西興部という人口1000人の村で北海道の若者たち、北海道に興味津々の仲間たち、そして西興部村の皆さんとの良き出会いの場を作りたい。1979年から活動してきた地平線会議にとってはじめての北海道。あの大地で起きることを考えるとワクワクするが、そのためにもまずは日程だ。
◆きのう13日、菊池博村長と話した。村にも1年を通していろいろなスケジュールがある。昨年から話に出ている8月末から9月前半にかけての2日間。そろそろ日程を固めて準備に入りたい。話を聞いた村長は幹部たちとあらためて打ち合わせしてくれたのだろう、午後になって「了解しました。9月5、6日でいきましょう」と返事をくださった。ああ、よかった。これで一気に進める。
◆ただし、これからが難題だ。宿泊、食事、交通など決めなければならないことが次々に出てくる。皆さん、2026年9月5日(土)・6日(日)を予定に入れた上で、いろいろ協力くださいね。行こうぜ! 西興部村![江本嘉伸]
■2025年の最後の報告者は、ドキュメンタリー写真家の小松由佳さん。2024年12月、夫のラドワンさんと長男と共にアサド政権崩壊直後のシリアに入り、独裁政権から解放されたばかりの同国の様子を伝えてくれた、1月に続いての報告になる。この間、由佳さんは第23回開高健ノンフィクション賞を受賞、11月下旬に『シリアの家族』を上梓した。
◆当初、『シリアの家族』は終わりの見えない動乱の下、異郷で生活を再建しながら故郷への帰還を夢見るシリア難民の物語になるはずだった。だが、2024年12月8日、半世紀余りに及んだアサド政権の終焉によって、書き始めたときにはまったく想定しなかった展開に。自身が「13年にわたるシリア難民取材の集大成です」と話すように、今回の報告は、前半はシリア難民を見つめた13年間について、そして後半は『シリアの家族』という作品が完成するまでの裏話がゲストを交えて語られる、盛だくさんな報告会になった。
◆まずは内戦前の話から。由佳さんが初めてシリアを訪れたのは2008年。土地に生きる人々の暮らしを知りたいと取材を進めるなかで出会ったのが、古くから交易地として栄えたオアシス都市パルミラで4世代70人が同居するアブドゥルラティーフ一家だった。3世代前までベドウィン(遊牧民)だった一家にとって、砂漠は“雌ラクダの乳と乾燥ナツメヤシがあれば、2か月でも旅できる、すべてがある”土地。砂漠に生きる力や知恵を持つ彼らはラクダの放牧のほか、果樹園の管理、レンガ造り、屠畜など、季節ごとに仕事を変え、スンナ派の教えのもと、強い絆で結ばれ、穏やかに生きていたという。大の男が豆のディップを顔につけ合い、ふざける写真を見せながら「シリアンノクタ(シリア製冗談)といわれるように、シリアでは冗談が社会の潤滑油になっています。ユーモアのセンスがない男性はもてません」と、由佳さん。
◆だが、アラブの春が飛び火し、シリアでも民主化運動が始まると、政府は武力弾圧を始め、政治的発言をする者の取り締まりを強化していった。2011年、政府軍に徴兵されたラドワンさんが、市民を弾圧したくないと思い悩んでいたころ、民主化運動に参加した兄のサーメルが反逆罪で逮捕されてしまう。「このままシリアにいて市民の虐殺に加担するよりも、生きていればいつか会えるから」。母親にそういわれたラドワンさんは政府軍を脱走し、ヨルダンへと逃れた。身近な人が逮捕され、難民になっていく姿を目の当たりにした由佳さんは、このとき難民を取材する決意をしたという。
◆2013年の結婚後、来日したラドワンさんは日本の生活になかなか慣れず、経済的に不安定な生活やシリアに入国できない状況が続くなか、由佳さんは彼らの避難先へと赴き、ご本人曰く「子連れパニック取材」をほぼ毎年、敢行した。そうせざるを得なかった面もあったものの、シリアの血を引く子どもたちに難民を通じて自分のルーツに出会ってほしいという思いからの、子連れ取材だった。
◆「(子連れ取材では)ゆっくり話を聞くことができず、決定的な写真を撮り逃すこともありました。子どもが難民キャンプ内で行方不明になり、難民のお母さんに叱られたこともあります。でも、誰もが子どもをケアしてくれる現地の方が子どもは育てやすかったし、取材相手と家族のように付き合うことができました」。
◆アブドゥルラティーフ一家もまた、2016年にトルコ南部オスマニエ県に逃れ、5つの家族がそばに暮らし、放牧で生計を立てていた。だが、威厳に満ちた家長だったガーゼムは、トルコに来て以降、寡黙になっていた。「半世紀以上かけて築いたものを失ったショックは大きく、ガーゼムは屋上でひとり焚火をしながら、かつて砂漠でラクダを放牧した日々を思い出していたようです」。
◆2021年、ガーゼムは難民のままトルコで亡くなった。彼らが難民になる以前に暮らした故郷は今、どうなっているか。点と点をつながなければ、難民取材にならないのではないか。ガーゼムの死を機にその思いを強くした由佳さんは、2022年、親族訪問ビザを得て11年ぶりにシリアに入国した。
◆2022年は2月にロシアがウクライナ侵攻を始めた年でもある。アサド政権はロシアとイランの後ろ盾の下、欧米の経済制裁や国連の非難を無視して化学兵器を使用するなど非人道的行為を繰り返していたが、在シリアロシア軍がウクライナへ流れ出したこの時期は、シリア入りのチャンスだったという。こうした国際情勢に加え、そのころ、微妙な空気が漂っていた夫婦関係を考え、親族訪問ビザを申請するなら結婚している今だという家族情勢も、シリア入りを後押しした。
◆かつて一家が暮らした家はどうなっているか。住民はどんな生活をしているか。危険を承知でパルミラ入りした由佳さんは、秘密警察による監視の下、知らない親族の家で軟禁状態に置かれた。「元々徹底していた情報統制は、内戦後エスカレートしていました。一筋縄ではいかない取材を通じて、アサド政権下の人々がどんな状況に追い込まれているかを実感しました」。秘密警察同行の下、アブドゥルラティーフ家の撮影に許された時間は15分。「鉄製品や台所の設備機器、トイレの便器など、換金できるものはほぼ略奪されていました。かつて女性たちがおしゃべりし、子どもたちが駆け回り、音が溢れていた場所で、残骸品が砂漠の砂にまみれているのを見たときは、絶望的な気持ちになりました」。
◆自由に出歩くことも、撮影することもままならず、写真はすべてチェックされ、空爆の痕跡を伝えるものは消去を命じられる。精神的に負い込まれた取材を終えて戻ったトルコで起きたのが、第2夫人騒動だった。「内戦が続き、経済的に困窮するなか、国内に留まる人々のあいだで、自分の娘を国外にいるシリア人に嫁がせることが流行っていたんです。空港に迎えにきた夫に到着5分後、この話をされたときは、シリアで見た光景が吹き飛び、頭が真っ白になりました」。まさかのタイミングで起きた第2夫人騒動。だが、由佳さんは彼らの文化を貶めたり否定するのではなく、リアルな体験として描くことに努め、書くことで心の痛みを乗り越えたと話す。
◆そして迎えた2024年12月8日。シリア難民を取材する予定で向かったロンドンに到着直後、アサド政権崩壊を知ると、予定を変更してレバノンでラドワンさんと待ち合わせ、陸路でシリアに入国。フリーランスの自分がどのように大手メディアと異なる取材ができるかを考え、解放直後のシリアを、夫=難民の視点で取材した。
◆直前に見つかった囚人名簿でサーメルが亡くなったことはわかっていたが、現地では、人間虐殺の場といわれ、囚人の75%が帰れなかったサイドナヤ刑務所や、アサド政権下で行方不明となった身内の消息を知ろうと、10万人近い人の写真が貼られているマルジェ広場などに足を運んだ。
◆13年ぶりに祖国に立ち、歓喜していたラドワンさんは、祖国の悲惨さを知るにつれ、安全な日本に逃れていた自身に後ろめたさを感じているようだった。「目の前の廃墟を見て、自分が何を失ったか、ようやく理解したと夫はいいました。『家や町は再生できるけれど、兄や父は戻らない。人々が故郷に戻らない限り、かつての日常は戻らない』」。廃墟の先にあるパルミラを見つめる夫を撮影しながら、彼はシリアに戻るだろうと、由佳さんはそう思ったという。
■後半は、受賞後、出版までの4か月間、作品をよりよくするために考えたこと、ギリギリまで磨き上げていくプロセスなどが、編集者の田中伊織さん、そして地平線会議代表世話人の江本嘉伸さんを交えて語られた。
◆賞の選考委員や諸先輩の助言などから、由佳さんは優れたノンフィクションについて次のように考えていると話す。①ノンフィクションはおもしろくなければならない。②その人にしか書けないものでなければならない。③内面の揺れ、動きこそが作品を決定づけるもので、作者の内面が出ていない作品はおもしろくない。と同時に、④作品には主観と客観のバランスも求められる。「『どれだけ自分の内面をさらけ出せるか。そして作品を書くことで作者自身、変化できるか。それが優れたノンフィクションだ』という江本さんのことばや、『どんなに主観的なテーマでも、そこに客観的な視点を反映させなければいけない』という岡村隆さんのメッセージなど、1冊の本を仕上げるまで、フィールドに立つ諸先輩から多くの助言をいただきました」。
◆また、作品の中でどう描くか悩み続けたエピソードとして、①2022年のパルミラ単独取材、②第2夫人騒動、そして③サイドナヤ刑務所を挙げた。「秘密警察による監視、親族による軟禁は、人間の負の面に目が行きがちな出来事です。ただ、どんなに厳しい状況にあっても、私は写真家として人間の中に光を探したいし、人間の尊厳や良心を信じることが紛争地での写真家の役割ではないかと思い、彼らを多面的に描くことを意識しました」。ともすれば私憤で筆を走らせそうな第2夫人騒動については、よりよい未来のための彼らの選択として、その文化をありのままに書くことに努め、人間の狂気を感じたサイドナヤ刑務所でも、負の感情をそのまま描くのは自分のスタイルではないからと、別の面に目を向けようとしたという。
◆写真、文章、そのいずれにおいても、多様な解釈の可能性を残したいという由佳さんは、写真のような文章を書きたいと続けた。「私にとってよい写真とは、見る人がいろいろなとらえ方ができる余白のある、個々の中に問いを生む写真です。今回の本でも、読者がそれぞれにシリアや登場人物につながってもらえればと思います」。
◆アサド政権が崩壊した今、難民は故郷のシリアに戻りつつある。これからの人生はシリアの再生に捧げたい。そう決意し、報告会の約1週間前に帰国したラドワンさんは、大家族の再生、そしてホテル「トモダチ」計画の実践に向けて動き出している。「市街地の8割が空爆を受け、今は宿が1軒もないパルミラに、夫は最初のホテル『トモダチ』をつくろうとしています。私の父から数百万円借金して、空爆を逃れた建物を入手・改装し、来春のオープンを目指しています」。
◆夫婦が一緒にいなくて寂しくないのか。友人知人の問いに、由佳さんは「そういう段階は乗り越えたというか、夫婦関係が大変だったので鍛えられたというか(笑)。個人の幸福よりも、一生帰れないと思っていた故郷に夫が帰還して、大家族を再生しようとしていることに大きな意義を感じています」と、答えたという。「それは写真家としてシリアを見てきたからだと思います。今後も2人の子どもを育て、別居婚の夫を何となく見守りながら、シリアの人々を見つめていきたいです」。
◆最後、田中さん、江本さんとの鼎談では、2017年の開高健ノンフィクション賞の最終候補に残った前作『人間の土地へ』の評価や、『シリアの家族』を上梓するまでの編集者とのやりとりから、原稿にかける由佳さんの姿勢を伝える話となった。
◆田中さんは、石川直樹さん、角幡雄介さん、宮城公博さん、本多有香さん、そして由佳さんと、地平線会議でお馴染みの人たちの作品の書籍化を手がけてきた編集者。前作の開高賞最終選考時、由佳さんは江本さん宅で掃除をしながら、田中さんの電話を待っていたという。「300万円はでかいから、賞を取ってほしかった」。当時の由佳さんの経済状況をよく知る江本さんのそのことばに、「(受賞できなかったのは)残念でしたけど、『シリアの家族』を書き上げた今、(前作は)まだ賞には値しない作品だったと思います」と由佳さん。
◆また、「あのとき受賞しなかったことで、一回りも二回りも大きな作品になったと思います」と話した田中さんは、「小松さんは、校正が出るたびに赤をびっしり入れるんです。そしてそのたびに原稿がよくなる。文章にかける情熱は本当にすごいです」と、担当編集者ならではのエピソードを披露。
◆難民という重めのテーマから読者が引かないように、どんな構成にすればよいか。冒頭の30ページでいかに引き付けられるかが勝負。作品は長ければよいわけではなく、エッセンスを凝縮し、長くても300ページ以内で収めたほうがよい……。1冊の本ができるまでのこうした具体的な話も、書くこと、撮ることに関わる人が多い地平線会議の参加者には、示唆に富む内容だったのではないかと思う。
◆質問タイムでは、多くの人がそれぞれ興味深い問いを投げかけたが、中でも個人的にグッときたのは最後のやりとりだった。過去の通信にUber Eatsで糊口を凌いだと書いたこともあるように、由佳さんは経済的にかなり綱渡りな日々を送ってきた。だが、生活の不安はないのか、もしあるならどう解消するのかという問いに「不安にならないですね」と即答したのだ。「そこがいけないのだと思うけれど、かつてのヒマラヤ登山経験から、命を落とさなければ何度でもやり直せるという思いが根本にあるんです。今、経済的に苦労していても、頑張り続ければいずれ安定するかもしれないと、楽観しています」。
◆渦中では頭が真っ白になるような苛烈な体験も、最終的にそのすべてを表現の糧とし、自身の変化・成長へとつないでゆく。今回、レポートを仰せつかり、大西夏奈子さんや貴家蓉子さんがまとめた過去の報告会レポート、ご本人が通信で連載した「石ころ」(2021年9月~2022年6月)などを読み返して、改めて感じたのはそのことだった。たおやかな外見からは計り知れない強さを内に秘め、どんなときでも現場に立ち続け、自分の信じた道を邁進する。その延長線上で生まれた作品を、ぜひ多くの人に読んでもらいたい。[塚田恭子]
報告会当日、三五康司さんの靴を間違えて履いて帰られた方、お知らせください。セダークレストの27.5cm とのことです
■今回の報告会では、11月に刊行となった開高建ノンフィクション賞受賞作品、『シリアの家族』の制作の裏側を語るということで、取材現場での経験やエピソードを、どのようにノンフィクション作品に落とし込んでいったのかをお話しました。
◆私はこれまで、地平線の皆様ももちろんのこと、登山や取材活動を通し、独自のフィールドを求め、そこに立ち続けてきた多くの挑戦者、冒険者、旅人、行動者の皆様に出会ってきました。そしてこうした方々から、生きた体験からくるかけがえのない学びをいただいてきました。
◆なかでも、本という作品を作り上げるうえで血肉になった哲学や言葉をご紹介させていただきました。地平線会議代表世話人であり、元読売新聞記者である江本嘉伸さんからは、“優れたノンフィクションとはどういうものであるか”を教えていただきました。 江本さんによればそれは、「どれだけ自分の内面をさらけ出すことができるかどうか」 、「さらにその作品を描くことで、作者が変化を経験する作品であるかどうか」だといいます。
◆また2025年7月に亡くなられた岡村隆さんからは、強烈な主観を模索しつつも、客観を常に意識し、多角的な視点から対象を描くことの大切さを教えていただきました。お二人をはじめ、これまで現場の第一線に立ち続けてきた皆様から薫陶を受けたことが、ノンフィクションを書くための大きな力になったことを実感しました。
◆またお話の後半では、江本さんと、担当編集者である田中伊織さん(集英社インターナショナル)にもご登壇いただき、鼎談させていただきました。実は、10年以上前に田中さんと私を繋いでくださったのが江本さんだったというご縁もあり、感慨深い三人の語らいとなりました。
◆本は、書き手一人の想いだけでは世に出すことができません。書き手の想いを汲み取りつつも、より多くの読者に届くよう磨き上げてくださるのが編集者です。執筆の初期段階から伴走してくださった田中さんの存在の大きさについても、改めて噛み締めることができた時間にもなりました。
◆報告会はこれまでの活動を振り返るような大変実りある時間でしたが、実はその裏で事件も。報告会の前に、私とは別行動で八王子の自宅から会場に向かっていた二人の子供(9歳のサーメルと7歳のサラーム)と連絡が取れず、行方不明のまま、報告会が始まってしまいました。
◆電話もメールも繋がらず、おそらく二人は八王子に帰るだろうと予想していましたが、なんと早稲田駅から最寄りの交番を探し、「迷子になりました」と警察に訴えた模様。さらに「僕のお母さんの名前は小松由佳です。お母さんがどこにいるか調べてください」と警察に頼んだとのことでした。結局、息子の携帯に電話番号が入っていた秋田の両親(子供たちにとっては祖父母)のところへ警察が電話し、私が地平線報告会の発表中だと父が突き止め、警察から榎町地域センターに、「関係者の子供が迷子だ。交番に保護している」と連絡が入ったのでした。私は報告の最中だったため、地平線のスタッフがタクシーで交番までお迎えに行っていただいたとのこと。大変ご迷惑をおかけしてしまいました。
◆その後、子供たちと連絡が取れなかったのは、私の携帯電話番号を長男が着信拒否にしていたこと(うるさいお母さんからガミガミ言われないため)、会場までの行き方を送っていたメールを、そもそも見ていなかった(!!)ということがわかり、携帯の使い方についても子供と再度話し合うことになりました……。こうして報告会の最中、子供たちが交番に保護されるというハラハラの一幕もありましたが、無事に一日を終えることができました。皆様、どうもありがとうございました。
◆私がテーマとするシリアは今、アサド政権崩壊から一年を迎え、国民の融和を掲げながら一日も早い復興を目指しています。破綻した経済や崩壊したインフラなど、シリアには課題が山積みですが、時間をかけて再生へと向かおうとする人々の姿があります。そうした、この時代を生きる人間の姿を、私はこれからも現場に立ちながら見つめていきます。皆様、いつもどうもありがとうございます![小松由佳]

イラスト 長野亮之介
■年末の小松由佳さんの報告会で心底驚き、心を打たれた瞬間があった。報告会終盤の質疑応答の場面だ。参加者から「コロナ禍でお子さん二人を抱えて、口座残高も底をつき生活も苦しくなる中、不安にならなかったのですか?」という主旨の質問を受けた際の小松さんの受け答えだ。小松さんは間髪置かずに「ならないですね」とハッキリと言い切った。独特の澄み渡る声で発せられたその一言の中に、微塵のブレも迷いもまったく感じられなかったため、目から鱗が落ちるような衝撃を受けた。小松さん曰く「かつてヒマラヤ登山をしていて死ななければいいかなという思いが根本にある。経済的に苦労していても頑張り続けていればいずれ安定するかもしれないという楽観さがある」と。どう見ても大変な状況の中で、心の底からそう思い苦しい状況を乗り越えたその強さに驚いたのだ。潔いまでに何か突き抜けたものを感じた余韻が今も残っている。
◆もう一つ驚いたのが小松さんのご著書『シリアの家族』における田中伊織さんという編集者の存在の大きさだ。私は編集者の仕事を、本の構成をサポートし締め切りを管理、著者と出版社を繋ぐ存在という程度にしか考えていなかった。だが実際はまったく違っていた。小松さんが情熱をかけて書き切った文章を、それに応える形で何日もかけて休みがなくなるまでに全力で直しを入れる田中さん。そしてそのやり取りを何度も何度も重ねるお二人。締め切りを過ぎても尚より良いものを追求する姿。本当に良いものは粘りに粘った行為の中からしか生まれてこないのだ。そして著者一人だけで生み出すことはできないのだ。伴走者が必要なのだ。ここまで情熱をかけた作品は、作者だけでなく編集者にとっても我が子の命のような存在なのではないのだろうか。コロナ禍の中、育児や家事、生活に追われながらも文章を粘り強く書き続け、そして受賞された後さえも作品の表現を磨き直し『シリアの家族』を最後まで書き切った小松由佳さん、そして田中伊織さん、改めて開高健賞受賞おめでとうございます!
◆新北京での二次会終了直後に小松さんのお子さんたちからおにごっこに誘われた。活発でやんちゃな男兄弟と思っていたら、おじさーん(失礼だ!)と言って私の手をやさしく引っ張って誘ってくれた小さな手のサラーム君、いたずらっ子の愛嬌あるサーメル君。二人ともよい子に育ってますよ、小松さん。[塚本昌晃 今回も福井から参加]
■小松由佳さんの報告会に参加することができました。書籍を上梓されるまでの編集者との共働の道のりなど、普段はなかなかうかがえない内容で、お話を聞けてとても良かったです。小松さんが紹介されていた「優れたノンフィクションとは…」との江本さんの言葉にうなずきました。作品には作家自らのすべてが出てしまうものですが、小松さんの著書には、ご自身の人生まるごとでぶつかり、さらけ出し、乗り越えて変わる作家の姿が描かれており、読み手が応援したくなる切実さがあります。
◆わたしは以前、お呼ばれで伺った友人宅で小松さんにお会いし、小松さんが大人とお話されている時間に、お子さんおふたりと一緒に絵を描いたり、転げ回って遊んだり、とても楽しかった思い出があります。報告会では、そのときよりも少し成長したお子さんにも再会できて、とても嬉しかったです![西口陽子 画家]
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです(メールアドレス、住所は最終ページにあります)。
水嶋由里江 下島綾子・亘 秋元修一(4000円) 西嶋錬太郎(6000円) 中山綾子 北川文夫 竹澤廣介 樫田秀樹
■地平線通信560号(2025年12月号)は2025年12月17日に印刷、製本、封入され、宛名を貼り付けたあと新宿局に託しました。作業が終わったあとは、近くの四川料理「川芙蓉」で打ち上げをしました。この日の発送請負人は以下のみなさんです。毎日新聞記者でもある滝川大貴さんはこの日、毎日新聞夕刊一面トップ(!)に堂々と書いた岡村隆を追悼する「紡がれた探検家の意志 岡村隆さん 道半ばで逝去」の記事をひっさげての参加でした。なお、この記念すべき紙面は27日の報告会場でも希望者に配られました。みなさん、おつかれさまでした。
車谷建太 伊藤里香 中嶋敦子 白根全 久島弘 滝川大貴 古山里美 落合大祐 江本嘉伸
■2026年丙午 新しい年が明けました。本年もよろしくお願いいたします。個人的なことをいえば、巳年は精神的にも肉体的にも不安いっぱい、調子は最悪でした。今年はそういうものを払拭して出直したい。年齢からくる体力の問題もありますが、新たな地平を目指して踏ん張ってまいります。
◆昨年8月末、10日間の日本滞在を終えてテンバ夫婦はネパールへ帰って行きましたが、9月に入ってすぐのこと、テンバやナマ(嫁)チャンジュのみでなく他の村人からもメッセンジャー経由で思いも掛けない動画が送られてきました。チャーター機で運ばれる塑像、降ろされた塑像を担ぐ5、6名の村の若い衆、それを迎えるランタン村の老若男女。言祝ぎの歌を唱えながら、人々の顔は喜びに満ち満ちています。
◆動画の一瞬に塑像のお顔の一部が見えたとき、私はまっすぐに50年前に引き戻され胸が塞がれるようでした。それは見まごうはずもないえんじ色の僧衣を纏った造像。サムテンリン寺の塔頭チョモ・ラカン(尼僧院)に安置してあった泥像ミンギュル・ドルジェでした。もちろん若い衆に担がれた造像は新しいものでしたが、ミンギュル・ドルジェに列なる一族の者たちの特徴である大きな目と太い眉は正確に再現されていました。
◆ゴンバ地区にあったサムテンリン寺本堂もチョモ・ラカンも2015年4月25日に発生した大なだれによって跡形もなく流されてしまいました。ランタンリルン峰西陵の氷河の末端部分から、対岸に達するほどの莫大な量の土砂や氷は、建物のみでなく畑地も家畜も人も呑み込んでしまいました。村人たちは大震災から7、8年後、ゴンバ地区ではなく、本村であるユル地区のやや北側にサムテンリン寺再建を進めています。完成はまだもう少し先のようですが、チョモ・ラカンを併設するまで、ここはミンギュル・ドルジェの仮のお住まいになるようです。
◆ミンギュル・ドルジェについて少し。この小さなランタン谷の近代にとって、現在まで続くニンマ派の伝統を持ち込んだ重要な人物です。彼らが伝える系譜によれば、出自を7世紀まで遡ることができるらしい、時のチベット王に唐から嫁してきた文成公主の随行者であったらしい……と、限りなく横道に逸れそうなので、拙著からの引用で恐縮ですが、18世紀初頭のランタン谷の導入部を書き下してみます。
◆“1704年チベット暦8月3日、ドマルワ家のミンギュル・ドルジェは四度目の挑戦で、ようやくランタン谷にたどり着いた。モンスーンも明け、越えてきた後方の白き峰々も、谷を形作る氷と岩の稜線も、群青との一線をくっきり画していた。ミンギュル・ドルジェ29歳の秋であった。” もう少し続けます。
◆“ランタン谷から北へ直線距離にして60キロ、チベット側のナンユル、ゴラの寺を出てから、もう何ヶ月も経ていた。幼いころよりニンマ派ゾクチェンパであった父や恩師から聞かされてきた秘密の谷「ナムゴダカム」。17歳の時父も亡くなり、自分で見つけ出したいとの思いが募り、『道案内書』を片手に、マンユル地方のペルクラツォ(湖)からクンブ・ヒマールを越え、ランタン谷の北周縁部を縦走し、探索を続けてきたのだった。”
◆この導入部には、この谷と宗派に関わるキーワードがいくつか含まれています。中でも「秘密の谷・ナムゴダカム」。実際、現在のランタン谷周辺の村人、ヒマラヤの旅人や巡礼者たちにとってはミンギュル・ドルジェは「秘密の谷」を開いた尊い人なのです。修行僧であったミンギュル・ドルジェは、彼の自伝的詩歌集の中で「この谷は異教徒から強固に守られた種々の宗教的特典を具備した特異な地」として紹介しています。ただ、彼以前にランタン谷に住んだドゥッパカギュ派たちの記述にはその言及がなく、この「秘密の谷」というヴィジョナリー・ジェオグラフィーを描いたのはこの宗派のみであった、ということ。しかし同時に、時代はミンギュル・ドルジェや彼の系譜の人々がこのランタン谷に入りこむことを後押ししていたと想像します。
◆時は18世紀初頭、チベット政治の中央ではゲルク派のダライ・ラマ政権が着々とその基盤を固めつつあり、敵対する弱小の宗派、ニンマ派、ジョナン派、ポン教徒たちはチベットの周縁部分にはじき出され、その地で生き延びることを選択せざるを得なかったのではないかと思えます。ニンマ派以外のサキャ派、カギュ派たちはすでに政治の後方に退いていた時代。飛躍するけれども、ネパールヒマラヤに進出したニンマ派の伝道師たちも概ね同じようなアプローチでそれぞれの谷に地歩を固めていたのではないかと思う。16世紀末から20世紀へ。見事なお手並みだと言いたい。ミンギュル・ドルジェは今、再び熱狂的な谷の人々に迎えられています。
◆2026年丙午のチベット正月は2月18日。カトマンドゥの仏教聖地(スワヤンブナート、ボーダナート)周辺にはまもなく避寒を兼ねてヒマラヤ各地から仏教徒が集まってくることでしょう。ランタン村の人々も例外ではありません。いつの頃からかこれが習慣化していました。大震災よりも前、おそらく経済的にも余裕ができて、子どもの教育のための拠点(アパート)を持てるまでになっていたのでしょう。1か月間の湯治に出かけるものやカトマンドゥ盆地の外へ仏教聖地巡りに出かけるものもいます。
◆わが家でも例年通り、チベットの友人(Friend of Tibet)たちと丙午正月を言祝ぎたいと思います。18日は水曜日なのでその週の土日(21日、22日)を考えています。どうぞご一緒に![貞兼綾子]

■1月4日で右足のアキレス腱断裂から6か月。もう大丈夫。バイクでの200万キロを目指してガンガン走りますよ。あと8万3572キロ(1月1日現在)で200万キロ達成です。さ~、やるゾ![賀曽利隆]
■2025年12月19日に誕生日を迎え二十歳になった。二十歳といえば、合法的に酒が飲めるようになったこと、国民年金保険料の納付が始まること、そして待っているのは成人式である。世田谷区主催の形式的な成人式には興味なかったので、離島留学で3年間を過ごした神津島での成人式に出席するべく正月2日に神津島へと向かった。久々の東海汽船さるびあ丸で待っていたのは懐かしさではなく、大荒れの波による船酔いに耐えることだった。12時間船に揺られ続け最悪のコンディションで迎えた成人式だったが、かつて島での生活を共にした友人たちと再会することができた。新成人は離島留学生4名を含め25名、出席者21名で、改めて島スケールを実感した。
◆しかし島での成人式ならではの良さがあった。成人者は一人一人抱負を語り、両親からのメッセージが読まれた。記念品にはそれぞれの名前と波がデザインされたグラスをいただいた。また神津太鼓での祝いもあり、もともと太鼓をやっていた同窓生は振袖を着たまま太鼓を叩いた。
◆式の後は元担任の先生も交えて懇親会(という名の飲み会)が開催された。お酒をたしなみながら同窓生と語らい、担任の苦労話も聞いた。会の終盤、何名かぶっ潰れたころに高校時代親しくしていた友人と話していたのだが、彼曰く、離島留学生は成人式にはどうせ来ないだろうと思っていたそうだ。同期の離島留学生は海外留学中や私用、インフルエンザ罹患により欠席。出席したのは私一人だった。だからこそ「お前が来てくれたことがめちゃくちゃ嬉しい」と言ってもらえたことがとても嬉しかった。大学の授業や軽音楽部のライブ活動などで慌ただしい日々が続き、長いこと島にも行けていなかったが、ここが第二の故郷なのだと彼の言葉で改めて感じることができた。[長岡祥太郎]
■年越しのレイキャビクは、祭りだった。12月31日、朝から夕方までバイト(土産物売り店の手伝い)した足で知人宅に向かっていると、暗い空に花火が打ち上がった。散発的だった花火は、その後23時近くになると連続して打ち上がるようになり、23時半に外へ出たときにはすでにあちこちで咲いていた。中心街の高台にあるハットリグリムス教会へ向かう人の波に乗って坂を登ると、まちの端まで見渡す限りの花火。そのほとんどは、市民自らが打ち上げている。
◆年末にかけて購入され、その売り上げは消防隊の活動費に充てられるらしい。目の前で打ち上がった花火は時折、人混みに向かったり、教会に衝突したりしてヒヤヒヤしたが、身を守るのは自己責任ということなのだろう。カウントダウンとともに年が明け、鳴り続ける打ち上げの音を聞きながら、3時に寝た。翌朝はバイトなのだ。たくさん学んで考えて、日が延びたら山にでかけるぞ。今年もよろしくお願いいたします。[安平ゆう]
■「えもと~で~す」と、モンゴルの伝統の歌唱法であるホーミーのような江本さんの声が、受話器の向こうから聞こえてきた。遠くの方から聞こえてくるようでありながら信念のある声、誰もが忙しい年の瀬。さすが元新聞記者の江本さん、こういうときに、原稿依頼である。毎号の地平線通信の記事によって、会ったことのない旅人に親しみとたくさんのエネルギーをいただいてありがたい。
◆私たち夫婦二人の企画会社が、「写真展・地平線発」を開催したのは、1997年7月11日。既に28年たった。当時の滝野沢優子さん撮影のチリ・アタカマ砂漠の“手”のチラシがまだ部屋の壁に貼られている。会社はもうないが、229点の写真を集めた写真展の小さな写真集は、現在も私たちの生活で活躍しており、チベット、モンゴル、ジョージア、ナイジェリアなど、美術と文化人類学系を研究する方々に取材の折、影山が手渡している。
◆その美術関連のインタビュー記事を30周年のWebサイト『artscape』(「アート・アーカイブ探求——絵画の見方」)に載せている(https://artscape.jp/study/art-achive/backnumber.html)。絵画の研究者は探検家でもあるようだ。世界編・日本編があるので美術の世界への旅もいかがでしょうか。[影山幸一・本吉宣子]
■日本医学ジャーナリスト協会の会員になりました。拙著『医療への信頼』がキッカケで会員推薦をされました。昨年10月、目を向けられることの少ない「離島医療」をテーマにしたシンポジウムが開催されました。その裏方を1年間させていただき、とても勉強になりました。島の医療、特にドクターヘリに関しての応援の働きかけをしています。沖縄の気概のある一人の医師が飛ばし始めたドクターヘリは民間の人々の寄附によって支えられています。命をつなぐ冒険者たちです。
◆さがみはら写真新人奨励賞をいただきました。1月20日から新宿駅直結のニコンギャラリー東京で巡回展が開催されます。在廊日はフェイスブックとインスタグラムでお知らせします。皆さまにお会いできることを心待ちにしています。[河田真智子]
■12月31日~1月3日、北八ヶ岳の黒百合ヒュッテにて、冬山ケーナコンサートを行いました。標高2,450m、しらびその森と湿原に囲まれたすてきなところです。今年開催48年目となりました。この22年は、妻の長岡のり子のピアノとのデュオで演奏しています。曲目は、ラテンアメリカ諸国の民謡を中心に、『コンドルは飛んで行く』(ペルー中央高原)、『エンクエントロス』(ボリビア・ラパス地方)、『セジョーホス』(アルゼンチン・パンパス地方)、『太陽の乙女たち』(ペルー・クスコ地方)、『花祭り』(アルゼンチン・フフイ地方)など。黒百合夏山ケーナコンサートは7月11日(土)に開催予定。皆様ぜひお越しください。[ケーナ奏者・長岡竜介]
■失職しました。このところ騒がれている国公立病院の赤字体質。医療費には消費税がかからないのが最大の原因と思われるのですが、これに巻き込まれました。全国800余の国公立病院中、ワースト2位と10位、そして勤務中の病院の150位と千葉県立病院群が上位を占めたことで、65歳以上の看護師の雇用延長を廃止。そのあおりを受けての失業です。精神科救急、救急隊要請クラス教官、終末期看護とたずさわった32年が、ここに終わりました。それでも看護師の資格は強い、ナースバンク(看護師版職安)に行くと求人だらけ、かくして4月からの再就職に向けてのんびりと吟味しています。最終目標の殉職に向けて、まだまだ医療の現場にとどまります。[埜口保男]
■ぼくは、江本さんと地平線会議の仲間の方々が居なかったら、死んでたと思います。普通の現実社会で遭難していた。これは、大袈裟ではなく。ほんとうに。いつも助けていただいてます。ありがとうございます。久島弘さんが地平線会議は「セーフティネット」、車谷建太さんは「学校」と言ってる。まったくそのとおりだと想います。地平線会議は、ぼくの日常的な生命線です。「生きるために」必要不可欠。
◆報告者の方々のことを知る度に「ああ、人間って、こうも成れるんだ」と、いつも驚愕感動してます。目前の「御本人」の【リアル】に ぼくは「ぼく自身」のリアル、「今」「此処」を体感自覚することが出来ています。
◆「報告者」の皆さんは、地球の辺境から「早稲田」まで報告に来てくれてる。たとえばシリアとかK2から、早稲田に。御本人の「ずっと続いてる人生」のままに、報告会に立っている。仲間のままに話してくださってるような気がして ともだち というか。そしてそれは「だれしも」。
◆そういうライブな体感のときに「生きてる」「生きよう」と自覚します。その体感が、「地平線会議」の独特だと ぼくは 思います。[彫刻家 緒方敏明]
■浜比嘉島は旧暦重視のためあまり正月気分はありませんが、年末年始、牧場の来園者は多く、忙しい日々です。浜比嘉島でヤギの牧場を始めてはや20年。在来種の島ヤギやトカラヤギ、クロヤギの他、スイス系のザーネン種などいろいろなヤギが約30頭います。ヤギとふれあいに、近隣の家族連れだけでなく、在日アメリカ人や本土からの観光客も多く来られます。特に宣伝はしていませんがだいたい口コミやSNSを見て来てくださいます。
◆ちょうど最近、子ヤギがたて続けに6頭産まれてかわいい盛り! 皆さん抱っこしたり哺乳瓶でミルク飲ませる体験したりと、大喜び。また、うちの牧場の目玉である「ヤギと海散歩」も大人気でした。これはヤギ数頭と徒歩10分ほどの海岸まで散歩するというもの。リードはつけず、草をあげながら一緒に歩くんです。ヤギたちはおりこうで、ちゃんと人と歩いてくれます。
◆うちの牧場にいる子はみんな名前がついていてかわいい子ばかり。でも欲しいと買いに来る人には売らないといけません。ペットではないのだと割り切らなくてはなりません。この辺が何年たっても難しい。ヤギを渡して、お金を受け取ったときの何ともいえない罪悪感。メーメー泣きながら去っていくときのつらさ。何回経験しても心が痛くてたまりません。それでも、新しいところで可愛がってもらえるならまだ気は楽です。でも、沖縄では山羊は食用としても利用されます。食べられるのがわかっていて売るのはほんとにつらい。
◆昨年秋、ネパール人がヤギを売って欲しいと訪ねてきました。ダサインという祭りが明日あるから、仲間と屠るのだと。ネパール通いしていた私は久しぶりのネパール語など話したりして嬉しい反面、明日殺すの?いやいや、この子は売りたくない!って思ったけど他に買うアテがないと言う。その子はほんとに可愛げのある子だったから。連れて行かれたあと、私はホントにへこみました。まったく因果な商売だ。
◆毎日ヤギたちからたくさんの癒しや幸せを、そして生活の糧ももらっている。こういうことは避けて通れない。家畜とペットの線引き、私はいまだにできないでいます。新年早々重い話になりました。
◆岡村隆さんが亡くなるちょっと前にFacebookで紹介していた本、『私たちは動物とどう向き合えばいいのか』(石川未紀著)を冒険研究所書店に即注文して購入しました。今も何度も読み返しています。私はどう向きあえばいいのか、今年も悩みながらヤギたちと生きていきます。では地平線の皆様、今年もよろしくお願いします。[外間晴美]
◆西沢先生《中学の数学教師。私と親しくしてくれていた》が結核で倒れたという。言葉が出ない。年賀状を出してきたばかりなのに…。
◆超過勤務《当時横浜郵便局で年賀状の区分けのアルバイトをやっていた》が3時間ほどあって終わったのが8時だったが、その足で先生のお宅伺ってみた。留守を預かるお婆さんかいて、詳しいことを聞くことができた。胃潰瘍とのことである。24日、血を洗面器に2杯分くらい吐いたのではじめ肺だと思ったが専門の医師によってそれがわかったそうである。
◆一昨日に胃の3分の2くらいを切り取る大手術をやったが、経過は良いそうである。胃潰瘍といっても重大な病気であるが、結核とばかり思っていたので何故かホッとした。面会謝絶なので会うことはできないが、明日でアルバイトをやめることにしたので時間に余裕はある。寒がり屋の先生の事なのでこの冬を越すのはどんなに辛いかもしれないが、先生の精神力の強さを願うのみである。
◆小松田先生《中学の理科教師》の家へ伺った。昭先生も幸子先生《同じく国語教師。当時結婚したばかり》も元気な姿を玄関に見せていた。シェパードが一匹だいぶ大きいのだが、無邪気に僕に飛びついた。まだ一つということであるが、何よりも可愛い。僕も大きくなったらこんな可愛い大きな犬を飼いたいと思った。
◆先生の家の庭は素晴らしい。せまいのだが、石どうろうがあって純日本的な感じの庭である。それがお二人の性質に本当にあっているのではないかと思った。先生2人と昭先生のお母さんとそれから何か親戚関係の人と思われるきれいなお姉さんとが居られた。皆気品があって、正月らしく美しい着物を着ておられた。昭先生の言葉は聞いていて本当に気持ちが良い。絶対に優しい言葉使いだ。お母さんのことは「ママ」と呼ぶ。幸子先生は僕のことを「江本君」と呼ぶ。百人一首をして僕が非常に素晴らしいのでニコニコしていたら「江本君、カルタが沢山とれて嬉しいでしょ」と言っておられた。昨日夢にずうっと見ていた顔とちっとも変わりはなかった。
◆小松田先生は僕の理想の夫妻である。僕も大きくなったら大きな家なんか要らないから幸子先生のような人と結婚して静かに幸福に暮らしたい。帰る時は去り難い思いだった。幸子先生は最後に出ていく時に「江本君、手紙をもらったままだたわね。素晴らしい手紙だったわ。また下さいね」と言われた。どこが素晴らしかったか、多分雪の降っているのを書いたからだろうが、とにかく嬉しくて仕方がなかった。「下さいね」などと言われなくても何回でも出したくなってしまう。目下僕が教員になりたいと思う時はその本質たる「学校における教員」をそう思うのではなく「家に於ける教員」を思う時である。
◆家へ帰ったら生田隆子さん《兵庫県在住のペンフレンド》から年賀状が来ていて「長い間お手紙を出さずすみませんでした」、などとしてあった。五か月間もの空白はあったが、僕は急に懐かしくなってきて久しぶりにペンを執る気になったが、レターペーパーがなかった。
◆小松田先生の家にまた行きたい。今度の春休み、行けるものなら姉さんと行きたい。姉さんはもちろん賛成するだろうから。
■2026年は幸先の良い始まりかもしれない。前号で私はデンマークに対する熱い思いを書いたばかりなのに、なぜか今号でも拙文を掲載していただくことになった。事の発端はこうだ。前号の掲載を自慢したく、友人にLINEしたところ、「ペンネーム使う事にしたの?」と聞かれ、はて?と思って誌面を確認したところ、綾子が郁子さんになっていた。特段自分の名前に思い入れはない方だと思っていたのだが、郁子さんに申し訳ない気分と、やはり少々の居心地の悪さを感じて、江本さんに恐る恐るメールをした所、訂正を兼ねて再度文章を載せていただけることになったのだ。江本さん、ありがとうございます! 今回は、なぜデンマークでは「民主主義が正しく機能しているか」と考えたときに、もしかしたら、私が旅を通じて、朧げに見えてきたデンマーク人像をまとめてみることがヒントにつながるかもしれないと、デンマーク人に抱いた印象を書き出してみた。
◆私は旅をするとき、近くに動物園や水族館があると必ず寄ってみる。動物が好きなのはもちろんだが、人間も同じ動物だと考えているので、動物を観察する動物(ヒト)を眺めるのが好きだといった方が正確かもしれない。デンマークの動物園で誰よりもはしゃいでいたのが、ヒト科の父親という生き物だった。「見て!パンダが寝てるぞ!」「こっちは爬虫類館だって!」子どもたちのテンションはそれよりやや低そうだった(檻の中の動物たちのテンションは更に低かったが)。また、疑問に思ったことはそのままにしないという点でも5歳児に近いといえるかもしれない。大人でも「なんで?」「そもそもどうして?」と口にすることを恥ずかしく思っていないようだった。
◆デンマークでは人生の様々なタイミングでギャップイヤーを持つことが普通である。学生時代に、または働き始めた後でも立ち止まって自分を見つめ直す時間を持つことが社会的に許されている。高校進学前の14歳~18歳の間に通うことができるエフタスコーレは全寮制の私立学校で、アートやスポーツなど自分が興味を持っている分野の学校を選び、ここで本当に好きなことを見つける機会を得る。幼少期より周りから植え付けられた自分像から解放される機会にもなり、キャラ変する子も多いという。あるエフタスコーレを訪れた際に、校長の思いつきで急遽学生寮を見せてもらうことになった。突然の見ず知らずの外国人の訪問にも関わらず、生徒たちはにこやかに「いいよ!どうぞ」とドアを開ける。そうか普段から片付けられているんだろうな、開け放たれたドアの奥を見て思わず声が出た……。
◆「汚なっ!」2段ベッドの上からも下からも布団と洋服で雪崩が起こり、窓側の鏡前はメイク道具がぐちゃぐちゃに散乱していた。おせじにも綺麗とはいえず、むしろ「汚部屋」といっても過言じゃない部屋の中で15、6歳の女の子たちは恥じらう様子も見せず、美しく微笑んでいる(男子の部屋の方が若干片付いていたのは興味深かった)。校長室の扉もいつも開け放たれ、常に生徒や先生が出入りしていた。デンマークでは片付いていることより、他者をいつでも受け入れることの方が重要という考えが主流だ。
◆デンマーク人の話し方はとても穏やかで控えめな印象だ。だが、よくよく聞いていると「僕たちはこの学校で1番目、2番目に頭がいいんだけどね」などの自慢話をさらっと入れてくる。一見シャイで、特に自分を誇示しているわけではないのになぜか自信があり、自己肯定感が高そうに見える人が多かった。
◆ヒントは森の幼稚園にあった。空気が冴え、木々の高い所で鳥たちが会話している、そんな森の少し開けた空間に幼稚園はあった。幼稚園といっても建物らしきものは道具小屋くらいしかなく、遊具は基本手作りだ。外には斧が刺さったままの薪が無造作に置かれ、時には蛇やキツネもやってくる。雨や雪が降ろうがどんな天候でも、子どもたちは外で遊ぶことになっている。その日の遊びは子ども自身で決める。ケンカが起きても保育士は仲裁をせず、自分たちで解決するのを見守っている。そんな幼稚園がデンマーク国内には700か所もある。デンマーク人は子どもを子ども扱いせず、対等の“人”として見ているから子どもにも意見を求める。小中学校に上がると、校則は自分たちで決める。不便なことがあれば、自分たちの意見で学校を変える。そういう成功体験を積み重ねていくことが自信につながっているのかもしれない。
◆私の抱いたデンマーク人の印象はまだまだあるが、そもそも国民性という言葉で一括りにしていいのだろうか疑問ではあるし、短い滞在期間で得た印象に過ぎない。だから次回はもっと長く身を置いてみたいと思う。それこそ自身がフォルケホイスコーレ(北欧独自の教育機関)という大人の学校で寮生活することも視野に入れて、今後もデンマークにアクセスして行こうと思う。[中山綾子]
★そう。12月号で名前を間違って(「郁子」と)掲載してしまった。幸い、中山さんは2本私に送ってくれており、どちらも通信に載せたかった内容だったので思い切って新年号にも登板していただいた。すいません、名前間違いをしないのは基本の基なのに。[江本]
■あけましておめでとうございます。今年は、今までになくワクワクした心持ちで新年を迎えているので、そのことについて書かせていただきたいです。
◆ちょうど1年前の地平線通信で私は、新年に寄せて、「思い通りにいかないことに直面しながら生きていきたい。経験や知識を蓄積して初めて、大きな喜びを感じられるような暮らしをしてみたい」と書かせていただきました。新年早々一人で薪ストーブの煙突掃除に悪戦苦闘し、それでもなお、スイッチひとつで何でも叶う生活ではなくて、電気もガスもない不便な環境を楽しめる人間になりたい、と思ったのでした。
◆それから1年が過ぎ、ついに私は、夢に描いていた「電気ガス水道なし生活」を始めることができたのです。昨年11月末から、知り合いから譲り受けた古い小屋で、一人暮らしを始めています。江本さんにも2024年秋に訪ねていただいた、私の地元、北海道南富良野町の林の中に佇む、大きなログハウスです。ランプ・薪ストーブ生活への想いが私よりもはるかに強い、パートナーの五十嵐宥樹と一緒に生活を始めたかったのですが、彼は秋から冬にかけて馬搬修行で北海道厚真町に滞在しています。「待ちきれないから私一人で始めちゃおう!」と、勢いで動いてしまったわけです。
◆昨年秋から、ちえん荘の仲間や地元の人に手伝ってもらい、経年劣化が激しい丸太小屋に少しずつ手を入れてきました。本格的な冷え込みが襲ってくる直前になんとか、寒さをしのげる空間が完成。ひとまず1か月と少し暮らしてみましたが、極寒期にも耐える気がしています。熱源は薪ストーブなのですが、なにせ隙間だらけの大きな2階建てなので、家全体を温めようとすると無尽蔵に薪が必要です。五十嵐や仲間たちが協力して用意してくれた一冬分の薪には限りがあるため、家の1階部分に壁を作って空間を区切り、いただきもののスタイロフォームで天井部分と四方の壁をぐるりとしっかり囲って、私一人が暮らすための10畳くらいの暖かいスペースを確保しました。
◆電気がないので、暗くなったらロウソク。というか、「暗くなったら寝るんです」(ドラマ『北の国から』より)を心がけています。水は、夏の間に沢水を引くことに成功しましたが、まだ水源地の整備が脆弱なため、水道管が間違いなく凍結するとみて冬場は使用を断念。幸い、私の実家がすぐ近くにあるので、20リットルのポリタンクで定期的に水をもらっています。冷蔵庫は……生活空間用に区切った空間以外は外と同じ温度になるので、家全体が巨大な冷凍庫状態です。薪ストーブで暖めている空間ですら、部屋の隅は冷蔵庫以下の気温になります。ガスがないのでカセットコンロを置いていますが、今は時間に余裕があるので、なるべくストーブの上で何でも調理するようにしています。節約節約。
◆16時を過ぎると外はもうかなり暗くて、読み書きするには光の量が足りないのでロウソクをつけます。そうすると、ロウソクの火って案外引き込まれてしまって、じーっと見ていたら1時間が経っていたりする。ストーブの前面には大きな窓がついていて、中で火が燃える様子が見えるのですが、これまた見始めるとずっと見てしまう。電気に照らされた明るい空間の中でこれほどストーブの火に見入ることはないのですが、真っ暗な中だと、なぜだか、見続けてしまう。焚き火を見続けてしまうのと同じようなことですね、きっと。それを毎日、家の中でやっています。
◆もちろんWi-Fiがなく、電波もないので、スマホも用なし。今まで、本当は興味がないのに中毒症状でぼーっと見続けてしまっていたYouTubeやInstagramも、見ることができないのでひたすら火を見る。1か月間この生活をしてみて、正直、救われたような気持ちにさえなっています。依存体質の私は、スマホを持ってからというもの、スマホの誘惑から逃れられず、集中して本を読んだり思考したりすることが昔より難しくなってきていました。ここでは、スマホを見る代わりにぼーっと火を見たり、本を読んだりできて、しかもそれが一時の休暇などではなく、生活そのものです。「電気や水道がない不便さ」もほとんど感じないくらいに、心地よい生活なのです(少なくとも、今のところは……)。
◆そういうわけで、昨年末からの流れに乗って、幸先良く新年を迎えることができました。今年の春は、父に手伝ってもらって、この丸太小屋の近くに物置小屋を作る予定です。建物を作るのは初めてなので、今からワクワクしています。それから、五十嵐がいずれ、仕事の相棒として馬を飼う予定なので、馬の飼育を学べるような、馬関係のアルバイトも見つけたいと思っています。自分の「椅子張り職人」としての工房の準備もしたいし、北海道地平線もあるので、そちらも楽しみです。盛りだくさんな1年になりそうです。最高の1年にします。今年も、よろしくお願いいたします。[ちえん荘住人 笠原初菜]
■地平線会議の皆様、今年もよろしくお願いします。毎年この時期は、広葉樹の森を間伐し、木を馬で運ぶ仕事を教わっています。100年生の樹を更に大きくすべく、立派な木は残し、競合する木を倒します。残した木に傷をつけないように、重機ではなく馬による搬出が選択されます。100年というと老齢のように感じますが、ミズナラなどは条件が良ければ700年は生きるそうです。眼前の巨木が樹木界ではまだ若いということ、私の短い時間軸ではなかなか想像が追い付きません。
◆この現場も今季で3度目を迎えました。例年12月頃から2か月程度、年をまたいで現場が続きます。年末は一度「ちえん荘」に帰り仲間と過ごしましたが、日々の緊張感と、年末年始特有の解放感とのズレがストレスになり、正月が素直に楽しめなくなってきました。
◆伐採木からは、道内の銘木市に並ぶ丸太が採れるものも。東大や北大の演習林から出る銘木に比べれば小振りですが、稀有な伐採経験です。皆伐ではなく、抜き伐りなので、限られた空間めがけて正確に木を倒す技術が鍛えられます。スラッと伸びる針葉樹とは違い、広葉樹は枝ぶりも複雑で、幹はほぼ必ずどこかに傾斜しています。馬の運びやすさも加味して、倒す順番や方向も調整します。倒した木が立木にかかると、馬で引っ張って外せる場合もありますが、絡むようにひっかけてしまうと、馬が大変苦労します。
◆汗だくになりながら、重たいナラの木を何度引っ張っても外れない。「ジャン」と鎖が張り詰める音が森に響く度、馬に申し訳ない気持ちでいっぱいになります。恨めしそうに馬に睨まれると、その視線が忘れられず、次の伐倒は慎重にならざるを得ません。木の伐り方は馬に教わっています。こうした現場に若手の自分を受け入れてくれている親方のおおらかさにも感謝しつつ、充実の日々を重ねています。
◆暮れに、「馬を買わないか?」という話にも恵まれました。諸事情あってまだ詳しく報告できないのですが、来年の春には力持ちの馬を迎えることになるかもしれません。予期せぬ縁に戸惑いながらも、気を引き締めています。
◆毎年恒例のちえん荘書き初め大会。今年は「備蓄」と書きました。米ではありません。「家畜に備える」という意味です。資金を蓄え、飼育環境を整え、馬を知り、備える。現実に向き合おう、という凡庸な抱負となりました。今年は午年らしいですが、遅れてナンボの我が家にまだ馬は来ません。今年も周回遅れ上等のゆとりでいきたいと思います。[ちえん荘住人 五十嵐宥樹]
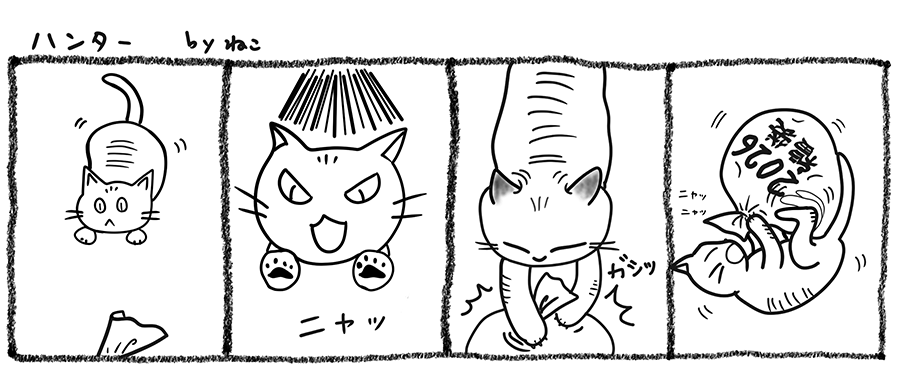
《画像をクリックすると拡大表示します》
■第555号にて自己紹介をさせていただいてから半年ほどたってしまいました。南極観測隊を目指して北大に進学した、青木銀です。みなさま、あけましておめでとうございます。
◆今年の正月は北大探検部の現役、ちえん荘住人など探検部OBOGの方々、山岳部OBの方など大勢で集まって過ごしました。五十嵐さんたちからは555号に載せていただいた文を読んだうえで激励をいただきました。当の集まりには初めて会う方も何人かいらっしゃったのですが、自己紹介をしたところ地平線通信で読んだ南極の子だと認識していただいたようで、地平線のつながりの強さを実感しました。
◆新年の抱負を書き初めとして表すという恒例行事があるようで、自分は「極学」を掲げてきました。きっとこんな言葉は存在しないので意味や読み方はほとんど自由なのですが、自分的には「学びを極める」と「極域を学ぶ」のダブルミーニングのつもりです。南極に行くために学ぶべきことをどんどん学んでいく、そんな年にしたいと思います。今年の抱負として掲げましたが、大学院に行くまでの3年間の目標といってもいいかもしれません。この書き初めは今すべきことを再確認する良い機会になりました。
◆今、大学では後期の授業もほとんど終わりを迎えているのですが、その中に極域海洋学入門というものがあります。地平線にもきっと詳しい方がいらっしゃると思うのですが、非常に興味深い学門でした。今まで南極でやる研究といえばアイスコアから過去の環境を特定したり、氷河や氷床の状態を観測したり、いずれも陸上で行われるものを思い浮かべていました。
◆海を観測し研究するというのは自分にとっては新しくて、極域海洋学者として人生を歩んでいく可能性もありえるのだろうと思います。極域は興味深い研究分野が多くて、将来どんな研究をしたいかはまだまだ決められそうにありません。極域というと南極だけでなく北極も含まれますが、もちろん南極だけでなく北極にも興味があります。チャンスがあればぜひとも行ってみたい。
◆日本の極域研究の中心である極地研と北大水産学部が中心となって行われるArCS Ⅲプロジェクトに先日応募したのですが残念ながら落選してしまいました。ArCS Ⅲとは若手北極研究者の育成のために実際に北極海に行って様々な分野に基づいて観測、調査するというもので、全国の学部生から8人ほどしか選抜されないようです。非常に残念ですが、北極行きは次の機会までお預けです。
◆悪いことばかりではなくて、先ほどお話しした極域海洋学入門では今年の(67次)南極観測隊隊長である北大低温研の青木茂教授の講義を受けることができました。南極観測隊についても聞くことができ、非常に刺激的な時間でした。北海道で過ごす毎日はそんな刺激的な出来事であふれています。雪も東京で生まれ育った自分にとって信じられないくらい厚く積もっていて、毎日その上を歩くのが楽しいです。北海道に来て本当に良かった。つくづく思います。
◆地平線会議が北海道に来るのもいよいよ来年ではなく今年となりました。きっと開催されるまでの数か月間もすぐに過ぎてしまうんだろうと思います。江本さんはじめ地平線の皆様に実際にお会いするのが楽しみです。それまでは学を極めながら、少しでも南極に近づけるよう精進してまいります。[北大探検部 青木銀]
■2026年初秋に予定している北海道での地平線会議を成功させるため、1万円カンパを募っています。北海道地平線を「青年たちが集う場にしたい」、というのが私たちの希望です。交通費、宿泊代など原則参加者の自己負担としますが、それ以外に相当な出費が見込まれます。どうかご協力ください。[江本嘉伸]
賀曽利隆 梶光一 内山邦昭 新垣亜美 高世泉 横山喜久 藤木安子 市岡康子 佐藤安紀子 本所稚佳江 山川陽一 野地耕治 澤柿教伸(2口)神尾眞智子 村上あつし 櫻井悦子 長谷川昌美 豊田和司 江本嘉伸 新堂睦子 落合大祐 池田祐司 北川文夫 石井洋子 三好直子 瀧本千穂子・豊岡裕 石原卓也 広田凱子 神谷夏実 宮本千晴 渡辺哲 水嶋由里江 松尾清晴 埜口保男(5口) 田中雄次郎 岸本佳則 ささきようこ 三井ひろたか 山本牧 岡村まこと 金子浩 平本達彦・規子 渡辺やすえ 久保田賢次 滝村英之 長塚進吉 長野めぐみ 北村節子 森美南子 飯野昭司 猪熊隆之 岡村節子 加藤秀宣 斉藤孝昭 網谷由美子 阿部幹雄 高橋千鶴子 岡貴章 森本真由美 山本豊人 小林由美子 斉藤宏子 渡辺三知子 小林進一 岩渕清(3口) 那須美智 森国興 丸山純 関根皓博 三輪主彦 中山綾子
★1万円カンパの振り込み口座は以下のとおりです。報告会会場でも受け付けています。
みずほ銀行四谷支店/普通 2181225/地平線会議 代表世話人 江本嘉伸
■私ごとで恐縮だが、私は登山を11歳のときに初めて自分で計画して自分で実行し、それが記憶にある初登山になる。登ったのは三峰神社の表参道なのでこれは登山かと言われそうだが、11歳の子どもにとっては結構大きな経験だった。服装も私はトレンチコートを着ていたと思うし、リュックサックではなくて手提げの奴もいた。まだ三峰神社にロープウェイがあったころで、下山はロープウェイに乗ったように思う。下山したら登山口に奥秩父の概念図を書いた大きな看板があり、「雲取山」を指さして「次は“うんとりさん”に行こう!」と言ったのを覚えている。それから55年が経ち、細々と登山を続けてきたが学校で行った遠足登山や林間学校、大学山岳部の1年生時の合宿、そして初期のヒマラヤ登山などの一部を除いては常に自分で計画して登山をしてきたので、登山という行為は自分で計画して自分で実行するものであると思っていたし、計画を作るということは実に面白くて創造的で登山という行為のかなり重要な部分を占め、登山が主体的で創造的であるための根幹の部分ではないかと考えてきた。それは当然であって疑う余地のないものであり、それを他者に委ねてしまったらもはや「登山」とはいわないのではないかくらいの偏見を持つに至っていた。そんな私にとって山岳会内の山行が「この指とまれ」方式になったことを知ったときはまさかと思い、「ツアー登山」なるものが登場したときは驚天動地の気持ちだった。
◆独断と偏見にまみれた私は、他者に計画を委ねるだけではなく一緒に登山をするメンバーとも現地で初めて顔を合わせると知ったときは、観光旅行じゃあるまいし「ありえない」と口走ってしまった。ただ、ツアー登山はけしからん行為でやめるべきであるということではなく、繰り返すが「計画立案を他者に委ねるのは、登山の面白さの本質である主体性と創造性を自ら捨てることになるのでものすごく勿体ない」という気持ちが強く、だからそこを自ら手放してしまうことは信じられないという気持ちが強かったとあえて付け加えておきたい。
◆そのような私が今冬、ある山小屋主催のツアー登山をボランティアでお手伝いすることになった。毎年この時期には剱岳に入り、長いときは2週間誰にも会わないことが珍しくない山行をしてきた私にとって晴天の霹靂的だったといえる。立ち位置はあくまでもガイドの方の補佐なので、失礼な言い方をすれば山岳部の1年生を見るように行動すればいいだろうと考えていた。そして私は、このツアーに参加した方々はどのような気持ちやきっかけで参加したのかなぁと思っていたのでそこを訊いてみると、「一人で冬山に登るのは不安が大きい」や「冬山の経験がほとんどないので最初はツアーが安心できると思った」という意見が多かった。
◆今はそもそも山岳会や山岳部に所属しない人が多いので予想はしていたが、何となく消化不良気味の印象だった。そして途中で体調を崩してしまった方が下山することになり、登山口近くまで一緒に下ることになった。本人は同行を遠慮されたがそんなに遠い距離(標高差)でもないので一緒に下山することにしたが、さすがに初日の途中で下山することを決めた姿は寂しそうで、気持ちを紛らわそうと思い色々と話しかけさせてもらった。
◆その方はいわゆる企業戦士と呼ばれた人たちの次の世代に属する方で、真面目に仕事に打ち込んできた軌跡がにじみ出ているような誠実な方で、ガツガツと山に登りそうな、山ヤの雰囲気はない。その方も一人で冬の山に登ることの不安を漏らしていたが、登山の前日に登山口に近い温泉で宿泊した際に同じツアーに参加する方々が同室になり、折角みんなで頑張ろうと話していたのに自分は下山することになったことがとても残念で寂しそうに見えた。そしてこういう登山は友だちができることも魅力だと話されていたことがとても印象的で、私は分かれた後その方が見えなくなるまで目で追っていた。
◆再度登り返しながら、どのような形であれ登山が先の方の生活の礎の一つになっていることは間違いないなと感じた。冬でも人の多い尾根道だが、このときは時間が遅くなったせいか誰もいない。一人で登りながら、登山の在り方とか本質などという視点ではなく、人が自分の生をより豊かにするということはどういうことなのかを妙に考えさせられ、ツアー登山という形も悪くないのかもしれないと感じた1年の終わりだった。
■正月はやはり箱根駅伝だ。今年も青山学院大が往路、復路とも優勝し、2012年の初制覇以来12年で9度目の栄冠を勝ち取った。とくに5区のあの険しい山登りで3分42秒差をひっくり返し、トップを奪った黒田朝日選手の走りには驚愕した。これまで多くの素晴らしい俊足に「山の神」の名を冠せられたが、それらをはるかに上回るスピード。走り終えて差し出されたマイクに「自分こそシン山の神だ!」と叫んだが、まさに。
◆私も一時はマラソンに入れ込んだことがある。走り出したのは40歳からでフルマラソンのベストは48歳になって「若潮マラソン」という大会で出した3時間08分9秒(とすらすら出てくるのがいじらしい)だった。海宝道義さんの「しまなみ海道100kmウルトラ遠足(とおあし)」にも何度も出たが、走るのは70歳を過ぎてやめた。人生、案外長いかもしれない。本格的登山もまだ余裕のあるうちにやめているし私はつくづく「頑張らない種」の人間である。[江本嘉伸]
 |
探検的ココロ
「山伏に興味を持ったのは、山で亡くなった友人たちの弔いみたいな気持ちからかな」というのは平靖夫さん(80)。20年前に羽黒山の山寺で一年修行し、円教坊という行名も。「寺系の山伏は、明治以降長らく迫害されていた。だからか神道系より仏教の源流の面影を残している気がします」と平さん。 「もっぱら僕は護摩ならぬ薪ストーブを焚くばっかりですが」。法政大学生時代の'65年に探検部を創設。中央アジアなどを探検しました。卒業後は山小屋でバイト。下山後は興味の赴くまま世界各地のクロスカントリースキーの大会に参加。10ヶ国で計700kmを完走したことも。 最初に関わったフィンランドとの縁が濃く、先住民のサーミ人とアイヌ民族の交流を企画するなど面白さを杖に人生を闊歩してきた自由人です。現在は山形県に住み、地域の活性化や環境保護などの活動に力を注いでいます。 今月は平さんにその多彩な足跡と柔軟なココロ模様を語って頂きます。 |
地平線通信 561号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2026年1月14日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|