

6月18日。予想はしていたが、早くも猛暑の日々である。今日は東京も35度に達するそうだ。私は今朝からついに半袖になった。
◆イスラエルとイランの大規模な衝突で、カナダ・西部アルバータ州のカナナスキス(2つの川の合流地点の意味という。Wikipediaによると人口わずか156人だそうである)でのG7サミットに出ていたトランプ米大統領は初日の会談だけでさっさと帰国してしまった。世界を揺るがすとてつもない案件が生じたのは確かだが、石破首相はじめ残る6か国のトップは軽く扱われたものである。
◆日本ではこの6日、野球の長嶋茂雄さんが89歳で亡くなり、それが大きく報道されたことでプロ野球にかけた「ミスター」の存在がいかに大きかったか思い知らされた。日本人はあの天性の明るさに惹きつけられてきたのだということをメディアの対応で思い知った。
◆9日には45回の優勝を誇るモンゴル出身の元横綱、白鵬が日本相撲協会を退職、新たに「世界相撲グランドスラム」構想を発表した。世界の相撲好きの少年たちを対象にすでに15回も実施してきた「白鵬杯」をさらに広げ、世界的なスポーツにするという。トヨタ自動車の豊田章男会長らの支援を得ているこの構想、日本の相撲界は、どう対処するのか。
◆17日、ロサンゼルスは、不法移民の徹底的締め出しを進めるトランプに抗議する市民団体と治安部隊の衝突で騒然となっていた。そんな中で大リーグドジャースの我らの「ショーヘイ」が663日ぶりに「二刀流」でマウンドに立った。大谷翔平二刀流復活の瞬間である。こんな場面に居合わせることができたら幸運なんてものじゃない。と考えて思い出し、LINEで訊いた。
◆「建太君、まさか大谷が2年ぶりに投げる日に居合わせるわけじゃないよね?」。即返信「もちろん、今まさに居合わせてます。20分後に大谷君が投げます! 今から国歌斉唱です。すごいタイミングで来たものです」。わぁー!なんと我らが印刷局長、津軽三味線弾きの車谷建太君が居合わせているのだ。親孝行の彼が母上と姉君の3人で大谷観戦に行くことはひそかに聞いていたが、それが今から始まろうとしている「二刀流復活」の日だなんて。
◆「了解しました!ダウンタウンはデモで大変な時期ですが、今日は大谷翔平に町中が沸いております。そうです。いま観客席にいます。まもなく試合開始です!」。投げたのは1回だけでヒットを打たれて失点したが、いきなり見せた「球速160キロ」に観客はのけぞった。おまけに投げ終わったら大急ぎで打席に立つ。なにしろトップバッターなのだ。そして自分のバットであっという間に2つの打点を叩き出した。うーむ。やられてもやりかえすことができるこんなスポーツマンは確かに初めてかもしれない。
◆「まさかパドレス戦初戦に投げるとは、本当に僕達家族は運が良すぎますね。引き続き、安全第一でこの連戦を心に刻み込んで帰りたいと思います。母も僕達も一生に残る思い出です」。建太君、毎月毎月縁の下の印刷仕事に汗かいていることへの神様のご褒美だよ。そして今回、建太君の代役印刷局長を引き受けてくれた中畑朋子さん、ありがとう。あなたにも必ずご褒美がありますよ。
◆2026年初秋、北海道西興部村で予定している地平線の集まり。ゆっくりだが動き出しつつある。今回の試みは昨年秋、私がちえん荘の皆さんを訪ねた時にすでにはじまっていて、この後1年あまりかけてさまざまなアイデアを生みつつ西興部村の現場ににじり寄っていくのがいいのでは、と私は考えている。すでに「1万円カンパ」も始まり、多くの方の協力いただいている。北海道の若者たち、毎月ここに登場してね![江本嘉伸]
■今回の報告者は、1975年に女性として初めてエベレストに登頂した田部井淳子さんとともに登山隊に参加した、北村節子さん。今年2025年は女子エベレスト登山隊が登頂を果たしてからちょうど50年という節目の年でもある。新聞記者として働きながら、国内外の山を登り続けてきた北村さんが、自らの山との歩みと、大正〜昭和の前半まで日本における女性登山の軌跡を語ってくれた。
◆北村さんは1949年、戦後間もないベビーブームの時期に信州で生まれた。営林署に勤務する転勤族の父のおかげで何回も転校したが、行く先々で田舎暮らしを満喫する。信州は学校登山が盛んで、小6では佐久の「双子山」、中2では「木曽御嶽」に登ったのがよい思い出だという。木曽御嶽は、北村さんにとっても初の3000m超えの経験だったが、みな、体育授業用の綿の白いトレパンで登り、校長先生はゲートル姿だった。まだ中学校の生徒たち、中には音を上げる子もいたが、北村さんにとってはとてもエキサイティングで、「山っていいなぁ」と思う原体験となった。
◆中学卒業後は、親元を離れて松本市の松本深志高校へと進学した。北村さんが3年生のとき、忘れられない事故が起こる。それが「松本深志高校西穂落雷遭難事故」だ。学校登山の一年後輩の2年生55人が落雷に遭い、そのうち11人が亡くなるという痛ましい事故で、これを受けて多感な思春期の生徒たちは大きな衝撃を受けた。後追い自殺まで起き、「生きるとは何か、死ぬとは何か」と考え込む生徒も多かったという。北村さんもやはり大きなショックを受けたが、この遭難は、山へ強い関心を持つきっかけともなったという。
◆翌年、上京しお茶の水女子大学に進学した北村さんは、「山が見えない」という東京の風土に素朴なショックを受ける。そこで、追悼登山と称して初めて穂高(西穂)へ向かった。弔いのために登山をしているはずが、そこで登山の魅力にハマってしまう。「なんて素敵なところなのだ!」と感銘を受け、“穂高病”にかかったのだ。なんとかしてここに通いたいと思い、翌年の夏休みから「上高地高山植物監視パトロール」のバイトに参加。北村さんにとってそれは「この世で最高のアルバイト」だった。山小屋で3食が提供され、山々をめぐっては、植物や昆虫などを採集する登山者や観光客に注意したり簡単な説明をする業務。そんな中で山に対する興味がどんどん増し、山の知識も増えていった。そこでのアルバイト代はすべて、登山装備へと消えていく。冬山登山を志していた北村さんは、冬山はやらないという大学山岳部入部はやめにし、独学で登山技術を学んで山行を重ねていった。
◆大学卒業を見据えて就職活動を始める際にも、女性であるがゆえの苦労があった。1970年代の当時は男女雇用機会均等法などなく、多くの求人は「男子のみ」。女性向けの求人は数少ない中で、運良く読売新聞社に就職することができた。が、当時の労働基準法では女性は深夜早朝勤務に就かせることができないという事情があり、本来、研修後は地方支局に配属されるのが通例だった中で、支局での勤務は難しいと判断され、いきなり本社社会部に配属。同期では女性は北村さんただ1人で、社としても17年ぶりの女性採用だったのだという。超・男性社会の新聞社において北村さんは記者としての道を歩み始める。世の中の動きを活字で伝えるという仕事は刺激的であり、手探りしながら仕事に邁進していった。
◆そんな中、1973年のある日、とある15行ほどのベタ記事を目にした。その小さな記事には女子登攀クラブが1975年の春にエベレストに登る権利をゲットした、とあるのにびっくり。というのも、そもそもエベレストといえば、ネパール政府から登山の許可をもらえるのは春、秋にそれぞれ1隊のみ。世界の強力な隊が虎視眈々と狙っていたから。「女性だけで挑戦」という発想自体がラディカルだったし、それに許可が出た、という事態も思いがけないことだった。
◆真っ先に「これはぜひ取材したい」と思い、即、隊の母体となる「女子登攀クラブ」が奥多摩のバンガローで開いた隊の準備会を取材、そこで出会ったのが、田部井淳子さんだった。北村さんにとって、田部井さんは強い印象を残す女性だった。当時の女性は語尾を濁すような話し方をするのが通例であった中、「私はこう思います。みなさんどうですか」ときちんと句点をつけて自分の意見をはっきり言う態度が「とても気持ちいい人。この人好きだな」と思ったのだという。
◆田部井さんに強く魅了された北村さんは、数日後彼女の自宅を訪ねてまたもびっくり。彼女には2歳の娘がいたのだ。にもかかわらず遠征するという強い意志にあらためてうたれた。田部井さんとの話は大いに盛り上がり、ほんの30分ほど話す予定が3時間ほど話し込んでしまった。エベレストへの想いを抑えきれなくなった北村さんは、その数日後に、田部井さんに「私もエベレストに連れていってください」と電話で告げたのであった。電話越しに、田部井さんが“絶句”した空気を感じた。
◆登山歴の浅い北村さんが隊に参加することへ懸念を示す隊員もいる中、北村さんに可能性を見出した田部井さんによって、まずはサポートという形で隊に加わることになった。やがて、彼女の登山経験と体力、そして何より「やりたい」という熱意が認められ、正式に「日本女性エベレスト登山隊」のメンバーに加わることになる。
◆1975年の春、女子隊総勢15人のメンバーはネパールのカトマンズを経て、ベースキャンプへと向かった。カトマンズから途中の村までは軽飛行機で向かう隊が多いものの、女子登山隊は約1か月かけて徒歩で向かった。その意図は、体力作りと高度順応。時間をかけて体を高度に慣れさせたことが功を奏し、隊員たちのほとんどは高山病にならずにすんだ。
◆北村さんは、キャラバン途中、標高4000mから、経費節減のために一気に5350mのベースキャンプを目指す先遣隊に指名される。地元で雇った、文字も読めない人も多い500余人のポーターを率い、到着地ではその賃金を払うという大役。わずかな賃金で一人当たり30キロの荷を背負う彼らの中には、赤ん坊連れの母親や10代半ばの少年少女もいた。社会人になりたての北村さんにとっては世界のリアルを突き付けられる経験でもあった。
◆5月16日正午過ぎ、田部井さんがエベレストに登頂。この登山隊の成功は、日本における女性登山者の存在を世に知らしめる転機となった。「女性が登山をする」ということが、もはや例外でも特別でもなく、「ステキなこと」として認識され始めた最初の一歩だったのである。
◆エベレスト登山を機に、北村さんは「女性と登山」というテーマに強い関心を抱くようになった。記者であるという自らの立場を活かし、あるいは必死で休暇を取得し世界中へ登山に出かけるようになる。田部井さんと北村さんの隊が次なるターゲットとして選んだのはチベットだった。エベレスト登山の功績が評価されて中国から特例的に登山許可がおり、1981年、幻の山と言われていた「シシャパンマ」へ女性9人で挑戦することになった。ここでも田部井さんが2つ目の8000メートル峰に登頂を果たした。
◆大勢で登る登山方法(極地法)に疑問を感じ始めた北村さんは田部井さんと2人だけで1983年にインド山旅に出ることになる。旅は少人数に限るということと、資金を寄付に頼るのではなく自分たちで工面するという新しい方法を試したのだ。
◆すでにキリマンジャロ、マッキンリーにも登頂していた2人にとって、このころから「七大陸制覇」が視野に入り始める。そして同時期、登山界にも「フェミニズム」の潮流がやってきていた。「女性が女性の力で山に登る」ということが1つのムーブメントになりつつあり、それを世界中の山々を登る中で肌で感じてきた。女性たちの登山のスタイルについても、国籍によって違いがあり、アジアでは女同士で登るパターンが多いが、欧米では父娘や夫婦など男女ペアで組むことが多い、そんなことにも気がついてきた。男女混成チームにおいても、性別で役割を分けずに、女性も男顔負けの力強い活躍を見せる場面を数多く目にしてきた。
◆1991年には、湾岸戦争に揺れる世界情勢を尻目に南極のビンソンマシフへ、そして翌1992年に西部ニューギニアへ行き、カルステン・ピラミッドに。いろいろなトラブルの末結果的には田部井さんが登頂している。七大陸制覇を達成した後は、誰かが決めた目標を達成するのではなく、自分たちで決めた目標を追いかけよう、ということになった。そこで目標に定めたのは、ヨーロッパの「アイガー」「マッターホルン」「グランドジョラス」だった。グランドジョラスは頂上直下の崩落事故で目指したシーズンは通行不可で登れなかったが、1995年には田部井さんと北村さんの年齢を合わせて「101歳の記念」をアイガー登頂時に祝うことができた。
◆北村さんは今、自らが生まれる前の時代の女性たちがどのように山に登ってきたか、ということを文献や聞き込み調査をしながら調べているのだという。昔のことを聞くために訪ねていくと、「つい先日亡くなった」「今はもう認知症になってしまっている」「調べて訪ねて行った住所は空き家だった」などというケースが多く、直接本人から話を聞き出すことはそう簡単ではない。今回、北村さんが調べた女性登山史の一部を紹介していただいた。
◆大正年間に入ってからは山に登る女性の写真も少しずつ残されるようになってきたが、その中の服装を見ていくだけでも、日本人女性が山に登るスタイルに変化があることがわかる。1919年の女子高等師範学校付属校の生徒たちは当時一般的だった「茣蓙」を雨具がわりに着ているし、1929年には、ある婦人の、鹿島槍下の冷池のテントに着物姿でたたずむ写真も残されている。大正時代の女学生の学校登山は、袴にわらじを履いて登るのが普通だったようだ。それにしても、大正~昭和初期に山に登る女性たちというのは、どんな身分だったのだろうか。
◆1957年には、川森佐智子さんという方が日本人女性として初めてマッターホルンやモンブランに登ったことが記録に残っている。彼女は8か月間も単身で欧州滞在しこの山行を成し遂げたというが、気になるのはその財源だ。実は彼女の夫は名だたる軍備品の発明者であり、戦後は造船会社の重役を務めていたとのことで、かなり裕福だったであろうと想像できる。彼女の死後田部井さんが彼女の追悼文集に一文を寄せているが、「御殿のようなお屋敷だった」とそっちの方に感心した様子。川森佐智子さんのように、当時の日本で先鋭的な登山をやっていた女性のほとんどは資産家であり、名家のお嬢様で高学歴というケースが多いようである。
◆例外もある。中村テルさんという方で北村さん自身もお会いしたことがあり、とびきりの美人で華やかなマダムだったという。元々は資産家の生まれであったものの、実家の没落から若くして自らで家計を支えなければならなくなったという経緯がある。英語を学び、18歳の時点で一般サラリーマンの3倍は稼いでいた彼女は当時としては珍しい「自分で稼いで山に登る女」だった。戦後も通訳として活躍し、日本で初めての女性山岳会であるYWCA山岳会を作ったという功績も残している。
◆今でこそ女性にも登山への門戸が開かれているが、そうではなかった100年近くも前に、これほど多くの女性が登山をしていたということに驚かされた。こうして多くの事例を並べてみると昔の女性たちは軽やかに多くの偉業を成し遂げているかのように思えるが、その無謀とも言える大きな挑戦を前にして、どれだけの人が「女性にはそんなのは無理」と言われてきたのだろうかと想像する。
◆ほぼ男女平等の世となった今、むしろ「女性だから」ということが言い訳にできない時代になった。しかし、今回、自分の中で「女性だから無理」と無意識に決めつけていることはないだろうか、と改めて振り返ってみた。
◆私事であるが筆者は先日、バイク(大型二輪)の免許を取得した。私は女性の中でもかなり小柄であるため、周りから「さすがに無理なんじゃないの」と言われたものの、絶対に諦めないという気合いでなんとか卒業検定合格まで至った。高校生のときからずっとバイクに乗りたくて、でも自分には無理だと決めつけていた10年以上の時間よりも、諦めないと決めた3か月で意外にもあっさりと乗り越えられてしまうのは拍子抜けだった。エベレストに比べて非常にスケールが小さい話で恐縮なのだが、登山をし続けてきた昔の女性たちの自分を信じる力の強さは半端ではないのだろうと想像している。
◆今回の報告会では、北村さんや、北村さんが生まれる以前の女性たちも、今以上に女性に自由がない時代に、自分たちがやりたいことをやってきていたことに、とても勇気づけられた。
◆今年の10月、田部井さんをモデルとした劇映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』(主演・吉永小百合)が公開される。それに合わせて、北村さんの著書であり、田部井さんとの山行の詳細を綴った作品『ピッケルと口紅』の文庫化も予定されているそうだ。この秋は、映画や書籍とともに田部井さんと北村さんが世界中で重ねてきた山行の数々に思いを馳せてみたい。[貴家(さすが)蓉子]

イラスト 長野亮之介
■自分の山登りは「やわ」なものなので、たまたまエベレスト隊とか田部井淳子さんとかのかかわりで人様にお話する立場になったのは面はゆいことでした。が、たしかに50年という年月を経てみると、自分自身の「滑って転んで」にも「歴史」が透けて見えるもんですね。戦後の経済成長に従って、ズック靴はキャラバンになり、革靴になり、コフラックの二重靴に。行動食だって、乾パン・魚肉ソーセージじゃなくて、「車で立ち寄る」「山麓のコンビニで」調達する、大福や作り立てのおにぎりに。レトルトのかば焼きもあるぞ。行動としてはだんだん軟弱化。行く先は広域化、これって幸せなのか、といぶかりながら、年齢のせいもあってもう宿命甘受です。こうして楽をしながらますます「昔はよかった」なんていうバーさんになるわけね。順調順調。
◆ところで、報告中でも少し触れましたが、日本の女性登山には「女性同士で」が結構多い。欧米のほとんど「カップルで」に比べると、「これはなぜ?」と思わずにいられません。逆に言うと日本の男性は「男同士」で登る機会が欧米より多いはず。つまり基本的に「男女別々文化」。これって、国会の党役員が背広男ばっかりだったり、地域の合唱団で女声は大勢、男声が足りない、なんて日本の現象にも通じる気がします。
◆こう見ると、「女性登山隊」というキーワード、案外いろんなものを引きずっているのかも。「どこへ登った」だけでなく、「女性登山隊」が成り立っている社会についてもあれこれ詮索してみたい気分です。
◆貴家さん、大型二輪の免許取得とはすばらしい! バイクは新しい世界につれていってくれる乗り物です。私は30代になってから400ccまでの中型二輪の免許を取って、行動半径を広げることができました。今思えば私こそ「女性だから、30代だから」と、自己規制して中型で満足していた気配があります。貴家さんの勇気に脱帽! でもくれぐれも事故には気を付けてくださいね。挑戦するということは、同時に「より慎重になる」ことを伴うものです。[北村節子]
■女性のエベレスト初登頂から50年、にちなんで北村節子さんがご登場と聞いて、これは是非に、と久しぶりに報告会に駆けつけました。期待に違わず心躍るエキサイティングなお話でした。思えば地平線に顔をだすのはほぼ半年ぶりのこと。この間、学部長を務めていた現場で発生した大事件の処理に追われ、この四月からは大学の経営陣にとりこまれてしまって学生の相手をする時間も自分の研究テーマに取り組む時間もすっかりなくなってしまっていたのでした。
◆その代わりといってはなんですが、ゼミの卒論生だった杉田友華さんが継続的に地平線に顔をだして通信にも記事を寄せてくれていましたので、私の欠席を埋め合わせてくれたようで嬉しく思っています。その彼女も今春から北の大学院に進学して研究ライフをエンジョイしてくれているようです。学生たちを地平線に連れてくるようになってはや10年。この間、前任の北大とまったく異なる学生気質に戸惑いながらも試行錯誤しながらやってきましたが、荻田泰永氏の北極ウォークに参加したゼミ生もいましたし、本格的に雪氷圏のフィールドワーク研究の世界に飛び込んでいった杉田さんのような若者も育てることができました。
◆法政大学という大規模私大に移ったときに「もう極域研究の最前線にでることはないだろうなぁ」と覚悟はしていました。それでも目標は高く掲げておきたいと、1)自分のゼミ生を冒険・探検の世界に引き込むこと、2)法政大学在職中に南極に行くこと、3)一流の学術誌に論文を載せること、の三つの目標を掲げてやってきたのでした。1)は地平線の皆さんにすっかりお世話になったおかげで実現できましたし、2)もコロナ禍の厳しい中で越冬隊長として最後のおつとめを果たすことができました。残る3)もあとちょっとで国際誌に論文が受理されるところまできています。ということで、これで三つの目標も果たせたことですし、研究・教育の最前線からはいったん退いてもいいかなと思うようになりました。学部長になったのはまったくの晴天の霹靂でしたけれど、南極とはまた違う組織運営を実践したことで未体験ゾーンの刺激をうけたこともあり、いま与えられている立場でも大学経営という新たな挑戦領域にむけてなにかしてみたいな、と思うようにもなったところです。
◆四月からは、担当する多摩キャンパスに加えて九段にある大学法人本部と、二つの勤務地を往復することになりました。朝イチで江戸前老中御用部屋へ出仕して秘書さんと各部署への指示の打ち合わせ、午後は領地国元へとって返して教職員との会議、というような日々です。日本のど真ん中が勤務地になるなんて、自分が思う自分らしさからしたら最もありえないはずだった展開で、まるで参勤交代大名のような気分です。ただ、江戸城のすぐ脇にオフィスがあるので、報告会が開催される早稲田の会場に来るのは前よりも楽になりました。日本山岳会(JAC)のルームも市ヶ谷の近所ですので、これからなにかと交流が進みそうです。
◆JACと言えば、北村さんのお話を聞いていて、大学山岳部での女性部員の活躍の歴史ということにも思いがよぎりました。昨年末に法政大学山岳部創立100周年記念祝賀会におよばれしたときにお土産に100周年記念誌をもたされたのですが、その編集後記にとても共感したことを思い出しました。そこには《当初この記念誌は「担い手不足のため作成しない—」。そのような決定がなされかけた。そこで「私たちがやります」と声を上げてしまったのが私だ》と書いてあったのです。この「私」こそが現在JACの事務局員をされている豊泉さんで、その昔は男女分かれて活動していたという法政大学山岳部『女子部』の流れを引く若手ホープだったのでした。
◆カチカチと自分の頭の中でいろんな事象がくっつき合う瞬間を体験して、北村さんが手がけておられるという「女性の登山史」ができあがってくるのがとても楽しみになりました。特にお話を伺っていて面白かったのが、大正デモクラシー前後の富裕層の「お嬢」が先駆的なアルピニズムを実践していたという話。「チェアーにザックは……」と叱責されたのを茶化して「ロックにザックは……」とふざけ合うお二人の光景も目に見えるようで、ほんとうに面白かったです。
◆中村テル女史はもともとは夕張の出ですが、実は、遠く北の地でもインテリ・富裕層が山で幅をきかせてきた時代はありました(男の話ですけど)。学生登山界で槇有恒と共にリーダー格として活躍した板倉勝宣らの時代などがそうです。未開の蝦夷地に分け入っていくにはそれなりの時間とお金に余裕がないとできなかったのですからそれも当然とうなずけます。ただ本州とちょっと様相が違うのは「都落ちした富裕層/開拓地の名士」という雰囲気もあったことです。私の世代は、そのころの雰囲気をまだ持っていた先達とかろうじてお付き合いできた時代でした。
◆まだ未踏で心残りのルートがあるのでサポートしてほしい、と老教授から頼まれてガイド役を引き受け、下山した後に「晩ご飯をご馳走するから」と、山の格好そのままで札幌市内のフランス料理レストランに連れて行かれたことなどを思い出しました。その一方で、坂本竜馬の血筋を引く「原野の農民画家」としても知られる坂本直行氏らの活躍もありました。なかなか女性の活躍までは私の浅学では引きだせないですが、そのような視点でも北の登山史を見つめ直してみたいと思うようになりました。
◆さて、私が取り込まれてしまった大学経営陣のトップは、田中優子氏に続いて本学二人目となる女性の総長でもあります。この総長のもとで大学経営の舵切りをしている日々の合間を見て、今後もちょくちょく報告会には顔をだしたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。[法政大学・澤柿教伸 いまでは副学長!=E]
■中二で行った木曽御岳で「山っていいな」と感動していた可憐な少女(主人公)が、新聞社入社を経て田部井淳子さんと運命的に出会い、瞬く間に逞しい女性へと成長してゆく……。紙芝居形式で駆け抜けた報告会は壮大かつスピーディーで、まさに高低差8000m超えのジェットコースターのようでありました。
◆当時の新聞社に漂う男社会気質は如何様だったのか? エベレスト初登頂を目指す女子隊に流れていた空気感は? 女性特有の長所も短所も深く理解しながら、北村さんが度重なる現場で体得してきた「女性ならではの底力」というものが男性の僕にもひしと伝わってきました。
◆好き嫌いや人生の価値基準に芯が通っている北村さんだからこそ、運命の大波が来ても咄嗟の判断に迷いのない場面が多々あり、その感性と逞しさにも驚嘆しました。過酷な現場の連続なのに、ご本人は飄々と楽しそうに乗り越えてきている感じが凄いんです!
◆女子隊エベレスト初登頂達成後に、悩める田部井さんに寄り添う北村さん。人生いざというときにはこれまで共に歩んできた信頼がお互いを支え合うのだとしみじみ……。隊の登山の難しさを痛感した後に、すべてから解放されるようにお2人で(あるいは3人で)、七大陸制覇が視野に入るほどの勢いで登山に没入し、純粋に山々と戯れている姿が僕の目には最も幸せな瞬間に映りました。北村さんにとって、山とは人生の困難を学び、人生を心の底から楽しむ現場だったのですね。
◆ これほど壮大なストーリーを、頭脳明晰で鋭い感性を持ちながらも、時にユーモラスでチャーミングにまとめ上げるその見事な語りぶり。スパッと終わる歯切れの良さたるや名人級の報告会でした。ジェットコースターが終わり、「もっとずっと聞いていたいな……」との思いに包まれております。まだまだ興味深いお話の引き出しがたくさんありそうな北村さん。記者時代の取材よもやま話等も含めまして、別の機会がありましたらまたお聞かせくださいね![車谷建太]
■なんて気持ちよい風がふいたことでしょう! 北村節子さん、田部井淳子さんに、8000メートル級の山々に連れていってもらったような2時間半でした。そして、面白いお話しがいっぱいでびっくり。
◆山の世界にも社交界があるということにハッとしましたが、写真のなかの田部井さんは確かにどんどんおしゃれになってゆく。チーム登山で、誰が頂上へアタックするのか?生々しい攻防戦も、北村さんにかかると不思議と軽やか。その人が登る理由があるのだと納得できてしまう。チベットの秘境もパプアニューギニアも、そうか、山は背景であり、北村さんの目が活写しているのは「その土地のひと」と「ともに登るひと」なんですね。
◆後半の、日本女性の登山史もとっても興味深い。上流の奥さま、努力家の職業婦人、なぜか料理研究家が多いのよねえと人物描写が際だって面白いうえに、目を引いたのは山に登るときの皆様の服装。着物に袴をつけた勇姿あり(ちょっとモンペ風)、ゴザを体に巻き付けるという実に素晴らしいアイデアも! そうまでしても、山に登りたい、高い所に立ってみたい、世界を見下ろしてみたいという女性たちがいたことに、大いに励まされた2時間半でした。[佐藤安紀子]
■女性が登山を始めたのはいつからか。どのような登山だったのかという登山史を意識したことがありませんでした。歴史としてみたときに社会での女性の立場から登山の在り方も今と違っていたはず。着物で登山をしていた時代、どんな人がどんな風に!? この史実が本になるのが楽しみです。
◆また、北村さん自身の学生時代の登山経験から田部井淳子さんとの登山に至るお話の背景には「女性」の社会的な立場も常について回る。近代女性登山史の生の声が聞ける機会に参加でき無理してでも行ってよかったです。北村さんの登山愛と社会背景、女性だけの登山の裏話をもっと聞きたかった。今、当たり前のように育休が取れるのも先輩女性の皆さんが奮闘してきてくれたお陰ですね。
◆今回子連れで参加しましたが、報告会中に子どもが泣いても気にしないでと声をかけてもらい、とても気持ちが楽になりました。ありがとうございます。子育てが落ち着いたら北村さんお勧めの穂高へ行きたいです![うめこと、日置梓]

イラスト ねこ
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです。編集長が期待しているのは皆さんが通信に「参加」してくれることです(メールアドレス、住所は最終ページにあります)。
恩田真砂美(10000円) 吉竹俊之(6000円 2023〜25年3年分通信費。宜しくお願い致します) 大浦佳代(5000円) 猪熊隆之(10000円) 山川陽一(30000円) 猪股幸雄 小島あずさ(10000円 いつも通信を送っていただきありがとうございます。通信費をずっとお送りしていなくてすみませんでした) 澤柿教伸 小林進一(10000円 5年分) 藤木安子 横山喜久 神長幹雄(10000円 久しぶりに地平線報告会に顔を出した。北村節子さんはここ数年、「田部井淳子のいた時代」をテーマに、女性たちの登山を丹念に、かつ精力的に取材を続けている。なんといっても今年は田部井さんがエベレストに女性初登頂して50年の記念すべき年。少し編集のお手伝いをさせていただいているが、そういえば私も、山岳図書の編集者になって50年を迎えてしまった) 山川佑司
■おととしの冬至は、宮古島の小さな集落ですごした。20戸ほどの班ごとに、豚肉を血と一緒に煮る「ツーキィワー」を大鍋いっぱいつくって新しい年を祝う伝統行事を見るためだった。宿に泊まり合わせた70歳ぐらいの女性は、茨城から毎年来ているそうで、エプロン持参でお手伝いをしていた。民俗学の研究者だそうで、最近は韓国のシャーマンの研究をしていると、翌朝の食堂で聞いた。モンゴルのシャーマン研究のこともチラリと出て、「へえー、モンゴルにもシャーマンがいるのか」と思ったのだった。
◆2月の地平線通信で「第1回日本モンゴル映画祭」のことを知り、10年ぶりぐらいに映画館に足を運んだ。どの作品でもいいからモンゴルの風景を見たいと思ったのだ。じつは2014年7月、江本さんに誘っていただき、モンゴルを旅した。ウランバートルから車で1日かけて草原に行き、観光向けではない本物のゲルに泊まり、遊牧民の人たちにヒツジを分けてもらって(殺してもらって)食べるという、贅沢きわまりない一生モノの体験だった(改めて、江本さんには心から感謝します)。
◆映画祭で観たのは、シャーマンの男子高校生が主人公の「シティ・オブ・ウインド」。誘った友人の都合にたまたま上映時間が合ったためだが、宮古の宿の雑談を思い出し興味深かった。だが、それ以上に風景が懐かしかった。舞台はウランバートル郊外の、草原を離れた遊牧民が居住している区域で、ゆるやかな丘の斜面にゲルがびっしり立ち並ぶ(江本さん、間違っていたらすいません)。モンゴル旅の最終日、草原のくらしとはまた別の現代モンゴルの顔を見るために訪れたのだった。映画そのものもすばらしく、そのあと行ったモリンホール屋の茹でヒツジも最高だった。
◆宮古島に話は戻る。わたしは2006年から、狩俣という小さな集落に通っている。ここには沖縄の伝統漁法「追い込み漁」の集団が残っている。素潜りでサンゴ礁の多種多様な魚を網に追い込んでとるのだが、人智をつくしたまさに「海の狩り」。初めての同行取材ですっかり心をつかまれた。親方は87歳の今も現役で、お聞きする昔語りがまた、とてつもなくおもしろい。ところが最近になって、親方や長老漁師のお話が、若い世代にはあまり伝わっていないことに気づいてハッとした。詳しいお話を聞き、記録にとっているのはわたしだけかもしれない。親方は、文字通り裸ひとつでサンゴ礁の海で生きてきた最後の世代だ。潮汐のリズムに同調し、サンゴ礁の生態系に溶け込むような生き方を伝える責任があるのではないか。勝手な思い込みだが、親方への恩返しのつもりで本にしようと思った。
◆ところが、1年がかりで原稿を書き上げたものの壁にぶち当たった。「出版不況」という分厚く高い壁だ。そもそもウェブサイトに「原稿持ち込みお断り」と明記している出版社が多い。また「お断り」の明記はなくとも、何度メールを送ってもナシのつぶてという出版社も(たとえば山溪とか)。つきあいのある2社にも担当編集者を頼って打診したが、1社は「1000部買い取り」が条件だという。ところが、初めてコンタクトした地方の小出版社から「残すべき価値がある。出しましょう」とお返事メールが。小躍りして電話すると、印刷費は著者負担、300冊買い取り、印税の支払いは1000部まではナシだという。プロのはしくれとして、1円の対価もなく仕事をしていいのか。迷いに迷ったものの、親方は高齢なのであまりぐずぐずもしていられず、この出版社に委ねる決断をした。というわけで、秋ごろには本が出る予定です。[大浦佳代]
■相変わらず、目が回るような忙しさの中で過ごしています。明日6月12日からは北海道の利尻、礼文へ「空見ハイキング」に行ってきます。空見ハイキングとは、山の中で天気やリスクを回避することを学び、空を眺めながら、花を愛でながら山を楽しむツアーです。雲は、目に見えない空気の状態(気持ち)を教えてくれる、空気の翻訳者のような存在です。そんな雲の見方がわかると楽しくなってきます。参加者にもそうした気持ちを味わっていただきたくて、14年前に旅行会社で始めた企画です。ツアーだけでなく、「ヤマテン」でも山頂で観天望気という雲の見方を学んでいただく講座を実施しています。是非、地平線会議の皆様にもご参加いただき、雲談義をしたいです!
◆山の楽しみ方は歳とともに変わってきました。若いころは、充実感や自分の限界を知りたい、アドレナリンが出る登攀がしたい、という気持ちが強かったですが、今は空や花、木、鳥を愛でたい、山を通じて色々な人と出会いたい、そして出会った皆様と語り合いたい、という気持ちが強くなっています。この地平線通信を読むたびに、寄稿された皆様と深い絆で結ばれているような気がしています。勝手ながら、「ファイト!」と心の中で応援し、いつかお会いできることを楽しみにしています。こんなオジサンですが、今後ともよろしくお願いします。[猪熊隆之 山岳気象予報士]

■エモノトモシャさま。超まのびのメールで申し訳ありません。3月4月と体調を崩したまま5月に小康状態……6月に入ってまた後退。今日はまあまあです。
◆聴きました『山カフェ』。わたしの好きな番組なので、その前の週から楽しみにしてました。北村節子さん、なんと軽やかで明るく前向きな方なのでしょう! エモノトモシャさんは出会った途端、ビビビッときてしまったに違いありません。番組を聴きながら、色々と思い出しました。女子隊エヴェレスト登頂のあのころは、わたしにとっても青春真っ盛り。ソル=クンブの南、ジャサ(虹の郷)という名のチベット人難民キャンプで過ごしていました。春のソルはロクタというジンチョウゲ科の植物が芳しく全山を覆い尽くすほど林立していました。ネパール紙の原料になるものです(聞いた話では、このロクタは日本へ輸出され土佐紙の原料と合わせて日本銀行の紙幣になるのだとか)。
◆キャンプのチベット人やバザールのシェルパたちはみな、「日本人の女子はみなエヴェレストに登っているのに、なぜお前は行かないのか?」と言ってました。カトマンドゥに下山後、大使館からのお知らせもあって、登頂成功のレセプションパーティへ顔を出しました。知らない人ばかりで、すぐに帰ってきてしまいましたが、今も目に鮮やかに残っている風景があります。着物姿の細身の女性が扇子をパタパタしながら、アン・ツェリンのそばに立っていた……。今思うと、この女性が北村さんではなかったろうかと。
◆ダラダラ長くなりました。一つのラジオ番組から、一気に青春時代のネパールへ戻ることができました。お二人に感謝します。[貞兼綾子 チベット研究者 5月17日朝8時から北村節子氏が出演したNHKラジオの『山カフェ』を聴いて。なお、着物姿の女性は隊のドクターでした]
■“日本にも羊飼いがいます”と聞いても、たいていの日本人は、「えっ!ほんとですか? なんだかアルプスの少女みたいで楽しそう、羨ましい」と思うでしょう。はい、主に北海道ですが日本にも羊飼いはいます。日本全体でも羊は2万頭強しかいません。だからニュージーランドのように牧場に何千頭というわけではなく何百頭です。でも日本の羊飼いは日本の政府から何の援助も得ないで自主自立、自分で育てた羊を、自分で営業して、肉を販売しています。
◆そんな春の北海道に先日行ってきました。牧場は1月の子羊出産にはじまり、4月の毛刈り。そんな繁忙期も一段落の5月中旬、羊飼いの集まる「北海道めん羊協議会総会」に原毛屋の私は2019年に発足したJapan Wool Project(JWP)の紹介をしに行きました。私はJWPの羊毛仕入れ担当だからです。
◆さて今までは、ほとんどの牧場が毛刈りした羊毛は放置、牧場の片隅でたい肥にされていました。だから「買い取って糸にしますよ」と呼びかけたら皆喜んで送ってくれました。でも、でも、でもです……。ゴミとウンコは取ってくださいね、という説明がなかなか伝わらない。愛知県一宮の工場で洗う前に、そのゴミ取りにかかった手間がハンパない。足を運んでそのことを羊飼いに説明、動画やパンフレットを作り、ワークショップしながら説明……というのがここ数年です。
◆ですから今年、北海道中の羊飼いが集まる総会で、羊毛の話をしませんかと声がかかったので、私は勇んで行きました。当日は私は力いっぱいのおしゃれをして登壇。ラムスキンで作った黒のライダースに、流行りの黒のチュールふわふわのスカート、髪もばっちり半分緑に染め、攻めたファッションでいきました。そして「ゴミを取ったきれいな毛を送ってください! その毛でツイードを作って、カッコよく羊飼いしましょう」と、40分間おしゃれ心をそそるスライドレクチャーをしました。
◆するとどうでしょう! その羊飼いの中には、ダークスーツにハットの紳士がいます、ちょんまげ金髪アメカジ系の羊飼い、黒の革ジャンのレジェンド羊飼いもいます。おもいのほか羊飼いは潜在的におしゃれでした。で!なんとそのノリで“北海道羊飼いおしゃれ番長チーム”が結成されました! やっぱり理屈よりもおしゃれ心♡ いつもは土にまみれて羊の世話をしている羊飼いも、たまには気分を変えておしゃれがしたい。次の総会は「羊のドレスコードでおこし下さい」と案内状に書き添えようという話で盛り上がりました。
◆どんなに厳しい現場の毎日でも、おしゃれ心と楽しむことは忘れない♡ 皆様もたまには「ドレスコード」いかがですか? 暮らしが楽しくなることうけあいです![羊の原毛屋 本出ますみ]

■地平線通信553号の発送作業は5月21日、無事終了しました。4ページにわたる「西興部村報告」を含め18ページになりました。以下の11人が汗をかいてくれました。ありがとうございました。これだけの人が馳せ参じてくれるので作業は迅速に進みます。
車谷建太 中畑朋子 伊藤里香 高世泉 長岡のり子 中嶋敦子 渡辺京子 白根全 久島弘 杉山貴章 江本嘉伸
■江本さんお久しぶりです。たまには近況報告しなさい、というお叱りを受けて筆をとりました。江本さんには20代のころからこうやってずーっと気にかけてもらい続けて今や50代も後半戦……。途中、ヒマラヤ遠征とか犬ぞりとか何度か報告者になれって言われたことがあったけど、自信なくて逃げ続けて結局どれも報告できるほどの内容がないままここまできちゃいました。すみません。
◆自分の冒険話ではないのですが、6月7、8日と一泊二日で兵庫県豊岡市に行ってきました。豊岡市には冒険家植村直己さんの郷里があって、毎年市が主催する植村直己冒険賞の授賞式が行われています。29回目の今年は洞窟探検家の吉田勝次さんが受賞されました。700人入るという日高文化体育館は満席で、地元の小中学生を中心に老若男女が会場に集い、吉田さんのお話に聞き入りました。
◆吉田さんは20代後半から未踏の洞窟探検に情熱をかけ続けて、今回の賞は2024年に行ったラオスの未踏洞窟の探査に対しての受賞。私が、吉田さんを初めて知ったのは『洞窟ばか』という本が出版された2017年で、神楽坂に吉田さんと角幡唯介さんの対談を聞きに行ったのがきっかけでした。「人としてのスケールが違う……」というのがはじめの印象で、今回の話を聞いてさらにその思いを強くしました。「洞窟探検が心底大好き」。そんな雰囲気に講演後の子どもたち大人たちの質問も絶え間なく、もちろん小中学生たちが一番盛り上がったのは「うんち、おしっこ」ネタでしたが……。
◆あるお母さんが子どもの教育について質問すると「なんでもやりたいことやらせて、飽きたらすぐやめて、好きなことが見つかるまで片っ端からやればいい」。すぐ飽きるのはダメ、ものになるまでやり続けるという考え方があるけれど、吉田さんのアドバイスは、飽きたらやめていい。好きじゃなければすぐやめればいい。好きなことが見つかるまで、色々やればいい。それは本人が心から愛する「洞窟探検」と出会う過程でもあったからなのかもしれないなと想像しつつ、そう断言できる吉田さんはやっぱりすごい探検家だなと思ったのでした。[恩田真砂美]
■1978年にカナダ・マッケンジー川をブリティッシュコロンビア州のFort St. John(フォート・セント・ジョン)近郊の橋から河口のデルタにある町Inuvik(イヌビック)まで2か月かけて単独で下った。大学を来年卒業する、そこで探検部での活動の集大成として、水面から40センチの視点の旅はこれで最後のつもりだった。
◆マッケンジー川は本流の上流にグレートスレーブ湖があり、そこに流れ込むスレーブ川そしてその支流ピース川の源流から4,241kmの北米2番目の長さを誇る大河である。その川を下りながらそこで川に向いて生活する人々との交流が、この水系をもっと知りたいと思った要因であった。もう一つ、自分の気持ちを高揚させたのは下流の部落で会った一人の地元民と2回目の旅で川の真ん中で再会したとき、“マッケンジー川に取りつかれたな、またこの川に戻ってきてこの川に骨をうずめるだろう”という言葉だった。
◆しかし4回目の2018年の旅は、40年を経た同じルートの旅だったのに、悲しくも寂しい現実を思い知る旅となった。時は人の営みをまったく変えてしまったのである。流域はインフラが整備され、生業もそのインフラ整備に取って代わり、子どもたちは室内の大きな画面でオンラインゲームに夢中だった。
◆そこでマッケンジー水系を隔てた、分水嶺の向こう側のバーレンズといわれる無人地帯の川をのぞき見したくなった。本来ならば以前の旅の通過点から線で繋げてみたかったが、歳という現実が無理な旅を思いとどまらすことになった。そこで分水嶺を隔てた湖ラック・デ・グラスからコッパーマイン川(845km)の旅を思い立ったのだ。マッケンジー川ではないので骨をうずめないで無事に帰ってくる予定です。日本を発つのは7月3日。報告会には帰国までお伺いすることはないと思いますのでお伝えいたします。[河村安彦]
◆夜、文芸部提出の作品を兄さんに批評してもらった。親切にしてもらった。兄貴はこういうふうでなくてはいけない。文学の話は大好きだ。非常に面白い。「作家?ダメダヨ」(シュウイ)。自分は文学に関して見栄があるだろうか? わからない。学校で本を読んでいる時は少なくともないな。そうだ、90%はないな。あとの10%?未決。いや、100%ない、絶対に。
◆ところで自分は本当に青びょうたんになりはしないかな、少し外へ出よう。学校では——仕方ないね。夜、この室に1人起きてると何か書きよい。書いていると他の勉強がイヤになってしまう。学校では目を前に向けていよう。横を見てはいけない。Tの様子をよくみていこう。明日は文芸部集会か、嬉しいな。今何時だろう。11時50分!! 寝よう!!
◆今、本当にヒッソリしている。今日、文芸部の集会があった。非常に面白かった。テニス部を見ると思わずほほえまずにいられない——。勉強か。——もう少し時間の使い方を工夫しよう。フトンを干したって? 気持ちいいだろうな。寝よう。
◆日記にはその日にあった出来事、その日に起こった心の変化を書くのであるが後者の方を全くその通り書く人は偉いと自分は心から思う。そして、日記を書いている人でそれが書けない人は複雑な心の持ち主と想像する。せいぜいその通りに書ける人につとめよう。1に勉強、2に身体、3に勉強、四に遊び
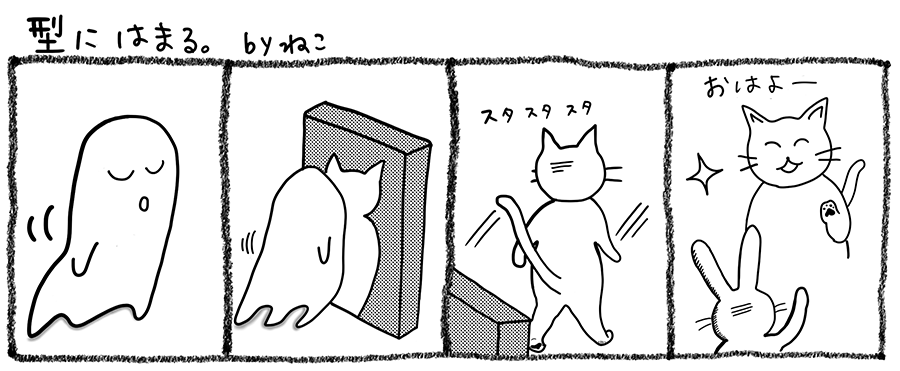
《画像をクリックすると拡大表示します》
■5月の連休が明けてから、谷あいの丸太小屋に住み始めた。ここも道内数あるちえん荘のうちの一つ。「ちえん荘は、チェーン展開しているのです。フランチャイズです」という創業当初からのお決まりのギャグはさておき。この谷には林道沿いに数軒の人家があって、その最奥に位置しているのが今の住処。憧れの「最終人家」である。電気と水道はないので、もちろんテレビもウォシュレットもない。別に某有名ドラマを意識した訳ではないが、「夜になったら寝るんです」といった黒板的生活のはじまりである。
◆地元林業会社に期間雇用してもらい、植え付け(植林)の仕事をさせてもらっているため夜更かしはしない。朝4時には起きて、日が落ちる20時21時にはシュラフに潜り込む。新調したばかりの冬用シュラフとテントマットがふかふかで気持ちいい。夜はときどき小動物が屋根裏を走るので、そのたびに大きな声を出して、これからこの小屋を人間の住処とすることを主張する。暗闇で気配を送りあうコミュニケーションにドキドキしながら、またすぐ夢の中へ滑り落ちる。
◆この小屋は長年人が暮らしていなかったせいで、なかなかに荒れていた。私が入居させてもらうより少し前に雨漏りの修繕はされていたけれど、小屋の木部には水漏れの染みがあちこち残り、一部は腐れているところもあった。人が寄りつかなくなれば獣が忍び寄り、屋根裏の断熱材を引っ張りだして遊んだのか、あちこちにグラスウールが飛び散っていた。そのうえ、床のそこかしこに黒っぽい糞もまき散らされていた。
◆旭川近郊のちえん荘から、休暇などに訪れるたびにスコップや箒で糞を除去するのだが、また家を空けて戻ると同じ場所に糞が盛られて、取り除いてのくり返し。人が住んでいないのだからそれは当然で、ここで暮らし始めてからはじめの数日間も、2階のテラスに糞をされる日が続いていた。
◆いつまでも獣の便所清掃員を続けていたくはなかったので、テラスの糞を溜められる場所に、自分のうんこを置いてみた。計3回分のうんこを配置すると、効果はてきめんで、獣に糞をされることは一切なくなった。油断はできないので、私のうんこはしばらくそこへ置いておこうと思っている。それ以外のうんこは家の周囲で。周囲がフキでいっぱいなので、野糞をしない理由はない。ここでも、それとなくテリトリーを主張しながら今度は自分の糞尿をまき散らす。
◆1日8時間近く鍬を振るい、苗木を植えるのは楽ではないが、日がな一日、太陽光を余すところなく全身で浴びることができるのは体に嬉しい。快食快便快眠の生活が、簡単なようで実は大変ありがたいことに気づく。
◆夜の電灯はランプ、といきたいところだが、とりあえず人からもらった乾電池式LEDランタンで明かりをとっている。ひとりの夕食とわずかな時間の読書にはこれで十分。月の電気代は単三電池2本。携帯電話の充電は勤務中に車から。パソコンの電源とWi-Fiはお隣さんに厄介になる。徒歩3分のサイバーカフェ気分でお邪魔させてもらっている。沢沿いの小屋自体が冷涼なので、冷蔵庫は無くても今のところ不都合はない。玄関においたクーラーボックスにいれた食材を2日間で使い切って、都度、仕事帰りに町の農協で補給する。
◆着火装置が壊れたカセットコンロにライターで火をつけて、夕餉の支度。20Lのタンクに沢水を汲むのは2日に1度の5分仕事。周囲の自然環境やご近所さんの御厚意に寄生できているおかげで、水道電気のインフラから切り離されても快適に生活できている。水道はそのうち沢から引きたいと考えるが、今のところ電気はこの家にはなくてもいいなと思う。今後の目標は、物置小屋、馬小屋づくりと水道工事。道内のちえん荘の中で最も開発が遅れたちえん荘、その最前線に私はいる!
◆さて、近況の随想が長くなりましたが、以下は江本さんに報告です。先月札幌で杉田友華さんに会いました。以前、北大探検部の部長を務めていた赤嶺直弥くんが飲み会に連れてきてくれました。なんでも、山小屋に泊まりながらフィールド調査の素養を学ぶ大学院実習が被っていたとかで、知り合ったそうです。地平線通信にお互いの名前が載っていたこともあり、エモカレー、エモ散歩の話題で意気投合したとか。彼女が北大に進学したことは通信で知っていたので、「近々会うかもな」と思っていた矢先、早すぎる遭遇でした。現役探検部員と鍋をつつきながら、地平線会議のことや、彼女が卒論で扱った南極のミッドウインター祭のこと、現役の最近の関心についてなど話は尽きず。「二次会」は後日、道内某所の所有山林「ちえん林」に持ち越されたのでありました。
◆改めて、地平線会議が続いてきたことで紡がれた人の縁に結ばれ、出会いに感謝する春でした。会ってすぐの人と同じ熱量を共有できるのって、他ではあまりないことです。杉田さん、赤嶺くんとは、北海道で地平線報告会があるらしい、という話で、「我々も北海道組としてなにかしようじゃないか」とささやきあっています。年内に一度、一緒に西興部村に行ってみようかなんていう話も。札幌にも、北海道報告会へむけた風が届き始めているようだということ、ここに報告しておきます。[ちえん荘住民 五十嵐宥樹]
★「ちえん荘」とは
ちえん荘は行き過ぎた効率、スピード社会に嫌気がさして「俺たちは遅れて行こう。遅延してなんぼ」と言ったのがはじまり。ヤマ仕事で使う「チェンソー」をかけた表現でもあります。ほかにも「知恵を使って生きる」とか「地縁」という表現も仄めかしていますが自由に解釈してほしい、との立場から平仮名で「ちえん荘」としました。2021年9月発足です。構成員は百姓、樵、大工、牛飼、家具職人、素浪人などです。
■こんにちは。北大探検部5年目の赤嶺直弥です。最近のことをつらつらと話します。話題があちこちに飛ぶかもしれませんが、話し相手になってもらえたら嬉しいです。
◆先月号をお読みの方はご存知かもしれませんが、先日地平線があったからこその偶然の出会いをしました。詳しい経緯は先月号の杉田友華さんの文章を読んでいただきたいのですが、あのとき声をかけて本当によかった。ちょうどその日に探検部のOBOGでちえん民の五十嵐宥樹さんや笠原初菜さんと現役部員数名で鍋会を行うことになっていたので、ぜひ来て欲しいとお誘いしました。五十嵐さんが「いつか会うと思っていたが、こんなに早いとは思わなかった」と言っていたのが印象的です。私もまったく同じ思いで、地平線会議や探検部といったどことなく似た属性を持っている者同士、どこかで会うだろうと予感はしていましたが、ふとしたところでの出会いの糸口を上手く掴めて良かったです。
◆先日、通信の24年12月号で紹介されていた荻田泰永さんの「君はなぜ北極を歩かないのか」を読みました。冒険家である荻田さんの思想・思考はもちろんのこと、素人たちが冒険行に挑戦するということが探検部と共通するところが多く、常に頷きっぱなしの読書となりました。私はこれまで探検部員としては恥ずかしながら、探検家・冒険家の書いた書物をあまり読まずに5年目となってしまいました。年目が上がり、探検のことがある程度わかってきたからこそでもあるとは思いますが、こんなに刺激を受けるならなぜもっと早く読んでこなかったのかと思います。せっかく本や情報が容易に手に入る時代です。これからはもっと積極的に巨人の肩によじ登っていきたいと思います。それにしても読んでいたときから(読み終えた今も)、すぐにでも野へ山へ飛び出したくてたまりません。昨年の2月に少しだけサロベツ原野を歩きました。今年の冬はスキー板を両足につけて、ソリを曳いて、もっとじっくり歩こうと考えています。
◆最近の北大探検部について。ここ数年、新人が増えており嬉しい反面、技術や探検的姿勢・思想の伝達に課題を抱えています。探検部の本当におもしろい核の部分を伝えるためにあの手この手を考える日々です。その一つとして部員有志で今秋に報告会をやろう、それに向けて毎月探検部新聞を作ろうとしています。報告会をやろうとするとそれなりに格好のついた活動をやらねばとなりますし、新聞には部員が思いの丈を書き綴っていく予定です。そんな中で発露する探検的なあれやこれやを後輩たちに感じ取ってほしいなと思います。
◆今年度やりたい探検活動について。札幌には豊平川という大きな川が流れています。その源流を辿っていくと、千歳川・尻別川という別の二つの川も源流を一にしています。ちょうどその分水嶺となる尾根にぽつんと不思議な池を見つけました。流入河川もなく、なぜできたのかもよくわからないこの池、通称「謎池」を踏査したいことが一つ。もう一つ、「北大の最高地点」を踏みたいと考えています。北大は道内各地と和歌山に広大な演習林を持っており、それらすべてを足すと国内の大学の所有する土地の4割にも及ぶそうです。そんな広大な“北大”で一番のピークを攻める。猛烈な藪漕ぎになりそうですが、やってみせます。
◆このどちらも物好きな探検部員しか興味を示さず、社会的に見たら探検的意義は薄いでしょう。世間的に見たら意味がなく、探検部員は価値を見出す。職業探検家はいざ知らず、モラトリアムに漂う大学生が行う“探検活動”というものは、そういったニッチな価値観にこそ「らしさ」がある。そんな独特の姿勢を突き詰めるからこそできる社会への還元というものもあると信じています。北大探検部の伝統的な通過儀礼である“100kmハイク”こそ、その白眉であると思うのですが、この話はまたどこかで。
◆最後になりますが来年の「北海道地平線」について。先月の視察報告を読ませていただき、徐々に構想が出来上がりつつあるのを感じて嬉しくなりました。江本さんがこのために昨年10月に来道され、ちえん荘にいらっしゃったとき、北海道地平線の第一歩に立ち会った者として、会が良いものとなるようかける汗はかきたい。そんな思いでいます。何より地平線の皆々様にお会いできることを楽しみにしています。[北大探検部 赤嶺直弥]
■先月の通信でお伝えしたように、2026年初秋に予定している北海道での地平線会議を成功させるため、地平線会議として久々に1万円カンパを開始しました。報告会参加費(500円)は1979年9月の第1回報告会以来、通信費(1年2000円)はハガキ通信から現在と同じB5サイズに代わった1986年1月から変えることなく今日まで運営してきましたが、もともと財源はゼロなので大きなイベントや出版物の刊行など価値ある企画を実行する際、10年に1回ぐらいですが、特別に「1万円カンパ」をお願いして実行経費にあててきました。地平線会議発足当初には今西錦司先生、宮本常一先生にもカンパを頂いた歴史があります。どうか、趣旨お汲み取りの上、北海道上陸作戦にご協力ください。ご協力いただいたカンパの使途については地平線通信でお知らせします。[江本嘉伸]
賀曽利隆 梶光一 内山邦昭 新垣亜美 高世泉 横山喜久 藤木安子 市岡康子 佐藤安紀子 本所稚佳江 山川陽一 野地耕治 澤柿教伸(2口) 神尾眞智子 村上あつし 櫻井悦子 長谷川昌美 豊田和司 江本嘉伸
ご協力ありがとうございます
★1万円カンパの振り込み口座は以下の通りです。
みずほ銀行四谷支店/普通 2181225/地平線会議/代表世話人 江本嘉伸

■モンゴルで5月14日から3週間つづいた若者たちの抗議デモは、成功に終わった。デモのシュプレヒコール「オクツロホ アマルハン」を直訳すると「辞めるのは簡単」。モンゴルの国会は6月3日、オユンエルデネ首相への信任決議案を否決し、デモが要求した首相退陣がほんとうに実現したのだ。
◆辞任に追いやられた理由は、首相の息子が婚約者の女性にベンツの高級車やシャネルのバッグ、高級リゾートを借り切ってのプロポーズ作戦など、大金を投じていたのがバレたため。20歳すぎの息子が自力で稼げるはずなく、税金が使われたのではと若者たちが疑い、怒り、立ちあがったのだった。
◆デモが始まる前夜、私は別の用事でモンゴルへ到着。デモ開始1日目から9日目まで毎日広場でデモを見て、10日目に日本へ帰国後はFacebook上で動向を見守った。まさに「新世代型」という感じで、清々しかった今回のデモの成功要因を考えてみたい。
◆デモの始まりは、20代の友人グループが会話しているうちに「やってみよう」となったという。そのうちの1人でもっとも目立っていた存在が、24歳の実業家の青年。SNS上で頻繁に発信し、広場で聴衆に語りかけ、「腐った政治を変えたい」という市民の思いを引っ張った彼は、ノーロクという独立系メディアの創設者で、デモ以前から知られた存在だった。というのも、ノーロクは昨年モンゴルで行われた国政選挙の舞台裏を取材し、選挙の不正を暴くドキュメンタリー映画の制作を進めていたのだ。ところがある日、ノーロクのオフィスに警察が来てパソコンやスマホを没収し、映画制作が中断するという奇妙な事件が起きた。それに対して「モンゴルは社会主義国に戻ったのか?」とSNSで若者たちが騒ぎ、ノーロクを応援する人が増えた。
◆今回のデモは主催側も若ければ、参加する側も20代〜30代がほとんど。モンゴル国民の平均年齢が28歳とはいえ、これほど若者が多く参加する政治デモは珍しいのでは? 赤ちゃんを抱いた30代の母親が「いま私が頑張らなければ娘に明るい未来はない」と言いきり、皆勤で参加していたのが印象的だった。
◆デモというと政治色が強くなりがち。しかしこのデモはどの政党とも関係なく、「国をよくしたい」という個々人の思いのみで連帯したという。参加者の中には、第一線で活躍する映画監督や写真家や作家の姿も。デザイナーの青年がおしゃれなビンテージのスーツを着てDJをしたり、人気作家が自由を訴える詩を朗読したりと、デモに行くことがかっこよく見えて、ますます若者を惹きつけた。
◆翌日何が行われるのか、デモのタイムテーブルを主催者が前日にSNSで発表し、つねに内容が明確だった。デモは夕方4時ごろから始まり、シュプレヒコールを唱えて広場を一周したあと、隣接する国会議事堂の前にみんなで座る。思いを訴える市民のスピーチに聞き入る人もいれば、持ってきた新刊小説のページをめくって過ごす人も。日没前の夜8時に国歌をうたい、「ゴミは持ち帰ろう」と呼びかけあって、家へ帰る。
◆若者のデモを妨害するため、誰かから金銭を受け取って派遣されたという年配の集団が、若者たちの前に突如立ちはだかった日もあった。しかし若者たちは感情的にならず、黙々と自分のデモを遂行し、翌日になると年配集団は消えていた。その日参加していた友人に聞いたら、「デモ最中はずっと地面に座っているから、もし腹が立っても手も足も出せないんだよ」と笑っていた。
◆デモ開始21日目の深夜、首相辞任の速報が流れ、モンゴル中が興奮に包まれた。次の日、広場でデモ閉会セレモニーが行われ、民族衣装のデールを着て参加する若者もいた。人口14億人の中国と1.4億人のロシアに挟まれた、わずか350万人しかいないモンゴルで、若者が勇気をもって立ちあがり、国を動かしたのだ。デモに参加した私の友人たちは「手応えと喜びを感じた」と嬉しそうに話し、首相辞任後、軽やかに元の仕事に戻っていった。
■毎月、上の報告会予告イラストで面白い絵と文章を書いてくれる長野亮之介画伯の個展がきのう17日まで阿佐ヶ谷駅近くのカフェ「ひねもすのたり」で開かれた。私は月曜日に慌てて飛び込んだが、小品ながらさまざまな作品が展示されていて画伯の面目躍如という感想である。
◆で、実は、この個展初日には地平線会議にとって歴史的な人、菅井玲子さん(結婚されていまは天野玲子さん)が恩師の三輪主彦とともにあらわれていたことをお伝えしたい。
◆え?誰?という人がほとんどと思うが、実はこの人、「地平線放送」という地平線会議発足当初に存在した電話放送のアナウンサー第1号なのです。当日、三輪さんが携帯で繋いでくれほぼ半世紀ぶりに話しましたが「こんにちは……」という若々しい声で始まるあの女性がいまやお孫さんもいる、と聞いて感無量だった。お元気でね、玲子さん[江本嘉伸]
 |
頭の中は地図だらけ
「僕の旅は紙の地図が命。出会いとコミュニケーションはスマホじゃなく紙の地図から生まれるんです」というのはバイクジャーナリストの賀曽利隆さん(77)。21才でのアフリカ大陸一周以来、オートバイを足に世界中を走り続けています。「10代の頃は狭い日本からとにかく出たくて、横浜港で密航できそうな船を探したこともあったなぁ」 20代は世界一周や六大陸周遊など超貧乏旅行でひたすら世界へ。30代は温泉、峠、林道、札所などテーマを決めて日本の隅々を。以来国内外を股にかけ、今年5月末までの通算走破距離188万3千235キロ。地球50周にあたる200万キロが目前となりました。 元気印の賀曽利さんですが、パリ・ダカールレースでの大怪我や病気、精神的に苦しい時期も。「年代の節目がいつも重圧。でも70代の壁が一番ラクに越えられた。200万キロは80代の玄関口。ワクワクですよ〜」。 今月は世界地図に刻まれた膨大な数の轍と、記憶力を誇る賀曽利さんに、旅の哲学と夢を語って頂きます! |
地平線通信 554号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年6月18日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|