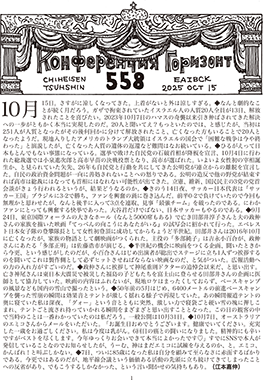
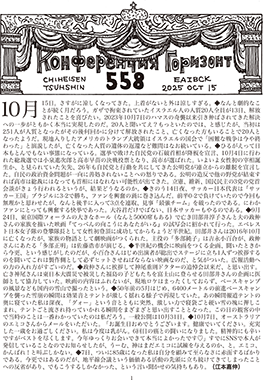
10月 15日。さすがに涼しくなってきた。上着がないと外は涼しすぎる。
◆なんと劇的なことが続く月だろう。ガザで拘束されていたイスラエル人の人質20人全員が13日、解放されたことを喜びたい。2023年10月7日のハマスの奇襲以来引き伸ばされてきた解決への一歩がともかく本当に実現したのだ。20人と聞いてえ?もっといたのでは、と感じたが、当初は251人が人質となったがその後何回かに分けて解放されたこと、亡くなった方もいることで20人となったようだ。現地入りしたアメリカのトランプ大統領はイスラエルの国会で「困難な戦争は今や終わった」と演説したが、亡くなった人質の遺体の返還など難問はなお続いている。
◆ひるがえって日本もとんでもない事態になっている。選挙で敗けた自民党の石破首相が降板を宣言、10月4日に行われた総裁選では小泉進次郎と高市早苗の決戦投票となり、高市が選ばれた。いよいよ女性初の宰相誕生か、と見られていた矢先、26年も自民党と行動を共にしてきた公明党が連立からの離脱を宣言した。自民の政治資金問題が一向に善処されないことへの怒りである。公明の造反で他の野党が結束すれば高市は総裁にはなっても首相にはなれない可能性が出てきた。立憲、維新、国民民主の3党の党首会談がきょう行われるというが、結果どうなるのか。
◆きのう14日夜、サッカー日本代表は「サッカー王国」ブラジルに3-2で勝ち、ファンを興奮の渦に巻き込んだ。前半0-2で負けていたので今回も無理かと思わせたが、なんと後半に入って3点を連取、見事「最強チーム」を破ったのである。にわかファンにとっても興奮する快挙であった。大谷君だけでばない、日本サッカーもやるのである。
◆9月24日、東京フォーラムの大きなホール(なんと5000席もある)で亡き田部井淳子さんと夫の政伸さんの家族を描いた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の試写会に招かれて行った。エベレスト日本女子隊の登攀隊長として女性初登頂に成功してからちょうど半世紀。田部井さんは2016年10月に亡くなったが、家族の物語として劇映画がつくられた。主役の「多部純子」は吉永小百合が、政伸さんにあたる「多部正明」は佐藤浩市が演じる。
◆半世紀の機会に映画をつくる企画、聞いたときから今更、という感じがしたのだが、小百合さんはじめ出演者が総出でステージに立ち1人ずつ挨拶するのを聞いてこれは製作側として必ずヒットさせねばならない映画なのだ、と気がついた。広報活動への力の入れ方がすごいのだ。
◆政伸さんに挨拶して神尾重則ドクターの追悼会以来だ、と思い出す。亡き神尾さんは東日本大震災で被災した福島の子どもたちを富士山に登らせる田部井さんの企画に医師として協力していた。映画の内容はふれないが、現地ロケはまったくしておらず、ベースキャンプの風景なども国内の雪山で撮ったという。
◆50年前の5月はじめ、6400メートルの前進ベースキャンプを襲った雪崩の瞬間は効果音とテントが激しく揺れる様子で再現していた。あの瞬間報道テントの奥に寝ていた私は深夜、「グォー」という音とともに突然、激しい力で寝袋ごと硬い雪の塊に押しこまれ、テントごと流され持っていかれる瞬間をまざまざと思い出すこととなった。この日の観客の中で当時のことは一番わかっていたのは私だろう。一般公開は10月31日。
◆10月7日、オーストラリアのエミコさんからメールをいただいた。「お誕生日おめでとうございます。健康でいてください。充実した一歳をお過ごしください。私は今度は乳がん。6回目の癌との闘いになりました。精神的にも辛いですがベストを尽くします。今年ゆっくりお会いできて本当によかったです♡」すでにSNSで本人が発信していることなのでお知らせしたが、うーむ、神はまだエミコに試練を与えるのか、と。エミコ、かんばれ!と叫ぶしかない。
◆7日、ついに85歳になった私は自分を顧みて至らなさに赤面するばかりである。今更ではあるのだが、地平線会議という価値ある活動の先頭に立ち続けてきてしまったことへの反省があり、でもこうするしかなかった、という言い聞かせの気持ちもあり。[江本嘉伸]
■「北海道大学大学院の矢澤宏太郎さんは、地球温暖化の影響を敏感に受けるグリーンランド北西部のカナック氷河(北緯77度)での研究活動を報告した。星野道夫の著作をきっかけに北極圏に惹かれ、気候変動が地球環境に与える影響を解明するため、氷河・氷床学の道へ進んだ。現地調査では、ドローンによる3D地形図作成やアイスレーダーを用いた氷厚測定といった最新技術を駆使。これにより、氷河が1年間で最大20mも流動するダイナミックな実態や、氷の融解量を面的に評価している。また、海に面したボードイン氷河では、氷の塊が海に崩落する『カービング』現象の観測にも成功した。これらのデータは、氷河の変動がもたらす海面上昇の予測精度向上に貢献する貴重なものである。研究は、伝統的な狩猟文化が息づくカナック村を拠点に行われる。現地の人々と交流し、その生活や文化に触れることも、研究活動の重要な一部となっている。矢澤さんは今後、博士課程へ進学し、科学的探求をさらに深めていく意欲を示した」。
◆東京駅から新大阪まで「のぞみ」で2時間半というのは、ちょうど地平線報告会の最初から締めの質疑応答までの時間そのままだ。きのうの報告会の録画を見返しながら、西へ向かう(あすは朝から大阪・関西万博会場で仕事があるのだ)。
◆冒頭の500字は矢澤さんの2時間半の報告を、Gemini 2.5 Flashに要約させたものだ。いかに味気ないことか。地平線での報告の真髄は、この500字には現れない、報告者の言葉の繰り返しや声に出さない逡巡、参加者の目の輝きや姿勢、質疑を通した戸惑いと発見にある。語られた言葉をすべて文字にしたとしても、この通信ではとても伝わらないが、せめてその努力はしてみようと思う。
◆地平線会議は来年2026年のこの季節に、北海道・西興部村で「地平線会議 in 北海道」を開催する。村の人たちだけでなく、道内各地の地平線の人たちに手伝ってもらい、かつその人たちの話を聞く場になるだろう。特に法政大学から北大大学院に進学した杉田友華さんのような若い人たちの志を受け止めたい。その杉田さんが薦めたのが、今月の報告者、矢澤宏太郎さんだ。
◆アッパという鳥がいる。植村直己さんも通ったシオラパルクで有名なアッパリアスに似ているが、手のひらサイズのアッパリアスと違い、両腕いっぱいに抱えるくらいの大きさがある。調査を終えて、カナックの村の中学生たちと歩いていた矢澤さんは、嘴が割れて食餌できなくなったアッパを見つけた。このアッパはもう長く生きられないから、殺して食べ物にしようと中学生たちは言う。日本人お前やってみろよ、胸骨圧迫して心臓を押し潰すか、首をねじって息の根を止めるかのどっちかだと言われ、矢澤さんはアッパを手にかけたが、うまくいかない。結局村の子たちがアッパの息の根を止めた。
◆「これが明日の自分たちに繋がるから、こういう生き物を殺すっていう行為は自分たちにとっては嬉しいことなんだっていうふうに教わって、相手は中学生なんですけれども彼らは強く生きてるなと。それと同時に劣等感を感じまして。そっか、自分はこの生き物1匹殺せないんだなっていう。ただの残酷な行為ではなくて、傷ついてこれ以上成長できない個体の命をいただくために殺すという行為もできないんだなっていうのにショックを覚えて」。これがきっかけで、矢澤さんはこの夏、狩猟免許を取り、命のやり取りというものが理解できないかと模索し始めたという。この24歳の眩しいまでのナイーブさもさることながら、こうした思考と行動とを直結できる北海道という環境にも、やはりどうしても魅かれてしまう。
◆矢澤宏太郎さんは札幌育ち。北大水産学部で音響資源量推定を研究。一方でワンゲル部に所属して北海道の山々を舞台に冬季の縦走やクライミングを趣味にしていた。積雪期単独北海道分水嶺縦断で知られる野村良太さんの後輩に当たる。大学3年生のときにベトナムへ1人旅した。最初に訪れたホーチミンで暑さとバイクの騒音に嫌気がさし、たどり着いたのは高原都市のサパ。そこで黒モン族の自然と密接に結びついた生活スタイルに感銘を受けたことが、大学院での選択につながった。一緒にハイキングしたり、料理したり、チャーミングな宿泊先の女主人との2ショット写真が印象的。
◆矢澤さんは海洋や音響物理から一転して、大学院では「地球圏科学専攻雪氷寒冷圏コース氷河・氷床グループ」に進むことに。そして入学式の日、「グリーンランドでドローンを飛ばさないか」と杉山慎教授に声をかけられて、極地研を中心とする「ArCSIII」北極域研究強化プロジェクトに加わった。ArCSIIIは、氷河だけでなく、海洋、文化、社会問題なども研究対象に含んだ大きなプロジェクトだ。
◆グリーンランドには2024年、25年の夏に1か月ずつ滞在した。研究の舞台は、飛行機で行ける最北の村、人口約600人のカナックだ。日本からデンマークのコペンハーゲンを経由し、グリーンランドのヌーク、イルリサットと乗り継いで向かうが、天候が不安定なため欠航が日常茶飯事。矢澤さんは「人生がうまくいってると思ってるやつはエア・グリーンランドに乗れ」という指導教員、ポドリスキー准教授の名言?を紹介した。2025年にはカナック上空まで飛んだが着陸できないこと2回。10日足止めされた後、3度目の正直でやっと村に入ることができた。着陸時には拍手が起きたという。
◆7月から8月の間の1か月は白夜の時期で、太陽は丘に隠れて村が日陰にはなるものの、沈まない。13人が共同生活するゲストハウスのオーナーはトク・オオシマさんとキム・ピーターセンさん。トクさんは、ご存知大島育雄さんの長女で、通訳から調査に使う漁船の手配まで、このプロジェクトになくてはならない存在になっている。
◆カナックではハンターがカヤックを使い、長い一本角を持つイッカクを、銛突き(ハプーン)を投げて仕留めるという伝統的な猟法が続けられている。中学を出た子供たちは村を出ていくことが多いが、ハンターに憧れて戻ってくるケースもあるそうだ。有名なアッパリアスに加え、北極イワナ、ハリバット(カラスガレイ)、アザラシと村の食生活は狩猟採集を基本としながら意外にも豊かなようだ。特にアザラシの脂は美味しく、オメガ脂肪酸が多く含まれて美容にもいいのだが、食べ過ぎると消化不良を起こす。矢澤さんもアザラシのカレーを食べすぎて、翌日から胃もたれで大変な思いをしたそう。
◆村には「ピラースイサック」というスーパーマーケットが1軒あり、食品、飲料から鉄砲まで売られている。グリーンランド語にも方言があり、矢澤さんの観察ではカナックではSの発音をHっぽく発音するのが特徴で、これを現地の人は「ピラーハイヒュック」と読む。しかしなぜか彼らはこのスーパーのことを「ビヒンヤビック」と呼ぶ。「ビヒンヤビックとは『ものを買う場所』。村の中にお金を払って物を手に入れる場所が1個しかないので、『買う場所』というと、ここを指すというのが面白い」。
◆そんなカナックをベースに、カナック氷帽、カナック氷河を杉山教授が観測地点として選んだのは、グリーンランド北西部には長期モニタリングされている氷河の研究サイトがなかったこと、そして大島育雄さんや植村直己さんら、さまざまな日本の冒険家たちの拠点となり、日本との繋がりが深いということからだという。
◆そもそも氷河とは、降り積もった雪が自らの重みで圧縮されて氷の塊となり、ゆっくりと動いている巨大な川のようなもの。チームは様々な方法でその変化を観測している。例えば、氷河に最長6メートルのポール(ステーク)を打ち込み、翌年その位置がどれだけ移動したか、ポールがどれだけ氷の表面から突き出たかを計測する「ステーク観測」。硬い氷河にドリルで6メートルの穴を穿つのは難しいし気をつかうし疲れるし、本当に大変そうだ。
◆矢澤さんの修士論文のテーマになっているのはドローンを飛ばして高精細な3D地形図を作成する「ドローン観測」。これにより、ステーク観測のような「点」の情報だけでなく、「面」として広範囲の氷河の変化を捉えることができる。この調査から、カナック氷河の末端部では、年間平均1.7メートルもの厚さの氷が失われていることが明らかになった。
◆こうした高さの比較から氷の厚さは間接的にわかるが、いま立っている表面から基盤岩までの氷自体の厚さを測るのがアイスレーダー(GPR)だ。レーダー装置を背負って2人1組で氷河の上を歩き、電磁波を氷の底にある岩盤に向けて発射する。カナック氷河では最大で厚さ150メートル。杉山教授と矢澤さんたちは氷上を40km以上歩くルートを設定して実行。しかし、実際の氷上は起伏もクレバスもあるし、水路も横切っている。GPSを持ってルート工作する杉山教授を先頭に進み、最後は融解水が濁流となった川をずぶ濡れで渡ることになった。
◆「みんなパンツまで濡れて。でもこのときはもう疲れすぎてたんで、なんかアイシングのような気分で気持ちいいな気持ちいいなとか、言ってたんですけど。約束の時間よりもオーバーしてしまって、迎えの船が干潮でも近づける場所を選ばないといけないっていうので、ずっと並走して追いかけて追いかけて、やっと船に回収してもらったんですよね。気持ち良かったはずの体はこの後の船上でどんどん冷えて、結局凍えながらカナックの村にたどり着いて、無事に氷の厚さを測定する旅が終わったっていう出来事ですね」。これはもう冒険そのものではないか。
◆こうした研究成果をカナック村の人たちと共有し、意見をもらうため、プロジェクトでは年1回ワークショップを行い、合わせて寿司やお好み焼きなど日本食も振る舞っている。矢澤さんはベトナムでの楽しかった交流を思い出したのか、カナック村の人たちの文化を知るため専門外の「研究」を個人的に試行した。日本から持参した27枚撮りのカメラ付きフィルムを数人に渡し、身の回りを自由に撮ってもらって、被写体を分析する。スーパーで働くカメラ好きのイエンスが撮ってくれた17枚はほとんどが景色と人。スーパーの裏のノスタルジーな雰囲気が伝わってくる。
◆犬ぞりでハリバットを獲りに行くハンターのマヒュッチャクは、コミュニティセンターに遊びに来る中学生や愛犬の写真を撮ってくれた。「犬がカメラのレンズなめちゃったけど大丈夫?」と心配していたらしい。学校を卒業したばかりのヤコビナが撮ったのも、やはり犬。ちょうど仔犬が生まれたばかりだったそうだ。現地のハンターに一目惚れして夏場はカナックで暮らす日本人のサキコさんにもカメラを渡した。彼女は風景だけでなく、身の回りの物を多く撮ってくれたという。
◆日本から来た学生や矢澤さん自身が撮ったものも現像した結果、ある共通点に気づいた。カナックの沖合にあるケケッタハ島がほぼ全員の写真に入っているのだ。イエンスが友人を写したショットの背景にケケッタハ、サキコさんが撮った風景にも少し見切れたケケッタハ、マヒュッチャクの写真にも、ヤコビナの写真にも。矢澤さんも数えれば50枚以上ケケッタハの風景を撮っていた。「それくらいこの景色は魅力的で、自分も好きなので、同じような思い、そこで生まれて育った人たちも持ってるんじゃないかなって思いを馳せました」。この個人的プロジェクトが次回以降どこに向かっていくのか、大変楽しみだ。
◆「自分が70歳になったときに植村直己さんがグリーンランドに初めて行ってから100周年になるんですけれども、それまでの間に自分がグリーンランドで何者かになりたいと思っていて、そのプロセスはまだサイエンスなのか、文化なのか写真なのか、冒険なのかわからないですけれども、日本との不思議な繋がりっていうものが現地に行くとすごく伝わってきて、そのためにもなるべく長く頑張りたいなと思ってます」。
◆報告会の2週間後というから、この通信が発行されるころには矢澤さんはネパールのトランバウ氷河・トラカルディン氷河の調査に参加するという。ネパールと言えば、貞兼綾子さんと共にランタン谷に長期滞在した樋口和生さんを思い出す。樋口さんも北大山岳部出身で、第57次で隊長としての南極で越冬した直後の2017年5月、地平線会議で報告。その後昨年まで第64次で2度目の越冬隊長を務めたことをご記憶の方も多いと思う。その前、63次の澤柿教伸さんも南極から戻ってすぐに報告してくれた。澤柿さんと言えば、矢澤さんを紹介してくれた杉田友華さんは澤柿ゼミ案……、あれ、ランタン、南極、グリーンランド、みんなつながってる?
◆Geminiには決して解釈されない彼らの魅力を感じるために、私は報告会に足を運ぶ。そしていよいよ来年のこの季節。北の大地でもっとたくさんの旅人たちの報告を聞きたいと期待が高まる。[落合大祐]
■今回、初めて地平線報告会に参加させていただきました。角幡唯介さんや山崎哲秀さんが報告されていたことからこの会の存在は知っていましたが、まさか自分が登壇することになるとは思ってもいませんでした。北大にやってきた杉田友華さんの推薦をきっかけに、江本さんとのやり取りがとんとん拍子に進み、あっという間に報告会当日を迎えていました。報告会では、これまでに二度参加したグリーンランド北西部カナック氷河での現地観測と北緯77度にあるカナック村の滞在について、お話をさせていただきました。2時間にわたって話すのは初めての経験でしたし、特に氷河の話は馴染みのない方が多かったと思いますので、うまく伝えられるか不安でした。それでも、温かく迎え入れてくれた地平線会議の皆さんには心から感謝しています。
◆私の先生がグリーンランドで研究を始めてから10年以上たち、村の人にとっては、夏になると日本人がやってくるというのが当たり前になっています。研究が、人と人との「つながり」を生み出してきたことには、感慨深いものがあります。また、カナック村は地球最北の村で極地冒険の拠点でもあるシオラパルクの隣町です。そのため、現地に滞在していると「オオシマ」という姓を持つ人や日本語の単語を話してくれる人と出会うことができ、6000キロメートル離れた日本とカナック村の不思議な「つながり」を感じさせます。私自身、初めての地平線報告会で、参加者の皆さんとは初めましてだったのですが、北大の先生や山岳ガイドの方々、グリーンランドの現地住民などを共通の知り合いに持つ参加者がいて、地平線会議のコミュニティの広さや歴史、皆さんの興味の幅に驚くのと同時に、ここでも不思議な「つながり」を感じました。
◆「地平線」とは、地面と空の境界をなす線を意味します。地球のどこでも地面と空の境界があり、活動の分野は違っても地平線という同じ景色を共有しているはずです。そこで、世界各地の地球体験を「地平線」と表現して語り合っているのだと感じました。私はこれからも地球のどこかでもがき続けます。またいつか、この場で報告ができればいいなと思います。[矢澤宏太郎]
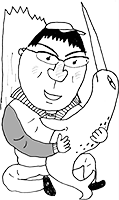
イラスト 長野亮之介
■2026年初秋に予定している北海道での地平線会議を成功させるため、1万円カンパを募っています。北海道地平線を青年たちが集う場にしたい、というのが世話人たちの希望です。交通費、宿泊代など原則参加者の自己負担としますが、それ以外に相当な出費が見込まれます。どうかご協力ください。[江本嘉伸]
賀曽利隆 梶光一 内山邦昭 新垣亜美 高世泉 横山喜久 藤木安子 市岡康子 佐藤安紀子 本所稚佳江 山川陽一 野地耕治 澤柿教伸(2口) 神尾眞智子 村上あつし 櫻井悦子 長谷川昌美 豊田和司 江本嘉伸 新堂睦子 落合大祐 池田祐司 北川文夫 石井洋子 三好直子 瀧本千穂子・豊岡裕 石原卓也 広田凱子 神谷夏実 宮本千晴 渡辺哲 水嶋由里江 松尾清晴 埜口保男(5口) 田中雄次郎 岸本佳則 ささきようこ 三井ひろたか 山本牧 岡村まこと 金子浩 平本達彦・規子 渡辺やすえ 久保田賢次 滝村英之 長塚進吉 長野めぐみ 北村節子 森美南子 飯野昭司 猪熊孝行 岡村節子 加藤秀宣 斉藤孝昭
★1万円カンパの振り込み口座は以下のとおりです。報告会会場でも受け付けています。
みずほ銀行四谷支店/普通 2181225/地平線会議 代表世話人 江本嘉伸
■江本さん、地平線通信読者の皆様、ご無沙汰しております。北海道で山仕事をしている五十嵐です。去る10月10日に終了した間伐作業について報告します。
◆今回作業を請負わせてもらった現場は、北海道某所にある25年生カラマツ林です。この木を胸元で測ると、樹の太さが16㎝程度、高さは18mくらい。普通は「切り捨て間伐」にしてしまうような細い林です。切り捨て、というのは、切り倒した木を搬出せずに、林内で刻んで間伐を終える方法です。カラマツは比較的値段が安く、販売しても作業費用のほうが高くつくことが多いため、木が細い林ではよく選択される手法のようです。
◆今回は、山主の要望もあり、「皆伐を想定して植えられた人工林だけど、私は皆伐せず、針広混交林にしたい」「せっかく木を伐るなら使ってもらいたい」という声に応えるべく、馬で出す間伐方針に決定しました。伐る木と残す木を事前に選び、林内をなるたけ傷つけずに木を運びだすとなれば、馬の出番です。ただ、馬搬は丁寧な分、重機に比べ作業効率は悪く、費用が嵩みます。馬搬は「高級な林業」です。馬の親方が普段請け負っている、巨木の生える天然林なら、丸太の値段も高く採算が取れそうですが、ここは細いカラマツ林です。炭鉱杭や建築足場に需要があったころとは時代が違うのだから、木代金で費用を賄うことなどできるのか? 親方も普段から「人工林で馬は合わないんじゃないか」と言っています。
◆逆に、もしこれが仕事として成立するなら、馬搬現場拡大のヒントをつかむことになりそうです。親方が仕事を受けているような、木の値段が高い森は、北海道にそう多くありません。私が今後仕事を展開していきたいと考える地域も、カラマツの人工林が主体の地域なので、そうした場所でどう仕事を成立させるかというのは、馬搬の拡がりを考えるには必須のテーマだと常々思っていました。今回はそれをシミュレートする好機だったのです。とはいえ、皆が赤字にならないような作戦が重要です。馬が来たときに効率的に運んでもらうには、木をどの方向に、どの順番で倒しておくのか。馬搬の戦略を練ります。
◆木の売り先を考えることも大前提です。「パルプ材」として売るのは簡単ですが、単価は最安値で、赤字は目に見えています。結局、杭や足場として買ってくれる業者との出会いに恵まれ、パルプの倍以上の単価で木を買ってくれることに。ちなみに足場は、冬の雪捨て場の基礎に敷いて、雪面を行き来する重機が沈むのを防ぐために利用されるそうです。
◆馬搬も、事前に立てた戦略がそれなりに功を奏して、予定期日内に作業を終えてもらうことができました。前半に小規模林業用の集材機械、後半は馬で、それぞれ同量の丸太を搬出したのですが、2人がかりで作業する機械で10日かかったのと同量の丸太を2人で3日で薮出ししたのには驚きました(林道に出した丸太は集材機械で回収、3日間で椪積みをしました)。
◆これまで仕事にするのは厳しいと思われていた人工林での間伐でも、条件があえば仕事になるかもしれないとわかったことが今回の最大の収穫でした。条件があえば、というのは、(1)小規模でもパルプ材以外の販路を確保すること。(2)最大効率で作業ができる馬搬チームが組織できる(人工数を抑える)こと。(3)馬がスムーズに木を運べる地形であることの3つが思い当たります。とくに(2)に関しては、自分と同じ程度にヤマで動いてくれる林業仲間、そして自分の馬の確保等、課題は多いですが、今後の馬搬現場の可能性に希望を感じた秋でした。
◆重機を使用して早く沢山の木を伐る大規模林業でもなく、チェンソーと軽トラックで自家用の木を賄う自伐的な小規模林業でもない、その間の中規模林業とでも呼びうるような領域で、馬搬現場の開拓ができるのではないかと静かに興奮しています。今後予定されている馬搬現場に引き続き混ぜてもらい、馬方としての独立目指して現場での学びを続けていきたいと思っています。[五十嵐宥樹]
■台北市内から北に車で30分のところに「北投」という温泉地がある。石川県和倉温泉の旅館、加賀屋ののれんも立ち並ぶ気軽に行ける観光スポットだ。その歴史は日本時代の1913年、熱海の伊豆山温泉を模した公共浴場が始まりで、往時は芸者さんの踊りや歌声をはじめ、流し音楽や食文化など活気に満ちた歓楽街情緒が漂っていたという。
◆戦後にいちどは荒廃するも、1998年に地元住民の力によって復元された史跡として、台湾総統府を手がけた森山松之助氏が設計した「北投温泉博物館」は北投文化のシンボルとなっている。レンガ造りの一階は当時の沐浴空間が再現されており、木造の二階には休憩所の畳の大広間が広がる温泉郷に相応しい建築物だ。
◆毎年中秋にここ北投温泉博物館で開催されてきた「台湾月琴民謡祭」が15周年を迎える今宵。青森の師匠・渋谷和生会主「和三絃会」はこのたび6年ぶりに参加させていただいた(2012年第2回に初参加。通算7回目)。
◆9月26日。主催者の「月琴民謡協会」、琉球舞踊の「紅倫の会」と共に、絵付を施したたくさんの月琴で装飾された大広間のステージにて特別公演が開かれた。オープニングの台湾月琴の調べに乗せた華やかな踊りで幕が開くと、琉球花笠を身に纏った踊り手達は、ゆったりと優雅な三線の旋律に合わせて王朝文化の荘厳な風格を静かでしなやかな動きで再現し、民間芸能のカチャーシーでは一転会場を巻き込んで観衆も一緒になって賑やかに踊り出す。北国特有の津軽三味線の力強い撥捌きに合わせて民謡歌手の生命力溢れる唄声が会場全体にこだまするかと思えば、盆踊りでは皆の笑顔の輪が生まれる……。
◆台湾〜琉球〜津軽。土地から土地へ。人から人へ。風土は違えども、一つの舞台上で三種三様の唄と踊りの織りなす物語が重なり合い、会場の熱気のなかで浮かびあがる壮観な景色には、『未来をも照らしているような感覚』を覚えた。ステージ上から肌で感じる観衆の感動の眼差しが、「民謡は地域の声にとどまらず、国境を越え、世界へと歩み出し、交流と刺激の中から無限の可能性を広げていく」ということを思い出させてくれるのだった。
◆思い返してみれば、僕が台湾の師匠・陳老師と初めて出会った2008年。陳老師はその出会い頭に僕を月琴の故郷の恆春に連れていってくれた。そこは今は亡き陳老師の師匠・朱丁順老師が地元に月琴を普及させている現場だった。その翌年に陳老師は台北で月琴民謡協会を立ち上げ、2011年に第一回月琴民謡祭を開催している。
◆「初めは生徒は二人だけだったんだ。今では1000人を超えているんだぜ」と今回陳老師は感慨深げに呟いた。僕は2012年以降、陳老師の家にお世話になりながら、彼が来る日も月琴教室に通う後ろ姿や、民謡祭のたびに数多くのスタッフ達が熱心に準備を重ねて会場を設営する風景を近くでずっと見てきている。この15年間、陳老師は音楽活動の傍で台北の土地を耕し月琴の種を撒き豊かな土壌に変えていたのだ。
◆台湾と日本を結びつけているものの中には、手放しでは廃れていってしまうものがたくさんあって、それらは決して当たり前には残らない。温泉も唄も踊りも「人の情熱」が繋ぎ止め、その情熱は人々へと伝播する。今回は改めて現場を支え続けている彼らの情熱や熱意に感じ入る一週間だった。
◆コロナ禍を経て大きな隔たりを経験した民謡同士の交流も青森チームとして台湾での活動がようやく実現した今、次は台湾チームが青森に来る気配も漂い始めている。僕個人としては12月6日には恆春で行われる陳老師の大きなコンサートにも参加する予定だ。一つ一つの場面を大切に、今後の展望に想いを馳せてゆきたい。[車谷建太]
■地平線通信557号(2025年9月号)はさる9月17日、印刷、発送作業を終えました。作業に汗を流してくれたのは以下のみなさんです。おつかれさまでした。岡村隆夫人、節子さんははじめての参加で頑張ってくれました。ヨーロッパ歩き走り旅から帰国した坪井伸吾さんも日焼けした顔で元気に汗をかいてくれました。ありがとうございました。
車谷建太 中畑朋子 伊藤里香 渡辺京子 高世泉 岡村節子 白根全 坪井伸吾 江本嘉伸
■ポルトガルにあるユーラシア大陸最西端ロカ岬をスタートして、フランスのルピュイまで2800キロを歩いた。そこでEUに滞在できる90日が終わってしまった。ルピュイから鉄道でリヨンまで移動して、EU圏外であるセルビアのベオグラードまで飛ぶ。さらにバスでボスニア内にあるスルプスカ共和国の首都バニャルカを目指す。バニャルカまではバスで8時間。畑と森が続く道はどこまで行っても路肩はない。町に着くまで道を歩く人間はもちろん、自転車すらも目にすることはなかった。
◆巡礼路の外に出ると、違う世界が待っていた。巡礼路は一応安全が保障されている。車はほぼ通らないし宿は15キロおきぐらいにある。村もあるので、水、食料の心配もない。ひとつの巡礼路が700キロほどもあるがイメージはマラソンと似ている。巡礼路の達成者は歓喜でゴールを迎え、次はどの巡礼路を歩こうかと考える。何本もの巡礼路を歩いた人にはあったが、巡礼路という「枠」から出た経験を持つ人には会わなかった。
◆バニャルカから出る道はどの方向も川沿いの谷道。ケータイの地図を拡大すると高速道路脇に一般道は見えるが、途中で消えたり高速に合流したりする。徒歩で進む場合、ここはどうすればいいのだろう? 宿のオーナーに聞いてみる。オーナーにとって「歩く」は想定外らしく、本気で言ってるのか、って反応だ。この問いに答えられる人間は……自転車乗りか! サイクリストは町から出るときにどのルートを通る? ケータイで探すと「シマノ」がある。英語ができる店員さんが「それはGoogle Mapsの『歩く』モードで探すしかない」と言う。
◆ボスニアとセルビアを歩き、ブルガリアを目指す。特に行きたい場所はない。ここまで自由だと逆にルート設定が難しい。今思えば、徒歩で越えられる国境は限られているから、そこを基準にルートを決めればよかったのだが。いろいろ悩んだあげく、初日はバニャルカから20キロほど北の町、ラカタシに決める。ラカタシまでは辛うじて一般道で行けそうだ。距離も無難だし、安い宿もある。問題はそこから先だ。ラカタシ方面に出た場合、次の町プリジョバールまでは44キロある。でもそれは国道61号線を使い真っすぐに進めた場合の距離で、61号が危険な場合、山の中に張り巡らされた糸のような道を探りつつ町を目指すしかない。距離も読めない。
◆ラカタシから森の中を抜けて10キロ地点、祈る気持ちで61号線に出る。61号線は路肩の夏草が道まではみ出し、道幅いっぱいのトレーラーが走っていた。厳しい。巡礼路は2800キロ歩いても、こんなことは起こらなかった。諦めてグーグル先生が示す未舗装の山道を探すことにする。まず来た道を2キロほど引き返す。往復で4キロのロス。歩き旅では致命傷の距離で、これでもう町までたどり着けない。舗装路から山道に入ると倒れた木が道をふさいでいる。悪い予感がする。入って1時間。誰とも出会わない。道にクマらしき足跡が現れる。町まで着けなければ、この森で野宿だ。さらに1時間後。突然電波が途切れる。現在地を示す青い点だけが携帯の画面上にある。しまった。地図は表示されていたから油断していた。
◆目の前の分岐をどちらに進む。南を走る61号線に入れないなら、北に進み、町の背後に出るが正解。しかし北を選べば、もっと山深くに入り込む。方位磁石と感覚だけで、この先に現れる分岐を選べるか? 考えると恐ろしくてできない。結局、南に下り、町に近づくとグーグルは復活。復活はしても目の前で画面から道が消えたりしてもう信用できない。この日は56.4キロ歩き、夜8時に町についた。
◆翌日、町で紙地図を探してみる。書店にも図書館にもガソリンスタンドにもない。携帯でクマを検索するとボスニアグマは存在している。国道には交通事故の危険があり、山にはクマがいるか。数日後、グーグルにまた山の中に連れ込まれ道が消える。そして目の前に現れたのはドクロマーク。どうも国境の地雷地帯だ。看板のボスニア語を翻訳モードで読むと、「アナタは犯罪行為をしている」と出る。地雷は仕掛けた側も場所がわからない。昔、アフリカアンゴラの難民キャンプにいたときに専門家から、そんな話を聞いた。内戦から30年が経過した今もボスニアでは被害者が出ている。
◆足元に注意を払いつつ来た道を戻る。麓の村に戻るとすでに15時。今日の宿は予約しているが、山越えができないうえに時間をロスしてたどり着けない。もう「歩く」にこだわっている場合ではない。そう思ったが、冷たい水を買って飲むと気持ちが落ち着く。ケータイで必死に探すとモーテルがあった。追い詰められると驚いたことに「走れる」。この旅で走るのは初めて。長らく使っていなかったので、走る筋肉は「歩く」筋肉にすべて置き換えられたと思っていた。走ったおかげで日没までに宿に着けた。ベッドに腰掛けると「助かった」と自然と言葉が出た。[まだ走ることもできる 坪井伸吾]
■恒例の秋の個展です。今年3月と8月の2度訪れた、アフリカ中部カメルーンでのスケッチなどを展示します。人の熱気にあふれたアフリカのイメージがどう描けるか、鋭意製作中。
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです(メールアドレス、住所は最終ページにあります)。
桜井勝之 大河原由紀子(10000円 毎月、通信を楽しく隅から隅まで読んでいます。日光に移られた貞兼綾子さん、昔ネパールで付き合いのあった人。次回は私もご一緒したい。通信を読んでいると世界は狭い。記事がとても楽しみです。ありがとうございました) 野口英雄(5000円 2年分とカンパ1000円です。毎月、地平線通信、楽しみにしています) 勝見洋一 大嶋亮太 嶋洋太郎 岩野祥子(10000円) 近藤淳郎 岡村節子
■9月26日22時30分、都内での業務に区切りをつけて故郷である輪島市町野へ車を走らせる。天気は埼玉、長野、新潟とときどき雨がパラパラと降ったり止んだりしていた。道中のSAには今年の春先まで時折見かけた、「がんばろう! 能登」や、「いつも一緒、がんばろう」などと書かれたキッチンカーの姿はもうなかった。
◆夜通し走り富山に入ったころに空が明るくなってきた。先月は日の出と共に汗が滲み出す暑さだったけれども今日は涼しい朝だ。奥能登に入ると途端に道の事情は変わった。アスファルトを貼り直した復旧道路はずいぶん走行しやすくなったけれども地面をなだらかに整地したわけではないので上下左右蛇行した道になる。
◆残り70キロは油断禁物だ。むしろ気を張らなければならない。午前8時、輪島市白米千枚田に到着。今年は全体の10%程度にも満たないくらいの田植えだった様に見えたけど7月、8月の炎天下の中、草刈り十字軍と名乗るボランティアさんたちで草刈りをしていたことを思い出す。稲刈りは9月の中旬に終えたそうだ。
◆さて、私の定点撮影ポイントだった場所は崩落の危険から立ち入り禁止となってしまったので、場所を変えて水平線にレンズを向け撮すことにしているが、私の感覚は地震後からズレたままだ。決して変わらないと思った光景は変わってしまったままだし、この世界で変わらないものなど何ひとつないことを地震が教えてくれた。
◆9時、海岸線を通る国道が使えるようになったので、実家に向けて車を走らせる。この復旧道路は以前は海底だった場所なわけで、車窓右側上部を眺めると旧道路と電信柱が残っている。不思議な感じがする。左側には津波避けに黒色のフレコンバックが2階建程度にズンズンと積み上げてある。重量にしてどのくらいなんだろうか? 見当もつかない。
◆フレコンバックどうしの隙間に雑草が根を生やし始めていた。春先は大量に野積みされたフレコンバックが殺風景だったけれども草が生えただけで命の循環を感じるが同時に退廃的でもあった。真っ青の空がもの悲しさを演出するが、心を明るくしてくれてもいた。9時30分、実家に到着。生まれ育った家の姿はもうなかった。9月1日から解体が始まり16日に父が現場立ち合いのもと公費解体が完了した。
◆家は更地になったが、敷地内をしの字で囲っていた生垣はそのまま残っており、玄関先までのアプローチもそのまま残って何とも滑稽な様子だった。私は父が生活する仮設住宅に真っ直ぐに帰省することはしなかった。小・中・高と学生のときの帰宅路に立ってみて実家があった画角を眺めたり、今年のお盆まで父が生活をしていた居間の窓越しの光景を更地になった地面に立って眺めたり、私が学生時代に生活した部屋は2階だったので、その直下の地面をしばらく眺めて写真を撮した。
◆私は20代のころにオーストラリア、タイ、インド、ネパール、トルコ、オランダなどを旅していた。そのころに帰るところがあるから旅ができるわけで帰るところは家ではなく、その人がいるところだと確信していた。でも私は、父のいる場所ではなく生活をした場所に帰っていた。地震は仕事、家、思い出、命を奪った。だけどすべてを失ってひとつ見つけたことがあった。それは家族の尊さだった。
◆これまで盆暮れ正月に忙しいから帰省できないと言っていた子どもたちが、家族を心配して戻ってくるようになった。震災時、無力な自分を自然界から徹底的に教えられた私は、こうした人々の心の変化を受け昨年のお盆に町野小学校と、仮設住宅地内の集会所を簡易スタジオとして家族の肖像写真撮影プロジェクトを立ち上げ撮影させていただいた。これがきっかけで今年の4月から来年の3月まで小学校と中学校の子どもたちの撮影をしている。
◆地震で外へ出るのが怖くなってしまった子どもたち、親の事情で別れ離れになってしまい新学期から友達がいなくなり心を塞ぎ込んでしゃべらなくなってしまった子どももいた。ようやく気を取り戻したころにやってきた奥能登豪雨は、また子どもたちの心を痛めた。雨が降ると怖くなり外へ出たがらなかったりもする。
◆昨年9月の奥能登豪雨は故郷に深刻な影を落としている。「もとやスーパー」は事業方針の見直しを余儀なくされた。町野町の田園風景は豪雨によって壊滅的ダメージを負っている。これは表面的な話だけではなく内面的な問題だ。田んぼの仕組みはお隣さんのお隣さんもお隣さんの関係で成り立っている。用水が復旧しないためほとんどの田んぼは機能していない。
◆1年も耕作しない田んぼはあっという間に野となれ山となれである。いちどこうなってしまった現状が一番深刻な問題だ。みんなで面倒をみてきた田んぼは人と人の繋がりであり、こうした“結の精神”は戻ってくるのだろうか? 私は二重被災から1年後の子どもたちの学校生活と故郷の祭文化を通してみる成長と、何とか行うことができた田んぼの成長を、命の関わり合いと見立て町野の変わりゆく今を、毎月帰省し撮り続けている。今は父のいる仮設住宅に身を寄せているが、私の役目が終わり、父がいなくなったとき、故郷って、どこなんだろうかと考えさせられている。[東雅彦]
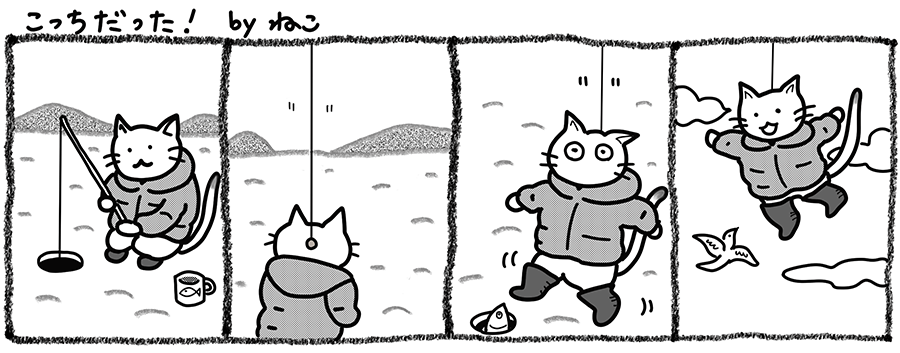
《画像をクリックすると拡大表示します》
■9月は旅ばかりしてました。9/5から3泊4日で念願のトカラ列島ツアー(50名定員160名応募)が当選して宝島、小宝島、悪石島のボゼ祭りに行ってきました。群発地震の最中で、こんなときだからこそと島民が一丸となって盛り上げていて素晴らしい体験でした。祭事というのは住民を結束させる力がありますね。来年もトカラ列島には行くつもりですし、各地の来訪神の祭りを訪ねてみたくなりました。
◆また秋分の日の連休に3泊4日で福井へ仁と行ってきました。甥が熊川宿でJAZZ喫茶店を開業したお祝い旅で、敦賀でレンタカーを3日間借りて久しぶりに運転(我が家は仁は運転しないのでわたしが運転役)三方五湖の年縞博物館や若狭、鯖街道を楽しみました。翌日、福井在住の塚本昌晃さんと駅つながりの恐竜前で待ち合わせ、彼の故郷三国港や東尋坊などを案内してもらい楽しい1日になりました。
◆永平寺から最後は県境越えて山中温泉へ。敬老の日に半世紀ぶりに登った雲取山で無理をして足を痛めてしまったので、湯治になりました。松尾芭蕉ゆかりの山中温泉は石川県の奥座敷ですが福井から1時間で行けるのだと知りました。「山中や 菊はたおらぬ 湯の匂ひ」。山中温泉に来ると、長寿の薬と言われる菊をわざわざ折る必要もないほど、素晴らしい温泉の香りがする。この湯の匂いだけでも命が延びるようだという意味だとか。町の中心にある公衆浴場「菊の湯」はこの句から名付けられ、観光客だけでなく地元民の憩いの場になっていました。また、鶴仙渓(かくせんけい)と言う渓谷の遊歩道が素晴らしいから足が痛くても少しでも歩くようにとのことで、湯上がりにあやとり橋から芭蕉堂、黒谷橋まで歩いてリフレッシュできました。
◆3泊4日旅というのには理由があって、火水木と週3日だけの新しい仕事を67歳からしてるからです。そんなしばりの中で残りの時間を使って旅の計画を考えることが楽しくて仕方ない最近の私です。[高世泉]
7月号の通信で大西夏奈子さんが書いてくれたように、この7月6日から13日までの1週間、天皇皇后両陛下がモンゴルをご訪問された。天皇にとっては皇太子時代の2007年に次いで2回目。国の祭りである「ナーダム」もしっかりご覧になられた。天皇にとってもモンゴルにとっても大事な日々について花田麿公さんに書いていただいた。[E]
■江本さん、天皇、皇后両陛下のモンゴル訪問は、世間で言われるより意義があるのではと思います。この訪問の目的の第一は、皇室がとくにご配慮されている慰霊の旅でした。戦後80年、昭和100年の節目、特に意義が大きかったと思います。1971年、外交関係がなかったとき、ダルハン市の小学4年の地理授業で女生徒に聞きました。「日本知ってますか?」「モンゴルの敵です」
◆いま、日本はモンゴル人の好きな外国第一位です。周辺の北東アジア各国で唯一両陛下安心して行ける国です。誇りです。モンゴル側から元首が10回以上訪日されています。両陛下のご訪問で多少モンゴル国民はこころ満たされたのかな、と思います。
◆両陛下はモンゴルの建国記念日7月11日の祝祭に参加されました。モンゴル国民の敬愛を集められたと思います。とくに、2007年陛下が皇太子時代のご訪問に続き、モンゴルオーケストラに参加されチェロを演奏されたことは、この上ない特別なこととしてモンゴル国民の心に響き、長く記憶されるでしょう。両陛下の外国訪問は滅多にありません。その中のモンゴルです。両国関係の盤石さを示し、世界を驚かせたと思います。日本に皇室があるありがたさです。
◆ソドノム首相が首相として初来日したとき、宮殿にお供しました。大きな中庭の対角線上に紅梅と白梅がありました。首相は「モンゴルにもチンギスハンの帝室がありました保持していればこのような宮殿があったのでしょう」と言われていました。[花田麿公]
■地平線会議の皆さまには、とりわけ2015年以降のランタン谷について、ずっと見守っていただいてきました。前号で江本さんが来日したテンバ夫婦のことに少し触れてくださったので、この誌面をお借りして、初めて訪れた日本での二人の様子や少し昔に遡って、彼らが幼かったころのことなどお話ししたいと思います。
◆テンバは私の友人(故人)の息子、彼が生まれたときから成長を見てきました。とりわけ2015年の大震災の折には、テンバなどカトマンドゥ在住の若者が中心となって、壊滅的な被害に遭ったランタン谷の人々をカトマンドゥにヘリ輸送し、一箇所(お寺の境内)に集め、国内外からの支援を窓口一本にして、数か月後には当面生活に必要な物資を各人に持たせてランタンへ送り返しました。そういう意味で、村人の再生の基盤を築いたと思います。テンバは巳年生まれの48歳、嫁のチャンジュは4歳下の44歳。
◆テンバとチャンジュは、今年のお盆のころに突然に日本へやってきました。ヴィザがなかなか取得できず、申請して1か月後くらいにようやく入手。その日のうちに電話があって、「1週間後に行きます」。嬉しいやら、困惑するやらで、彼らを待つ1週間はまるで暮れの大掃除のようでした。
◆彼らの来日の目的は私の病気見舞い。3月初旬から約4か月間、右腎盂腎炎なる泌尿器の不具合で体調を崩していたのですが、彼らがやってきたころには復調していました。それでもほぼ10日間、ずっと一緒にいて、お掃除や食事の支度など、本当によく世話を焼いてくれました。各種の香辛料や豆類、コッフィーや紅茶など、彼らがネパールから持ってきたものを見ると、私の代わりにしっかり台所を預かる意気込みが感じられました。普通、他人の家の台所を使うには、ある種の躊躇があるものです。ましてやまったく文化の異なる異国の台所となると戸惑いもあったと思うのですが、そこはそれチベット人。彼ら特有の好奇心も働いてIHクッキングヒーターや洗濯機、圧力鍋、炊飯器、食器の位置など一度教えると、難なくわが家の台所に溶け込みました。
◆テンバ夫婦のお土産に、香りの良いお線香や五色旗(ルンタ)に加え「LEDバターランプ」があり、驚きました。高坏様の容れ物は金ピカの飾りがついていて、2週間毎にチャージすれば、半永久的に灯し続けられるしろもの。先週の土曜日(10月4日)に4回目のチャージをしたところ。つまり、テンバたちが日本の私を訪ねてくれた記念の日から50日は経過したことになります。敬虔な仏教徒であれば、毎朝夕の灯明は普通のことですが、チチ(母の姉妹・私のこと)はそうはゆくまいと思ったのでしょう。良いものをくれました。
◆彼らが当地に滞在中、日光東照宮や奥日光、それから昔住んでいた鎌倉へも泊まりがけで出かけました。初めて海を見た嫁は稲村ガ崎の岩に砕ける波の前で踊ったり歌ったり、床上50センチはある長い髪を風になびかせながら彼女なりの感動表現をしていました(ちなみに嫁の身長は170センチくらい)。帰国した二人にどこが印象的だったかと尋ねると、声を揃えて「カマクラ!」と。
◆滞在中の二人は毎日のように、空気が美味しい、お水が美味しい、へ(ジャガイモ)が美味しいと言い続けました。ジャガイモはランタンではほぼ主食といっていいほどです。彼らがこの地のものを美味しいというのは、お世辞ではないかと思ったのですが、鎌倉の農民市場で買ったジャガイモは美味しいとは言いませんでした。「柔らかすぎる」らしいのです。当地のものは「身がしまっている」。デンプンの含有量が多いのでしょう。ネパールでも高地産は珍重されます。私たちが北海道産のジャガイモを美味しいと思うように。余談ですが、鎌倉への道すがら、乗り物酔いをする嫁のために、高速のサービスエリアに何度も立ち寄りました。都度、嫁とテンバは必ずといっていいほど「ポテトコロッケ」を買ってました。
◆信仰について少し。二人からのプレゼントが物語るように、彼らは祈りを欠かしません。これは、震災後のランタンの人たちにとって特に顕著で、老いも若きも等しく、目に見える変化だといってもいいと思います(昔はそれほどでもなかったのです)。「自分の犯した罪のせいで大地の怒りを招いたのではないか、亡くなった親族をどのように弔うべきなのか」、とばかりに、日常の祈りのみでなく、年中行事の復活、カトマンドゥ市内や近郊の聖地巡りを怠りません。何か救いを求めているように見えました。ランタンプランに対して、村人からの最初の要望が「キャンチェンゴンバ」を再建することだった、と今しみじみ思い起こされます。
◆帰国の1日前、8月24日にこれまでランタン谷の復興に関わってくださった方々が集まってくださいました。地平線会議+ゾモ普及協会の江本嘉伸さん、田中明美さん、横内宏美さん、阿佐昭子さん、中嶋敦子さん、落合大祐さん、大阪市立大学山岳会OBの兵頭渉さん、それに2015年10月、現地ランタン谷で大なだれの被害状況調査にあたった、国立防災科研の山口悟さんと都立大都市環境科学研究科の泉岳樹さん。山口さんは、長岡からの参加でした。
◆テンバは、「その後のランタン」について、スクリーンの画像を見ながら語ってくれました。これは事前に準備したのではなくて、テンバがその場で自分の画像からピックアップしたものを映写できるよう泉さんがセッティングしてくださいました。彼はまるで他の場所でもこの種の報告をしたことがあるように、震災後と現状の違いがわかるように組み立てて語っていたと思います。適宜私たちの質問も挟みました。山口さんたち調査チームが作成したハザードマップが、村の再建に生かされているのかどうかなど厳しい質問も出ました。お話の要点は、文明の利器(モバイルなど)の導入もあって生活は便利になったこと、村人は計画的な住宅建設には行政と国立公園の規制があって理想通りにはいっていないこと、厳しい牧畜の現状など。この日のテンバの最新ランタン報告は、泉さんが動画に記録してくださっているので、後日、翻訳してランタンプランのウェブサイトとFacebookに載せる予定です。
◆参加いただいた皆さんへ私たちからささやかなお食事を用意しました。嫁チャンジュが腕によりをかけて作ってくれたこの日のメニュー:1 ガサ(ジャガイモ料理、ランタンでは法事や結婚式などには必ず供されるもの)/2 ダルスープ+ご飯(いわゆるダルバート。彼女がネパールから持ってきたダル豆は黒、白、赤の三種混合のもの)/3 モーモー(肉餃子、時間がなくて皮は市販品)/4 鶏肉の甘辛トマト煮/その他、皆さんお持ちよりのスイーツなど。私の体力に余裕がなく、都内での集まりはできなかったけれども、こんな辺鄙な森の中まで訪ねていただいて、いわばランタン村民と交流できたことはテンバにとっても大変意味のあることだったと思います。
◆ランタン谷はネパールにいくつかある国立公園の一つで、1975年にランタンへの入山が可能になったが、国立公園として一般に開放されたのは1976年であった。ランタンといえば「ランタンリルン峰」、中学生のころから憧れていた山だった。母の購読していた婦人雑誌の写真ページを飽きずに眺めていた。一人の少年の背後に君臨する青い氷と聳える岸壁。そのころすでにたくさんのチベット・ヒマラヤに関する本に触れていたから、その写真からバター茶やチベット人たちの放つ生活の匂いまでがしているように思えた。
◆その年、1975年秋に寄宿していたユニセフの代理大使クロイ氏(ノルウェー人)を介して、ランタントレッキングに行くというブータン王室のお抱え医師(デンマーク人)夫妻に同行することにした。またとないチャンス到来だった。紙面の関係でキャンチェンまでの道中のことは省くが、ここでテンバの父親ダワに出会った。
◆ダワは牧畜専従のゴタルー。彼は突然に私のテントに現れ、「あの外人がガンジャ・ラを越えてヘランブーまで行くというんだ。雪用のメガネも手袋も靴もない。どうすればいいのか?」と問う。それに対して、「荷を担いで行けるところまで行きなさい。無理だと思ったら、引き返しなさい」とアドヴァイスした。デンマーク人の医師夫妻とはキャンチェンで別れたが、結局5500メートルの峠越えをやめて、ゴサインクンドの迂回路をとってヘランブーに向かったようだった。中年というより高齢に近く、無難な道を選択されたのだろう。
◆ランタンへはその翌年1976年にも出かけた。当時、ネパールの大学から奨学金を得て、ソル=クンブ地方の南、ジャサというチベット人キャンプを研究のテーマにしようとしていた。南西チベットからの難民で構成されたチベット人キャンプだった。しかし、その1976年のランタン訪問以降、ネパールの政治事情もあって、テーマをチベット人ではなくチベット系の人々に変更した。以来、今日まで本当に長すぎるランタンとのご縁が続いている。
◆1976年、ランタン村を目指してランタン・コラ右岸の山道に入ったところで、ダワに再会した。彼はお祭りのためのお米を買いに下の町まで出かけるところであったが、私に出会うと、すぐに私の荷物を引き取って、まっすぐに彼の家に向かった。ダワは婿養子で、家付きの娘リクチーと義両親、娘ばかり3人いた。1977年は1年間、出版する本の準備のために日本に一時帰国した。1978年、再びネパールへ。まっすぐランタンへ向かった。ダワは私が何も言わないのに、リクチーの家の貯蔵部屋(半分は長逗留の旅人たちが利用する炉のきってある小部屋)を少し広げて、私のための部屋を作ってくれた。私のランタンでの生活はこのようにして小部屋から始まった。家族は娘3人のうち真ん中の女の子を流行病で亡くし、半年前の1977年巳年に長男のテンバが誕生していた。続きは折々に 。[貞兼綾子 ランタンプラン]

■タキシード姿の白鵬さんに遭遇した。モンゴルからやってきた華々しいミュージカル、「モンゴル・ハーン」初日の開演直前の客席でのことだ。彼がこのミュージカルの日本公演アンバサダーに就任したのは、ことしの8月末。その 2ヶ月前、6月はじめに相撲協会を出ることが決まり、6月半ばに「世界相撲グランドスラム」の夢実現に向けた新会社設立を発表した。
◆私が気になっていた子どもたちの相撲登竜門「白鵬杯」は、来年以降も継続して開催されるらしい。ただし会場は両国国技館ではなく、青梅にオープンする「東京トヨタアリーナ」に変更。ここを、アマチュア相撲の聖地にしたいという。国技館ではないので、女子の相撲大会も同時開催できるし、国際色もより強まるかもしれない。白鵬の第2ラウンド開始のゴング音が聞こえた気がした。
◆さて「モンゴル・ハーン」というミュージカルは、モンゴル国内で 180回以上のロングラン上演後、シンガポールとロンドンでの上演を経て、現在東京と名古屋で上演されている。じつは、一部のモンゴル人たちから激しく非難され、炎上中の作品でもある。ミュージカル自体は、迫力があって、演出も独特の面白さがあり、素晴らしかった。赤、黄、青など原色が鮮やかな衣装は豪華絢爛。役者も魅力的。ステージが20度くらい傾斜して作られ、奥側が高くなっているので、35人のダンサー、4人のコントーショニスト(軟体芸)、13人のアクロバットパフォーマーたちの動きがしっかり見えるのもよかった。
◆すこしだけ、物語のあらすじを紹介したい。主役は、約3000年前のモンゴル高原で勢力をもっていたフンヌ(匈奴)帝国の架空の王。王の正妃と側妃が、ほぼ同時に男の子を産んだが、王は正妃と長らく一緒に寝ていない。驚きつつも、王は、側妃が産んだ子を後継にしようと決めた。ところが、正妃の子の父親である宰相が、自分の血が流れる子を将来の王にしようと、正妃と側妃の子どもをすり替えることを企む。こうして、王をとりまく、愛、嫉妬、復讐、憎しみなどの感情が、モンゴル伝統音楽と舞踊で表現されていくのが特徴的だ。
◆2時間以上のステージが終わると、最後のカーテンコールで、民族衣装のデールを着た演出家の男性が登場した。彼の名前はヒーロー・バータル。今年5月にウランバートルのスフバータル広場で起きた若者のデモで、息子の派手な金遣いを糾弾されて辞任に追いこまれたオユンエルデネ元首相の実兄で、この作品が炎上している所以だ。ちなみに、「バータル」という言葉には英雄という意味がある。モンゴル国民は、汗水流して納めた税金が、オユンエルデネ首相を介して、ヒーロー・バータルさんの手がける「モンゴル・ハーン」制作費に膨大に投入されたことを疑っている。「マネーロンダリングに使われた汚いミュージカルを、絶対見に行かないで!」と、これまで私は何人ものモンゴル人から釘を刺された。そのせいで行く予定はなかったのに、友人の小松由佳さんから「そんな背景があるのなら、ますます見たくなってしまった!」と誘われて(さすが小松さん)、一瞬で気が変わったのだった。
◆国の税金が本当に投入されたのか、真相はわからない。ただ、このミュージカルの宣伝チームで働く私の友人たちが、プロモーション目的で昨年から頻繁に来日し、東京都心部のホテルに滞在していた。また最近、都内数ヶ所のJR駅構内で「モンゴル・ハーン」の大きな看板を目撃。思わず調べたら、1ヶ所あたり50.100万円ほど費用がかかる。50人以上のキャストに加えてスタッフの渡航費、大掛かりな衣装や舞台セットの運送費も考えたら……莫大な予算がかかっているとみて間違いないだろう。チケット代は8,000円.18,000円。東京公演のチケットは、初日はほぼ完売、他の日も8割近く売れたと聞いたが、チケット代だけで、経費をカバーできるのだろうかと、頭のなかを数字が巡る。
◆ミュージカルのカーテンコールの別の主役は、白鵬さんだった。ヒーロー・バータルさんや駐日モンゴル国特命全権大使が挨拶したあと、マイクを渡された白鵬さんは、大きな花束を抱え、ステージ前方の中央に堂々と立ちながら、このミュージカルを初めて生で見て感動したこと、自身の日本との関わりなどを熱く長めに語った。そしてそのまま、ステージの幕がゆっくり降り、白鵬さんのリサイタルに来たのかと錯覚してしまいそうになった。彼のなかにある「ハーン(王)」の精神は、いまなお消えないのだと思う。
◆会場には、タキシード姿の俳優の浅野忠信さんの姿も(客席では白鵬さんと横綱豊昇龍関に挟まれ、窮屈そうに座っていた)。ミュージカル終演後、会場に立てられた金屏風の前で、なぜか浅野さんがモンゴル政府から北極星勲章を授与されていたので、驚いた。この賞は、モンゴルの経済や文化などの発展に貢献した人物に与えられる最高位の国家勲章のひとつ。受賞理由として唯一考えられるのは、彼が2008年公開の映画『モンゴル』で、チンギスハーン役を演じたこと。それにしても、なぜいま?海外でも話題になったドラマ「SHOGUN」で、今年のゴールデングローブ助演男優賞を獲得した“世界の浅野忠信”を、「モンゴル・ハーン」初日に呼ぶための口実なのではと、勘繰ってしまいそうになる。
◆初日上演後、SNS上では別の炎上騒動もあった。ミュージカルはモンゴル語で行われ、舞台の左右に日本語字幕が表示されたのだが、これがひどかったのだ。文字が小さくて読めなかったり、間違ったタイミングで表示されたり、縦書きなのに「ハーン」の「ー」が横向きで表示されていたり、文字化けの謎の記号が入っていたり……。初日上演後の夜、会場で観劇した翻訳担当の日本人研究者が抗議文を出す騒ぎになったが、翌日には改善されたという。原因は、モンゴルから持ってきた字幕機械が日本語対応のものではなかったことらしい。見た目は立派で派手なのに、肝心なところが適当なのも、モンゴルらしいのかもしれない。
◆さて、この連載のテーマに戻ると、「モンゴル・ハーン」には、モンゴルの音がふんだんに詰まっていた。舞台を彩る馬頭琴やホーミーの響き。伝統舞踊と一体のリズム。荒々しくも包みこむようなその音は、視界には到底おさまりきらない大草原と青空の国からやってきた力強さがある。低音から高音まで音域の広いホーミーは、耳を通りこして内臓にズンズン響くような感覚。役者の太い声、剣を交える音、音の演出も多層的だった。心理学の研究では、人が他者から受ける印象の割合は、見た目が55%、声が38%、話の内容が7%だという。声の占める割合が、意外と大きい。たしかに私自身、モンゴルに来たと実感するのは、視覚より聴覚だ。とくに、ウランバートルで乱雑に鳴りつづける車のクラクション。車を馬であるかのように操縦するドライバーたちの、自己主張のぶつかり合いを感じる。一度クラクションが鳴ると、それに続くように他の車も次々と鳴らし始め、まるで交響曲。気がつけば私も、その大合唱を「これぞモンゴル」と妙に嬉しく聞いているのだった。街を歩いていると、あちこちの建設現場から、コンコンという金属を打つ音が聞こえる。草原では、牛の鳴き声、子羊が母親を探す声が、無音の世界に響く。それらを耳で拾いながら、自分はいまモンゴルにいるんだなあと実感する。
◆今回が、この連載の最終回になる。音は、あえて録音しなければ永遠に消えてしまうもの。でも、記憶にこびりついて離れない音もある。消えてしまうからこそ、耳を澄ませたくもなる。人の本性や、そのときの状態は、見た目よりも声に表れるような気もする。声はお化粧ができないからだ。そして私は、明日からまたモンゴルに行ってしまおうか、どうしようかと、迷い始めている。すでに現地の気温はマイナスで、秋を通りこし、冬が来ている。懐かしい音も聞きたいし、新しい音にも出会いたい。読んでくださって、本当にありがとうございました。
■初めまして。法政大学探検部OBの桜井勝之と申します。1979年、「地平線会議」が誕生した年に探検部に入部しました。当時、岡村隆さんの誘いもあり、月例報告会には何度も参加して、様々な行動者の熱を感じられる報告に大いに刺激されました。森田靖郎さんから依頼されて、年報『地平線から1982』の原稿集めや編集のお手伝いなどもしていました。その後は仕事が多忙になり、転勤などもあり、地平線会議からは遠ざかってしまいました。それから40年以上も経過してしまいました。
◆私は岡村隆さんの10年後輩になります。現役時代もOBになってからも、岡村さんとはおつきあいをさせていただいていました。多分怒られていた場面のほうが多かったと思います。私が岡村さんに対して生意気にも探検論を挑むと、岡村さんは理路整然と私を論破しました。その後の酒席で愚痴をこぼすと、烈火のごとく怒られました。そうやって議論し怒られ鍛えられてきたと感じています。当時「探検とは何か」という議論を、機会ある毎に行っていました。探検という抽象的な概念は掴みづらく、部員を悩ませていました。一方で「探検とは文化的な侵略である」などという議論もありました。大学探検部の中には自己解体していく部もありました。そんな中で岡村さんは、議論を牽引する中核的な存在でした。人に会い、読書し、勉強を続けていました。
◆法政大学探検部OB会では毎年秋に「OBキャンプ」と称して関東が中心ですがキャンプを実施していました。多い時には30人くらい参加者がいました。現役部員も参加しており、交流の場としても機能していました。岡村さんもたびたび参加して、料理つくりや後輩たちとの再会を喜んでいました。これとは別に岡村さんと丹沢の低山に行ったことがあります。沢沿いにテントを張り1泊2日の山行でした。岡村さんと会うのは東京の居酒屋が圧倒的に多かったのですが、山で見る岡村さんの顔は生き生きとしていました。何か解放されたような雰囲気というか、その場に流れる空気全体を呼吸している、という感じの表情でした。フィールドに出て行動するのが本当に好きなんだろうな、と私には感じられました。
◆それはスリランカでもそうですし、モルディブでもそうだったと思います。それぞれの行動には遺跡探査という明確な目的がありますが、そのアプローチや幕営地では、野外で活動している喜びのようなものを感じていた、そしてそれが次の原動力になっていったと思います。70歳を過ぎても活動するには、やはり根源的な喜びのようなものがあったのだと、感じています。
◆私は仕事上で大きな窮地に陥ったことがあります(詳細には書けずすみません)。社会からも批判の声が寄せられました。その時に岡村さんは電話をかけて激励してくれました。一つは「逃げるな」「窮地にあっても物事の本質から逃げずに、きちんと向き合いなさい」ということ。辛くても苦しくても逃げずに対応することの大切さを話してくれました。もう一つは「迷惑がかかっている人がいないか確認すること」「人と人との関係の中で仕事も生活も成り立っているわけなので、そこは手を抜かずに確認すること」でした。自分一人で生きているわけではなく、必ず他者との関係性があります。そこに信頼関係がなければ、何かをなす意味もありません。この二つの言葉でどんなに支えてもらったか。自分を見失うことなく向き合うことができました。それからだいぶ時間がたったあとで感謝を伝えると「酒も飲もう」といってゴールデン街に誘ってくれました。
◆急逝した岡村さんは多面体の人だったと思います。地平線会議関係の人たちとのお付き合いをはじめ、他大学探検部関係者、出版関係者、山岳関係者、NPO法人関係者など多方面でのお付き合いがありました。それぞれの分野で中核的な存在でありました。その基底には「逃げずにきちんと向き合うこと」と「人と人との基本的な信頼関係」がありました。それ故これほど多方面で多くの人たちとの良き関係が築かれて行ったのだと思います。それにプラスして薩摩隼人としての熱い情があったと思います。
◆私が学生だったころ、OBも含めた忘年会を毎年行っていました。興にのった岡村さんが「刈り干切り歌」を歌っている姿が、いま脈絡もなく瞼に浮かんできました。♩ここの山の刈り干しゃすんだよ/あすは田圃で稲刈るかよ♩ 高千穂地方で歌われている、山の草を刈り取って干し、家畜に与える、という労働歌です。嬉しそうに歌う岡村さんの姿が私はとても好きでした。
◆12月中旬に岡村隆さんの追悼会を開こうと現在法政大学探検部OB会で準備を進めています。多くの分野の人たちに声掛けする予定です。岡村さんのことを語り、交流し、その意思を継承できるような会になればと思っています。[桜井勝之]
■私が岡村隆さんと初めて話をしたのはおそらく1979年の9月で、8月に設立されたばかりの地平線会議の今後を話し合おうと、四谷にあった喫茶店オハラIIに頻繁に集まっている頃だった。こちらはまだ学生で、憧れの大先輩たちの突き抜けた発想と熱い議論に毎回付いていくのがせいいっぱいだったから、岡村さんにどんな自己紹介をしたのか、何を話したのか、まったく憶えていない。
◆この頃の岡村さんはトラベルジャーナル社の仕事でかなり忙しかったようで、打ち合わせを終えるとそのまま編集部に戻っていくこともあった。先月も書いたように、岡村さんは年報『地平線から』のための情報収集の一環として、雑誌『Number』に地平線会議周辺の活動を紹介するページを持っていた。まだ30歳を少し越えたばかりなのに、探検界だけでなくメディア関係にも広範な人脈を築いて活躍している。理路整然と場の議論をまとめあげていく岡村さんの姿は、駆け出しの身にはとてもまぶしく映った。
◆1980年の1月、私は第5回の地平線報告会で初めてのパキスタンの旅を報告させてもらったのだが、終了後、惠谷治さんと岡村さんからものすごく褒めてもらった。この二人は大学探検部の活動にどっぷりとはまり、物見遊山の観光旅行や自己満足だけの探検ごっこのような軟弱な行動は地平線会議にはそぐわない、という硬派の考えの持ち主だったので、認めてもらえたことがとてもうれしかった。村に住み込んで現地の社会に溶け込み、居候生活をしてきたことに、モルディブで同様の体験をした岡村さんは共感を覚えてくれたのかもしれない。
◆その後はあまり岡村さんと話をした記憶がない。会社に所属して編集の仕事をしていると、月末の金曜日などという超忙しい日に開催されていた地平線報告会には、なかなか顔を出せなかったのだろう。
◆惠谷さんと岡村さんのコンビといえば、やはり誰もが「地平線オークション」を思い浮かべるに違いない。たしか最初は1986年の「『地平線から・6』発刊記念大集会」だったと思うが、年報の制作費や印刷費に充てようと、地平線のみんなが世界各地から持ち帰った物品をオークション形式で販売した。このとき惠谷さんと岡村さんが「競り人」をつとめてくれたのだが、香具師も顔負けの迫力あふれる啖呵売を繰り広げて、大いに会場を沸かせた。惠谷さんが品物を取り上げて「おお、これは……」とうんちくを傾けてもどこかうさん臭さが漂い、みんなが値を付けるのをためらっていると、すかさず岡村さんが博識ぶりを披露して鮮やかにフォローする。ときには瞬時に立場を入れ替えて、「はい、そこ! 3000円で落札!」などと岡村さんがびしっと決める。絶妙のコンビネーションで、最後まで目が離せなかった。この二人にはその後も何度か競り人となってもらったが、あの独特の間合いと迫力は誰が代わりにやっても再現できない。まさに地平線の伝説となっている。
◆先月も触れたように、私は1986年に子ども向け雑誌の取材で岡村さんをインタビューしたことがある。このときは日ごろ聞きにくいこともあえて聞いてしまえと突っ込んだのだが、岡村さんは文化人類学にほとんど関心がないことに驚いた。民俗学者の卵が出入りする観文研の出身なのになぜですかと尋ねてみると、どうやら最初のモルディブ滞在のときに、文化人類学的な調査では人々の心の奥底には迫れない、文学作品を通して表現するしかないと確信したかららしい。モルディブで過ごした二十歳のなまなましい体験は帰国後に原稿用紙300枚まで書いたが、これでは1000枚費やしてもとうてい書ききれないと、途中で投げ出してしまった。それが苦々しく感じられ、以後の人生の手かせ足かせになっていたという。その悔しい思いをやっと精算できたのが、14年ぶりの再訪となった1983年の『モルディブ漂流』(筑摩書房 1986)の旅だった。
◆2週間の休暇を申請して出かけたのに旅は1か月に及び、当然のごとく無断欠勤となった。おかげで帰国後は閑職に追いやられ、結局『モルディブ漂流』を書くために会社を辞めることになる。そして、フリーランスとなった岡村さんは、本を書き上げて出版した後に「見聞録」という編集プロダクションを立ち上げて、雑誌の企画ページや企業PR誌などの編集を請け負うようになった。プロダクションの得意分野が旅や観光だったので、出版関係者だけでなく探検の仲間たちも出入りしていたようだ。
◆その後、岡村さんは見聞録を畳んで作家となった。早稲田の探検部の重鎮で親交の深かった作家の船戸与一さんに焚きつけられたからだという。『モルディブ漂流』の執筆を通してノンフィクションで書けることの限界を痛感していたので、船戸さんの誘いに大いに心が動き、『泥河の果てまで』(講談社 1989)と『狩人たちの海』(早川書房 1992)の2冊の小説を上梓した。奥多摩に近い青梅市に仕事場を借りて執筆に集中しようとしたが、夜の飲み会のお誘いがけっこうあって、なかなかはかどらなかったそうだ。[丸山純]
■我が家の話である。猫の源次郎と暮らすようになってこの秋で10年になった。2015年8月3日、源次郎は信州上田城の庭で私の連れに拾われた。たまたま遊びにきていた2人の山友達と城に行ったら、人懐こい雄猫がいた。そのときの印象が強かったので翌日もう一度城を訪ねたらきのうの場所にはいない。
◆しかたない、帰ろうと歩きかけたら遠くからくだんの猫が鳴きながら飛んできたのだそうだ。「姉さん、これは連れ帰るしかないです」と友人に言われて連れ帰ることに。名は城主真田幸村の幼名を取って「源次郎」とした。当時推定1歳なのでいま11歳ほどか。
◆言いたいのはこの源次郎、かあちゃんにしか懐かないということだ。毎日一緒にいて、トイレの始末もしているし、かあちゃんが旅に出るときは食事の世話もちゃんとしてやるのに、だ。猫って、こんなに人を差別するの?[江本嘉伸]
 |
バレエから見たロシア
「2才の頃に見たボリショイ・バレエのビデオがあまりにステキで憧れちゃって」というのはバレエ研究者の梶彩子さん。病膏肓に入り、東京外大でロシア語専攻。サンクトペテルブルク大学修士課程へ進みます。 イタリアで生まれ、フランスで花咲き、ロシアで成熟したとも言われるバレエ。しかしロシア国内のバレエ史はあまり研究が進んでいません。彩子さんが着目したのは“不運な天才”とも称されるユダヤ系振付家、レオニード・ヤコプソン。 「少年時代、ロシア革命の混乱に巻き込まれて難に遭いますが、偶然日本の実業家の助けを得ます。バレエ界で活躍していた'67年にも来日。その後ヒロシマという作品を発表しますが上演禁止となり、レパートリーには残っていませんが、日本との縁を感じます」 彩子さんはコロナ禍の'21年から2年間ロシアに再度滞在して研究を進めます。修士時代の学友達が奇禍に遭ったことを知り、根強く残る男性優位の風潮やコネ社会の闇も垣間見ました。 今月は彩子さんに、ロシアバレエの魅力、そして戦争が影を落とす社会の明暗など、内側から見るロシアの今を語って頂きます。 |
地平線通信 558号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年10月15日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|